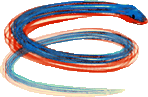
第11話
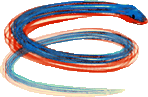
ゆりがこの世界にきて10ヶ月近くが経とうとしていた。ゆりはずっと城にいるので、そんなに季節の移り変わりとかを
感じることはない。近くの森も、そんなに紅葉することもなく、ずっと葉は緑のままだ。蛇の国も広いので、場所により
気温のばらつきがあるようだった。
暦は向こうと違い13ヶ月で、日にちもちょっと違って一月20日くらいである。20日だったり、22日だったりするので、
月の経過が向こうよりも早い。時間は向こうと同じ一日24時間だった。
ゆりはアヤコと文通して情報のやりとりをしていた。書いている文字はこちらの世界の文字である。
向こうの世界の文字は、書こうと思っても、書けなくなってしまった。こちらにいる以上は不都合はないのだが、
自分がすらすらと違う文字を書いているのは変な気分である。アヤコはまだ全然おなかが大きくならないらしい。
相変わらず食欲だけはあるようで、毎日食べては寝てるようだ。
蛇の一族と虎の一族では、やはりいろいろと違うようだった。
虎の一族にも交わりの月はあるが、あんまり関係なくしょっちゅう交わってるらしい。虎族は精力が強い一族のようだ。
交わりの月にはガットはかなり毛深くなる、とアヤコは言っていた。
ラクシュミも交わりの月には変化する、といっていたが、どう変わるのか、ゆりはまだ知らない。
まさか大蛇に化けるってことはないよね・・・交わるに交われないし・・・まあいいや。
持ち前の気楽さで、ゆりは気楽に考えて、あんまり気にしなかった。
もちろんこの生活に不満はあるが、それを言ってもしょうがない。王の結界の中だけがゆりがいける場所で、ゆりは
国の町並みも、景色のきれいな場所にもいけない。市場も。城の上の方から景色を眺めるだけだ。
それでも、文句は言わないことにした。
ラクシュミ自身は、王になってから城から外には出たことがないという。
城の中、特に王の間は力が使いやすい場所なので、外に出ると辛いそうだ。
ゆりはアヤコに手紙を書いて小包を作った。
中身は、カレーの香辛料である。新しく調合しなおしたのだ。
虎の国は暑い国なので、辛い物がうれしいらしい。
ゆりは侍女に小包を渡して届けてもらうようにした。
その時部屋にフリットが入ってきた。
「こんにちは。王妃」
「フリット。こんにちは」
「・・・?何か薬草の匂いのようなものがしますね?」
フリットは部屋の中を見て言った。
「うん。料理の材料もってきてたから」
「料理の材料?」
虎の国では大受けのカレーだが、蛇の国のみんなに食べさせたら、みんな顔をしかめた。
あんまり気に入らなかったようだ。
「フリットは何か用なの?」
「はい、羽がある蛇の子供ができたので、よかったら・・・」
「見たい!」
ゆりは瞬間移動で蛇の飼育場に連れて行ってもらった。城からちょっと離れたところに建物があり、そこに子蛇が
いっぱいいるのだ。藁を敷き詰めた上にいろんな色の小さい蛇がいて、すみの方に羽がある蛇を発見した。
「やだ、かわいいー!」
アヤコがもしきたら、悲鳴を上げて失神間違いなしであるが、ゆりにとってはかわいいのである。
「すごいかわいい羽ついてるね」
「まだ飛べないですけどね」
羽がある蛇は三匹いて、みんな眠っていた。
「ねえ、蛇ってここに来て卵産むの?」
ゆりは疑問に思って聞いてみた。
「そういう時もありますし、我々が持ってくる場合もありますよ。森の中だと、食べられることがありますからね。ここは安全です」
「そうなの。この国って蛇が最強かと思ってた。」
「森には獣のような生き物もいろいろいますよ。かなりでかい大蛇は最強ですけどね。ただ蛇も野生で育った方が強くたくましく
なりますから、たいていほっておきますけどね」
「そうなんだ。蛇ってかわいいのになあ、なんでアヤコさんあんなに嫌うかなあ・・」
ゆりはぶつぶつ言った。フリットは微笑んでいる。
「そろそろ部屋に戻りますか?」
「うん。ありがとうね」
ゆりは部屋に戻された。
「ねえ、フリットもうちょっと時間ある?」
「なんですか?」
「気もらっていい?」
「気?いいですよ」
フリットはラクシュミから聞いているのか、深く聞かなかった。
ゆりはフリットと隣り合って長椅子に座り、腕を組んだ。
フリットはどうするのか興味深そうに見ている。
「・・・なんだかうまくいかないなあ・・・」
気をもらおうと思ってももらえない。
「私が送りますか?」
「うん」
フリットはゆりの体を抱き寄せた。
え・・・・
ゆりはどきりとした。
するとふわっと何かが体に入ってきた。
「・・・あ・・・なんだかいい気分・・・」
「私もなにやらいい気分ですよ」
フリットが言う。
ゆりはからだを離した。
「ありがとう・・・」
性格と気は似ているのだろうか。なんだかフリットの気も優しい感じがする。
フリットが微笑み、ゆりの頬がちょっと赤く染まった。
その時部屋のドアがノックされた。侍女はいなかったのでゆりが自分で出ると、ミカエルがいた。
「こんにちは。王妃」
「ミカエル」
「今日もバラクでもどうですか?」
「今フリットがいるの」
ミカエルは部屋の中を見て、フリットと目を合わせた。そしてゆりを見た。
「・・・二人で何してたんですか?」
「何って、お話だよね、フリット」
「はい。」
「じゃあなんで王妃はそんな真っ赤になってるんです?」
「え?」
ゆりがミカエルを見たとき、フリットがミカエルに舌を出し、ミカエルの眉間にしわがよった。
ーお前なんかしただろ
ミカエルが思念を送った。
ー何もしてない。お前と一緒にするな
フリットが思念を返した。
ゆりは黙っている二人を見ている。
「では、私はそろそろ行きますね。王妃」
「うん。ありがとうね」
フリットは立ち上がり、出て行った。
「・・・ねえ、王妃、もしかして、フリットの気もらいました?」
「え?なんでわかるの」
ゆりが驚いて聞いた。
「あなたの気に、フリットの気が混じってるから」
「え?そんなの見えるの?」
「見えます。私のももらってほしいな」
ミカエルがにこやかに言った。
「・・・・いや、いい」
ゆりは拒絶した。
「どうしてです?」
ミカエルが眉をひそめて聞く。
「どうしてって・・」
ミカエルに抱きしめられるのはしゃれにならないよ。
100パーセント不倫気分になりそう。
「今日はもうもらったから。いいの」
「そうなんですか?じゃあ今度ね」
「そんな気遣ってくれなくていいから」
「なんでです?私の気ほしくないんですか?おいしいですよ?」
「手つないだだけでもらえる?」
「口付けであげたいです」
「・・・やっぱいい。せっかくだからバラクの相手してね」
ゆりあっさりかわしてゲーム盤を出してきた。でも頬は赤くなっている。
「つれないですねえ」
ミカエルはいすに座りながら言った。
「私は王妃よ。王様以外とはそんなことしないもん」
「本当に?」
「本当よ」
「あれからヴィラに会いました?」
ミカエルが突然いい、ゆりの目が見開いた。
「え・・・ヴィ、ヴィラ?だれだっけ」
といいつつゆりの頬はまた赤くなっている。
「あなたは嘘がつけないところがいいですね」
ミカエルは笑って駒を並べている。
「・・・・」
ゆりはちょっと気まずそうな顔をした。
「ヴィラもたまにここにくるんですか?」
「ううん。」
「じゃあどこで会ったんです?」
「あってないよ。顔知らないもの」
「嘘。」
「まあいいじゃない。別に、ミカエルには彼女いっぱいいるくせに」
「ヴィラにだっていますよ」
「じゃあ私からねー」
といってゆりは駒を進めた。ミカエルも進める。
「ミカエル別に私に気があるわけじゃないんでしょ?」
「ありますよ」
ミカエルがあっさり言って、ゆりは持っていた駒を落とした。
「え?またまた」
「最初からあなたを見てきたんですからね。気にしてますよ」
「あ、そういうこと・・・」
「だから、あなたが他の男と仲良くなると、さびしくなるんです」
「別に仲良くしてないよ。」
「ならいいですが・・・」
どうもミカエルって人をからかう趣味があるらしい、とゆりは感じた。
ふらふらしないように気をつけなくちゃ。
ゆりは自分に言い聞かせている。
だがミカエルほどのいい男にあんなふうにからかわれるのも、女としてうれしいものだ。
心のどこかでは喜んでいる自分がいる。
その日の夜更け、ヴィラがやってきた。
やっぱりミカエルには嘘ついたことになるのかなあ・・・
ちょっと複雑なゆりである。
「王妃、そろそろ、交わりの月の話をはじめますね」
「はい」
ゆりはベッドの上で正座した。
「我々は、その夜になると多少変わるんですが、王はかなり姿が変わられるようです。部屋の中は真っ暗にして、
最初の内は姿を見ないほうがいいでしょう」
ゆりの胸はどきどきしている。
「どう変わるの?」
「さあ。それはさすがにわかりません。交わりの月には性格さえ変わってしまう者もいますから、月が近づいてきたら、
絶対王と喧嘩などしないようにしてくださいね。」
「うん・・・わかった」
「それから、月の間は、絶対他の男の名前は言ってはいけません。その間は城の外にも出れませんからね。ずっと部屋の中に
いるんですよ」
「10日ずっと?」
「ええ。交わりの月の間、王妃は他の男に顔を見せてはならないという決まりがあるんですよ。他の男の事を考えても
だめですよ?」
「うん」
「怖いことばかりではないですからね。忙しい王も、その時ばかりはあなたとずっと一緒にいてくれますから」
「うん。そうね。大丈夫。きっと」
「あなたはいい王妃ですよ」
ヴィラが笑ったような気がした。
11の月の中ごろ、夕方になり、ミラがゆりに言った。
「王妃、王が今日は一緒に湯浴みをしたいそうです」
「・・・え?」
ゆりはぽかんとした。
「どうして?」
「さあ」
「・・・まあいいけど」
散々体を見られているので、いまさら恥ずかしがることもない。
王と王妃の浴室は別である。結婚して、ゆりはラクシュミと一緒にお風呂に入ったことはない。
ゆりは久しぶりに王のお風呂に入っていた。
・・・ぬるいなあ・・・
こちらはぬるいお風呂に入るのが普通らしい。体温がゆりより低いせいだろうけど、ゆりは自分のお風呂は、もっと
熱くしてもらっている。お風呂の湯の色は薄いピンクで、いい匂いがした。
しばらくすると、ラクシュミがやってきて、一緒のお風呂に入った。
「ねえ、どうして誘ったの?」
ゆりが聞いた。
「・・・覚えてないのか?お前がここに落ちてきたのが、去年の今日だ」
「え・・・・そろそろかなって思ったけど・・・」
初めてこの世界に来た時、気づいたらお風呂に落ちていたのだった。
ゆりは懐かしく思い出した。
「あの時は、まさか王様と結婚するなんて思いもよらなかった」
「それは私もだ」
「・・・」
ゆりの目から涙がこぼれてきて、ラクシュミが首をかしげた。
「どうした?」
「なんだか、いろいろ思い出して・・・王様にあえてよかった」
「私もお前に会えてよかった」
「本当にそう思ってる?」
「ああ」
「・・・じゃあ後で可愛がってくれる?」
ゆりが伺うように聞くと、ラクシュミが笑った。
「いいぞ」
ゆりもほほえんだ。
その夜は、なんだかいつもよりもラクシュミが身近に感じられたゆりだった。
年が変わり、交わりの月が近づいてくると、城の中はあわただしくなってきた。ミカエルやフリットも昼間こなくなり、
ゆりは侍女たちと過ごしている。
1の月の最後の夜、ヴィラがやってきた。
「王妃、私が来るのも今日が最後です」
「最後?」
「ええ。交わりの月が終われば、もう必要ないですからね」
「・・・」
最後、そういわれるとなにやら寂しい気がした。
「もう会えないの?」
「そんなことないですよ。交わりの月が終わった後なら、顔も見せられますよ。昼間に呼んでくだされば」
「そうなの?」
「あなたの好みの顔ではないかもしれないですが」
「どんな顔でもいいよ。どんな顔でもヴィラのこと好きだよ」
「言ったでしょう。他の男に好きなんていってはいけないと」
「ごめん」
「では、今日が最後の授業ですよ」
ヴィラはいろいろ話をしていき、今日は体には触らずに最後にそっと口付けをして出て行った。
これで、もう夜ヴィラが来ることはないのだ。
気持ちを切り替えなきゃ。
私もがんばろう。
その夜、ラクシュミが来た。
「ゆり、交わりの月は3の月の5日の夜からと決まったからな」
「うん。わかった。」
「・・・はりきってるな・・・」
「うん。私がんばる」
「・・・そうか・・・」
まあ前向きなのはいいことだ・・・・
とラクシュミは思った。
「私の姿が変わっても、大丈夫かな。お前」
「部屋真っ暗にしてるから、大丈夫だよ。きっと」
「そうか?」
この世界では、あまり異種族感の恋愛というものがうまくいかないことが多い。それは、交わりの月の変化のせいでも
あった。相手の姿が本能的に受け付けられない場合があるのだ。力が強いほど変化も大きく、逆に力が全くない者は
変化しないか、わずかにしか変わらない。
ゆりがあまりに楽天的なので、逆にラクシュミは驚いている。
なんといっても初めてだし・・・少々不安だが・・・
自分でも不安だ。なにせ、どういう性格になるか予想がつかない。
ラクシュミにとっても、自分の妻とのはじめて過ごす交わりの月である。前回はゆりが子供だったために何もなかったが、
今回はどうなるか見当がつかない。
無事過ぎればいいが・・・
あれやこれやと頭が痛いな・・・
ラクシュミの一番の悩みは一族の出生率がとても低いということだった。
何とか皆もその気になり、子供をなしてくれなければ、どうしようもない。
出産の女神ヒルデリアの力でも借りたいものだ・・・
こればかりは神頼みのラクシュミだった。