第12話
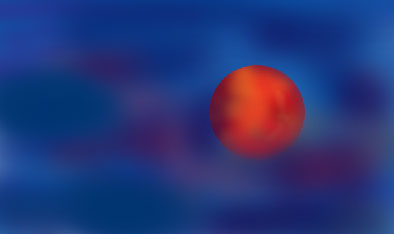
3の月の5日の晩、とうとう赤い月が夜空を照らした。
ゆりはその月を眺めて、カーテンを閉め、明かりを消してベッドにあがった。
部屋の中は真っ暗である。何も見えない。
ゆりは服を脱いで裸になった。そして、自分で自分の体に触れた。
ラクシュミにふれられているところを想像してふれていると、体の中が潤ってきた。
交わりの月についての知識は、いろいろヴィラから教わっていた。
最初の時は、すでに受け入れる態勢に体をしておいたほうがいいといったのもヴィラだ。
その時、ベッドの横に気配を感じた。ゆりは緊張した。
ラクシュミである。すでに姿は変わっているのだろうか。ゆりは怖かったので目を閉じていた。
「ゆり・・・」
ラクシュミがベッドに近づいてきた。
ゆりはごくりとつばを飲んだ。ラクシュミが布団をはぐり、ゆりの体の上に乗ってきた。
頬をなめられてぎょっとした。舌が、二つある。いや、分かれているのだ。
蛇・・・・やっぱり・・・
だが大蛇に化けているわけでもなさそうだ。ちゃんと人の形をしている。
手の感触も、いつもと違っているようだった。いつもよりもてかてかしている。
「ゆり・・・恐ろしいか?」
ラクシュミが耳元でささやくように聞いた。
「平気よ」
ゆりは緊張した声で言った。
ラクシュミはゆりの体をなめまわした。足を開き、下半身までも。
「あ・・・・」
それは、今までされたことがないことだった。手で触れられても、肌にキスされたことはなかったのだ。
舌が、体の中にまで入ってくる。
「ん・・・ああ・・・」
いつもされない愛撫にゆりは、快楽を感じ始めていた。姿が変わっていようが、別にかまわないという気になっている。
やがて、ラクシュミは顔をあげて、立ち上がった。ゆりの体がふわりと浮き上がる。
ラクシュミはゆりの腰をひいた。そして、自らの体を挿入した。
「あう・・・」
ゆりは体をのけぞらせた。ラクシュミはかまわずに奥までつながり、腰を動かした。
「あ・・・・ああ・・・」
ゆりはその圧迫感に驚いた。
いつもと違う。いつもよりなんか大きいんですけど・・・
「あ・・・あ・・」
「はあ・・・ああ・・・ゆり・・」
王様・・・王様が、荒い息はいてる。
ゆりは驚いた。ラクシュミが自分を抱いて感じている。
今まで荒い息なんて吐いたことないのに。
「ああ・・・」
うれしい・・・もっと感じて・・・
「ああ・・・・はあ・・・」
「ああ・・・!」
ゆりは奥で放たれた感触を感じた。
ラクシュミが体を離す。
「うれしい・・・」
ゆりはうれしかった。これで、本当に妻になったような気がした。
得体の知れない存在に抱かれたというのに。
「寝転んで足を広げろ」
ラクシュミがいい、ゆりは言われたとおりにした。
ラクシュミがゆりの上に乗り、抱いた。
「ああ・・・」
ゆりは痛みのあまりに顔をしかめた。いつもよりも乱暴に、からだの奥までつきあげられる。痛かったが、苦痛ではなかっ
た。ラクシュミが、自分を求めているのがわかるからだ。
「お前の身体・・・とてもいいぞ。からみついてくる・・・」
「王様・・・・」
ゆりはその晩、何度も抱かれた。しまいにはへとへとになり、為すがままになっていた。その行為には、苦痛が伴ったが、
ラクシュミに抱かれているというのがうれしくて、ゆりは抵抗しなかった。そして、自分でも知らないうちに、眠ってしま
っていた。
朝、ゆりが目覚めると、そこにはいつもと変わらないラクシュミがいた。
「王様・・・」
「体は大丈夫か?」
ラクシュミがいつもと変わらない声で聞いた。
「腰が、がくがく・・・」
「くくく・・・」
ん?王様こんな笑い方したっけ。
「お前の体がよすぎてつい責め立ててしまったな。これで体温がもう少し低ければ、最高の体なのだが、おしいな」
「・・・王様、いつもと目つきが違う・・・」
「そうか?」
「なんだか、感情的な気がする」
ラクシュミはにっと笑った。いつもはこんな笑い方はしない。
「お前が愛しいからだ。」
ラクシュミはゆりにキスした。舌は普通に戻っていた。
「ああ?」
ゆりは自分の体を見て驚いた。ところどころ、薄いピンクになっている。
「何これ・・・」
液体が乾いて肌についている感じだ。
「私が放ったものだ」
「ええ?」
「お前の中にも一杯いれた」
「お風呂入りたい・・・」
「気持ち悪いのか?」
ラクシュミは不快げに目を細めた。
やっぱり感情的だ。
「ううん。だって・・・」
「まあいいだろ。湯浴みしよう」
ゆりがあっと思った時には浴室に移動していた。湯船にはもうお湯がはってある。
ラクシュミはゆりの体を抱きしめたまま、湯に入った。体にお湯がしみて、ゆりは顔をしかめた。
「痛むか?じっとしてろ」
ラクシュミはゆりのおなかのあたりに手をあてた。すると、ゆりは体が楽になっていくのを感じた。
「女は見かけによらぬな。お前の身体がこれほどまでによいなどと、誰も思わぬだろう。」
胸をなでられて、ゆりはどきりとした。
「今までと比べてどうだった?」
「え?何が?」
「私に抱かれてどうだったか聞いている」
「王様が感じてくれて、うれしかった。」
「そうか、つらかったろう?」
「ううん、うれしかった」
ラクシュミが微笑んだ。
やっぱりいつもと違う・・・
感情豊かっていうのかな。
笑みも、なんだか柔らかい感じがする。
っていうか・・・別人だよ。これじゃ。おもしろすぎる。
お風呂から出て、ゆりはラクシュミと共に、部屋で朝食を食べた。
「こんなの初めてだからうれしい」
「そうか」
「お前、私と一緒にしたいことあるか?」
「したいこと?」
「この際だからな。」
「デートしたい」
「デエト?」
「一緒にあちこち歩きたい」
「外には出れないぞ。」
「お城の中でもいいよ」
「そうか。わかった」
ゆりはうれしそうに笑った。
「では、お前がまだ行った事がない地下室に連れて行ってやろうか。」
ゆりは地下に連れて行ってもらい、いろんな宝石などを見せてもらった。ラクシュミはゆりが聞く事には嫌がらずになんでも
丁寧に答えた。そしてその後は2人で寄り添って時々キスしながら話をした。
絶えずラクシュミの手がゆりの肌に触れている。
「王様・・・いつもよりいいにおい・・・」
いつもわずかに花の香りがするのだが、今日はさらに匂いがする。
「お前も私の匂いが好きか?」
「好き」
ゆりはうっとりして答えた。ラクシュミは妖しく微笑んだ。
王様・・・いつもよりいろっぽい。
「お前が欲しくなってきた」
「ええ?」
「お前がそのような顔をするからだぞ」
「ドンナ顔?」
ゆりが真っ赤になって言う。
「もの欲しそうな顔」
「な!」
「ふふふ。」
ゆりは顔を横に向けた。
「恥ずかしがることはない。来い」
ラクシュミはゆりの体を抱き上げてベッドに運んでいる。
えー?昨日あんなにしたのに昼間も!?
いくらなんでもやりすぎだろう。
ラクシュミはさっさとゆりの服を脱がしている。
そして体の上に乗ってきた。
「ねえ王様」
「なんだ?」
「私・・・く・・・口でしてみたいな・・・」
ゆりはおずおずといった。
「そうか?」
ラクシュミが体の上からどいた。
「ならそうしろ」
「うん」
ゆりはラクシュミの体を見てぎょっとした。すでにかなり興奮している。
一応体が辛いときはこういってみろ、とヴィラに言われたのだが、うまくいくかゆりはちょっと不安だった。
「どうしたんだ?」
「やり方教えて」
「ヴィラに教わったんじゃないのか?」
「王様に教えてもらえって言われた。」
「そうか、まあ自由にしてみろ」
「うん」
ゆりはラクシュミの体を口にいれて、舌でなめた。
手でさすりながら、しばらく口でしていると、ラクシュミがゆりの髪をなでた。
「なかなかいいぞ」
「本当?」
「ああ。こういうの好きか?」
「好き・・・」
別にいやではなかった。
手でなでながら、必死で奉仕した。
「ふふふ、かわいいな。お前は・・・」
必死なゆりの様子を見てラクシュミは微笑んでいる。男の体を口の中にいれているという事に、嫌悪感はなかった。
ラクシュミを喜ばせたい、その一心だったのだ。ゆりは根元から舌でなめたり、口に入れて動かしてみたりして
ラクシュミの反応を見た。
「どうされるのが一番気持ちいいの?」
「どれも気持ちいいぞ。本当にヴィラにはしてないのか?」
「してない」
「そうか。口に入れて動いてくれ。身体に入れているように」
「ん」
ゆりは言われた通りにした。
「お前の口の中はいいな。とても・・・」
「ん・・・ん・・」
「・・・いいぞ離しても」
ゆりが離すと、ラクシュミは達した。ゆりの胸元に精液がかかった。
「白い・・・ピンクかと思った」
ラクシュミはにっと笑ってゆりの体を抱き寄せた。
「お前はすごくかわいい」
「本当?」
「ああ、赤い月がこんなに楽しめてうれしいぞ」
その夜も、ラクシュミは変化してゆりを抱き、次の日は、ずっと側でゆりは抱き寄せられて、いろいろ話を聞いた。
今までにない濃厚な愛の時間にゆりは時折ぼんやりしてしまうほどだった。
朝でも昼でも夜でも、ラクシュミは側にいる。そして、いつでもキスしてくれるのだ。
いつもよりも優しい瞳で。
毎晩抱かれていたが、さすがにゆりは参ってしまい、最後の2日目は、ただラクシュミはよりそっているだけだった。
「今日で最後なんだよね。王様」
10日目の夜、ゆりは言った。
また、再び夜だけの生活に戻るのだ。なんだか悲しかった。
「また来年な。ゆり、お前はちゃんと私をずっと愛しているんだぞ?」
「うん。愛してるよ。王様、世界で一番愛してる」
ゆりはぎゅっとラクシュミに抱きついた。
たとえ姿が変わっていてもかまわない。
「ゆり、私もお前を愛してるぞ」
ラクシュミはゆりを抱きしめて言った。ゆりは初めて言われたその言葉がうれしくて、しばらく涙を流した。
次の日の朝、起きるともうラクシュミはいなかった。
夢の時間は終わったのだ。
なんだかすごーく濃厚な10日だったなあ。一年分愛された感じ。だから普段はそういう気にならないのかな。
あの王様とずっと過ごすとなると、ちょっと大変だもんな。
でもなんだか・・・寂しい気分・・・・
ゆりは10日ぶりに自分の部屋に戻った。
「ルー久しぶり」
ルーにあったのも10日ぶりだ。ルーはうれしそうに舌を出した。
「王妃!」
「ミラ!」
部屋の中にいたミラは、ゆりを見てぎょっとした。
「どうかした?」
「王妃・・・やつれましたね」
「え?そうかな?」
ゆりは鏡を見てみた。そういわれれば、やせた気もする。
ずっと責められたせいだろうか。
「だ、大丈夫ですか?その・・・大丈夫でした?」
ミラは聞きにくそうに言った。
「何とか大丈夫だったよ。大変って言えば、大変だったけど、かなり。」
でも王様3日目くらいは回数減らしてくれたし、気使ってくれたもんなあ。
「王妃、今日からしばらくは、こちらの部屋で休まれてくださいね」
「なんで?」
「交わりの月の後の男性というのは、ちょっとそっけないんですよ。ですから、そうした方がいいですよ」
「そうなんだ・・・」
「感情の落差が激しいですから、なれない内はちょっとお辛いかもしれません」
「わかった。」
「それから午後にはフレイ様が診察にみえますから、部屋にいてください」
「はーい」
午後、診察にきた医師のフレイも、ゆりを見て目を見開いた。
「そんなにやつれた?」
ゆりが自分の頬に触れて聞いた。
「大丈夫ですか?」
「うん。なんとか」
「体を見せてください」
「うん」
ゆりはベッドの上で上だけ裸になった。
フレイは老人の医者である。なので、裸になることにもあまり抵抗はない。
「・・・・」
「どうしたの?」
フレイがゆりの肌を見て固まっていたのでゆりが聞いた。
「今朝入浴されました?」
「ううん」
「そのせいですかね。王妃の肌から、いい匂いがしますよ。王と同じ」
「そうなの?」
フレイはゆりの肌のあちこちに触れた。
「やはり体もやせてますね。かなり激しかったですか?」
「時々は」
「いやではなかったですか?」
「やじゃなかった」
「ではよかったですか?」
「う・・・うん・・」
ゆりはちょっと恥ずかしそうに言った。
「そうですか。もう服を着ていいですよ。念のため、しばらく体を休めてくださいね」
「はい」
ゆりは服を着ながら言った。
「それから、また再び王はお忙しくなります。赤い月の後の男は冷たい態度を取りがちなので、王がそのような態度を
とっても、誤解しないでくださいね」
「うん。ミラにも言われたよ。」
「では、わしはこれで」
フレイは出て行った。
フレイはその後王の間に行き、ラクシュミと面会した。
「王妃の診察をしてきました」
「・・・どうだった?」
ラクシュミの顔は、すっかり元に戻っている。
「体は辛そうでしたが、感情的には、幸せだったみたいですよ?」
「そうなのか?」
「本当に何も覚えておられないのですか?」
「覚えてない」
ラクシュミは、赤い月の間のことを何も覚えていなかった。こんなことは初めてだ。
朝起きた時、ゆりの顔がえらくやつれていたので、ラクシュミは驚いたのだった。
まさかひどいことでもしたのだろうか・・・という気にさえなったのだ。
「それほどのめりこんでおられたのでしょうね」
フレイがからかうように言った。
「・・・」
ゆりはその日は普通に部屋にいたのだが、夕方のなると熱が出て、再びフレイが診察に来た。
「王妃、大丈夫ですか?」
フレイがゆりの額に触れると、ひどく熱かった。
「きっと疲れが出たのよ。大丈夫よ」
「熱冷ましを飲みましょうね」
フレイはかばんの中から薬を取り出した。
「それ、子供に影響ない?」
ゆりが聞いた。
「え?子供?」
「もしかしてできてるかもしれないでしょ?」
「・・・大丈夫ですよ。そんなに強いものではないので」
「そう、よかった」
ゆりは薬を飲んで、早めに休んだ。
次の日、熱は下がっていたが、体はだるかったので、ゆりはずっとベッドにいた。
食事も軽くすませている。
ミラや、他の侍女がずっと心配げにゆりを見ていた
「大丈夫よう。そんな顔しないでよ。みんな」
ゆりは明るく言うが、周りは気が気じゃない。
夕方になり、ちょっと容態が落ち着いたゆりは、お風呂に入りたくて仕方なくなってきた。
「誰か男の人連れてきて、お願い」
ゆりがお願いすると、ミラは仕方なく出て行き、ミカエルと一緒に戻ってきた。
「大丈夫ですか?王妃」
「うん。お風呂までお願い」
「はい」
ミカエルはゆりを抱き上げて、ちょっと驚いたような顔をした。
「何?」
「え・・・いえ・・・」
ゆりの体から、ラクシュミと同じ匂いが漂ってくる。それで驚いたのだ。
ミカエルは瞬間移動で王妃の浴室に移動した。
「後でまたきますね」
ミカエルがゆりを下ろそうとする。
「ちょっと待って。まだ用があるの。ねえ、あなたたちちょっとミカエルと二人きりにして」
脱衣所にいた侍女にゆりが言った。侍女たちが出て行った。
「王妃?」
ミカエルはゆりの目を見てぎょっとした。左目が、おかしかった。
黒目のところが黄色になっていて中に黒い丸い瞳があった。
ゆりはミカエルの頬に触れて、ミカエルの首に腕を回して、口付けた。
「・・・・!」
ミカエルの体から、大量の気が奪われていた。
「ごめんね。体が辛くて」
ゆりはミカエルの腕から下りていった。
「おかげでラクになったわ。ありがとミカエル」
ゆりがほほえんで言う。
「・・・私はこれで・・・」
ミカエルは脱衣所から出て、しばらく歩いてばったり倒れた。
「ミカエルが倒れた?」
王の間で、ラクシュミはフリットに報告を受けていた。
「はあ、王妃に大量の気を与えて倒れたようで」
「ばかか・・・」
ラクシュミがあきれていった。
「ですが王妃はちょっと元気になったようです」
「そうか。それはよかった」
それから三日ほどしてフレイが診察すると、ゆりはすっかり元気になっていた。
「ひとつ、王妃の体でかわったことがあるんですが」
フレイが王の間で言った。
「なんだ?」
「体から、王と同じ匂いを発せられてるんです。前の時は気のせいかと思ったんですが」
「ずっとひっついていたからではないのか?そのうち消えるだろう」
「そうだとは思いますが。」
「ミカエルのばかはどうなった」
「屋敷で休まれてますよ」
「全くばかなやつだ。そんなになるまで気をやるなんて」
ラクシュミはぶつぶつ言っている。
「はあ・・・」
その時、番兵がラクシュミのすぐ横に来た。
「王、ジュノー様がお倒れになりました」
「ん?」
「どこにいる?」
フレイが聞いた。
「救護室です」
「ちょっと見てきます」
フレイが瞬間移動で消えて、しばらくして戻ってきた。
「ミカエルと同じでした。王妃に気を与えたと」
「何?ゆりはそんなに気が不足してるのか?」
「先ほどはそのようなこといってませんでしたが」
「夜にちょっと会ってみよう」
ラクシュミは夜が暮れたころ、ゆりの部屋に飛んだ。ゆりはラクシュミを見ると喜んだ。交わりの月以来だ。
「王様。そっちにいってもいい?」
「すまん。もうちょっとここにいてくれ」
「はい」
ラクシュミはベッドに近づいて、ゆりをじろじろ眺めた。
「ゆり、男から気をもらうのはいいが、もうちょっと加減しろ」
ゆりは首をかしげた。
「相手が倒れるまでもらったらだめだ」
「何のこといってるの?」
「ん?今日ジュノーとあっただろう?」
「会ってないよ」
ラクシュミは奇妙な顔をしてゆりの頬に触れた。ラクシュミは肌に触れることで相手の心を読めるのだ。
「ジュノーから気をもらわなかったか?」
「もらってないよ」
嘘ではない。どういうことだ?
ラクシュミはゆりから手を離した。
「まあいい、体を大事にしろよ」
「うん。王様もね」
「ああ」
ラクシュミは優しくゆりの頭をなでて消えた。
その時、ゆりの左目の眼球がぱっと変わった。黄色と黒の瞳に。
ゆりは舌を出した。
「ごめんね。加減が難しくて。」
ゆりは笑って寝転んだ。