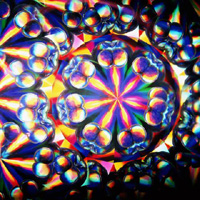
第15話
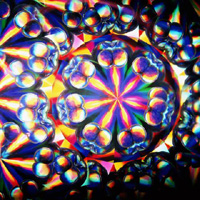
その日、ゆりはお城の地下にある部屋に来ていた。そこは、きれいなステンドガラスのようなガラス窓がはめ込まれた
部屋である。
先祖への祈りを捧げる場所だった。部屋の前方には、神棚のような物があり、お酒が捧げられている。
子供が無事産まれますように。
ゆりは両手をたたいてお祈りした。
「王妃」
ゆりは男に声をかけられて、後ろを向こうとしたが、向けなかった。
「あれ?」
男がゆりの後ろにぴったり立った。
「王妃・・・」
「ヴィラ?」
「そうですよ。」
「・・あなたが体止めてるの?」
「そうです。振り向きたいですか?」
「うーん・・・」
ヴィラの顔は見たい。
だけど、なんだかもったいないような気もする。
ヴィラはゆりの首筋をそっとなでていて、ゆりはどきりとした。
「なにやらあの時が懐かしいですね。今夜、部屋に忍んで行きたいんですが・・・」
「え?」
ゆりの頬が真っ赤になった。
「どうですか?」
「どうって、それはちょっとまずいんじゃ・・・」
「いや?」
「やじゃないけど・・・なんだか浮気みたいだし・・・」
なんだかすごくゆりの胸が騒いできた。
「あなたは王を愛してるでしょう?」
「うん」
「ならいいじゃないですか。」
ならいいって・・・なんでいいのかわかんないけど。
「あなたから王に言ってください。今夜私にあいたいって」
「私が言うの?」
「私からは言えませんよ。交わりの月の時の報告とか、いろいろ聞きたいんですよ。」
「う・・・・別に昼間でもいいと思うけど」
「じゃあ私の顔見ます?」
「・・・なんだかまだ見たくないな・・・王様に言ってみる」
「それでは後でね」
ヴィラは消えて、ゆりの体は動くようになった。
・・・つい言っちゃったけど・・・考えてみたらそんなこと王様に言っていいのかな。
そうだ。ついでにヴィラから気もらっちゃえ。
ゆりは王の間に行って番兵に話をすると、すぐ中に入れてくれた。
なんだか、最近みんな変だな・・・
なぜか二人の番兵は涙ぐんでいたし、ゆりの侍女たちも、妙に笑顔で、時々瞳がうるんでいる。
城の中ですれ違う人たちもそうだ。
王の間の中にはミカエルもいた。
「こんにちは。王妃」
ミカエルが笑みを浮かべて言った。
「こんにちは」
ラクシュミが指でこっちに来いとジェスチャーしたので、ゆりは側によっていった。
ラクシュミはゆりの手を軽く握った。
変といえば、王様も、最近なんだか優しい。
「安定期に入られましたね。おめでとうございます」
ミカエルが言う。
今朝のフレイの診察で、そういわれたのだ。
「ありがとう。もうあのメメント食べなくてよくなってほっとしたよ」
ゆりも笑っていった。
「それでは私はこれで」
ミカエルは瞬間移動で消えた。
「あのう、王様」
ゆりはラクシュミを見た。
「なんだ?」
「その・・・夜ヴィラにあってもいいかな?」
「ヴィラ?」
「いろいろ報告したいの。」
「いいが、なんで夜なんだ?もう昼間呼んでもいいぞ?」
「顔見るのがなんだかもったいなくて・・・お話しかしないからね」
「いいぞ。今夜お前の部屋に呼んでやる」
ラクシュミはあっさり言った。ゆりは瞬いた。
「王様ってあっさりしてるんだね」
「ん?」
「その・・・まあいいや。それじゃあね」
きっと私を信頼してくれてるのね、とゆりは思い、王の間を出て行った。ゆりはそのまま庭園の方に行った。すると、
東屋に一族の女性らしき女の人が二人いた。
ゆりはそのまま帰ろうかなと思ったが、女性の一人がゆりに近づいて誘ってくれた。
「少しお話でもいかがですか?王妃」
「うん」
にこやかに言ってくれたので、ゆりはお邪魔することにした。
「私はローズですわ」
青い髪の女性が言った。
「私はハルナと申します」
もう一人は緑っぽい髪をしている。どちらも美人である。蛇族の女性は、たいてい目が少し釣りあがっている印象が
あるが、この二人もそうだった。
「王妃がお元気そうでよかった」
「本当に」
二人はにこにこして言ってくれた。
「ありがとう」
「蛇の一件では、私たち感動いたしました。そこまで蛇を好いてくださっているなんて・・・」
「蛇たちもきっと同じ気持ちですわ」
「そ、そうかな・・・」
「ところで、王妃様にひとつお伺いしたいのですが・・・よろしいですか?」
ローズが言った。
「なあに?」
「王妃様の、お気に入りの男性はどなたでしょう?」
「お気に入り?王様」
「ほほほ、それはわかっておりますよ。王以外です」
ハルナが言う。
「みんな好きだよ。優しいし、いい人ばかりだから」
ゆりがにこにこして言った。
「だれが一番好みですか?」
「一番?一番って・・・わかんないよ。そんなの・・・」
「では一番信頼されてるのはだれですか?」
「うーん・・・みんな信頼してるけど・・・そうだ。一族の女性の一番人気はだれなの?」
「今はミカエル様ですかね」
「へーそうなんだ・・・ヴィラって人気ある?」
ゆりは思わず聞いた。
「ヴィラ様ですか?人気ありますよ」
「そうなんだ」
ってことはやっぱり美男じゃない。ヴィラの嘘尽き。顔がよくないなんていったくせに。
「ヴィラ様とたまに会われてるんですか?」
ローズがにこにこして聞いてきた。
「うん。たまにね。いい人だよね。ヴィラって」
ゆりは何気に言った。
「そうですね」
二人はニコニコして答えた。
ゆりはいろいろ話をして二人と別れたが、次の日には、どうも王妃のお気に入りはヴィラらしい、という噂が
巷で飛び交っていた、などゆりが知る由もない。
王妃に子供ができた、というのはここ50年ほどで最も喜ばしい話題であった。街の酒場でも、人々が陽気に酒を飲むように
なった。国の中がちょっと明るくなったのだ。そのことで一族の女性たちもゆりに興味を持つようになったのだった。
ゆりの好みはだれなのだろう、と気になりだしたのだ。
ちなみに王妃のお気に入りの男には、一族の女性たちもちょっと一目置くものなのだ。
その夜、ゆりは部屋を暗くして待っていた。
すると、ヴィラが瞬間移動で部屋に入ってきた。
「会いたかったですよ。王妃」
「ヴィラったら。でも、私もなんだか会いたかった」
ヴィラはゆりの横に座った。
「どうでしたか?交わりの月」
「王様がすっごくよかった。体は辛かったけど、優しくて、愛情にあふれてて、すごいよかったの」
ゆりがうれしそうに言った。
「よかった。うまくいくか気にしてたんですよ」
「王様の姿、結局よくわかんなかったけど大して気にならなかった」
「すごいですね。」
「そうかな」
「あなたはすごいですよ。王妃」
ヴィラは何気に体を寄せてきた。
「な、何?」
「久しぶりに肌に触れたいな」
「え・・・・?」
「いやですか?」
「だめだよ。どうしたの?あの時は、なんか私から近づくと警戒してたのに」
「あの時は、王との関係が不安定だったからですよ。でも今は、王を愛してるでしょう?すごく」
「うん」
「ならまあ、多少何があってもねえ・・・」
「多少って?」
ゆりの顔が引きつってきた。
「久しぶりにあなたを可愛がりたい」
「な、だめだよ!何言ってるのヴィラったら」
ゆりはからだを離した。顔はまっかっかだ。
「おや、つまらないですね」
「だーめ」
ゆりは舌を出した。かなり動悸が激しくなっている。
「まあいいですけどね〜」
その時、ゆりの左目が黄色と黒に変わってヴィラが目を見開いた。
「王妃?」
ゆりはじーとヴィラの顔を見ている。
「ヴィラって、ジュノーの顔に似てるね」
ゆりはそういった。
「おや、見えるんですか?」
「うん。左目では見えるよ。でも、目つきが悪いね。ジュノーより」
「ふふふ。よく言われます。私とジュノーの父親は兄弟なんですよ」
「そうなんだ。」
ゆりはヴィラに体を寄せた。
「ねえ、いちゃいちゃしましょ?」
「いいですよ」
ヴィラはゆりに顔を寄せて口付けた、
裸にして愛撫すると、ゆりの体はすぐに興奮状態になった。
「あ・・・ああ・・・」
ヴィラの指は、ゆりの体の中を出し入れしている。
淫らな音が、響いていた。
「ん・・・気持ちいい・・・」
「随分素直になりましたね。あなたの体。すごく反応がいいですよ?」
「あ・・・ああん!」
ゆりの体がのけぞった時、おなかに金色の小さな蛇が浮かんでヴィラはぎょっとした。
「・・・蛇紋」
「はあ・・・」
「あなたは一族の女なんですか?」
「あっちの時も出たよ。妊娠したからみたいよ」
「そうなんですか・・・」
ヴィラは蛇に触れた。蛇はそのうちに消えてしまった。
「前にね、フリットにされようとしたら、あっちに抵抗されたんだ。でも今日はされなかった。ヴィラならいいのかな」
「だめですよ。いろんな男としちゃ」
ヴィラがゆりの横に寝転んで言った。
「だって、せっかく王妃様なんだから、いい男と遊びたいもん」
ゆりはヴィラに体を寄せた。
「気ちょうだいね」
「いいですよ。」
ヴィラはゆりの髪をなでた。
「あなたは、他の男に抱かれても平気なんですか?」
「うーん。そこまではしない方がいいかな。」
「ひどいですねえ」
ヴィラが苦笑気味に言う。
「王妃様だからひどくてもいいの。」
ゆりは笑っていった。
その数日後、北の砦を訪れたミカエルは、そこの将軍ヴィクターがやけに妙な笑みを浮かべてくるのを見た。
「なんですか?」
ミカエルが聞いた。
「・・・いや、別に。」
「・・・何か言いたそうですが・・・」
「案外情けないな。ミカエル」
「???何の話です?」
「王妃と一番最初に近づいておきながら、王妃のお気に入りはヴィラらしいじゃないか。お前の父親も
情けないといってるぞ。きっと」
「・・・・は?」
ミカエルの顔が凍りついた。
「私もあと100年若かったら名乗りをあげるんだがな。最近王妃を見ているとなにやらかわいいと思うようになった。
交わりの月を過ごすと女はぐんと変わるからな。」
「ちょ、ちょっと待ってください。なんで王妃のお気に入りがヴィラという話が出てるんです?」
「女たちがみんな噂してたぞ。王妃がそういったらしいぞ」
「え・・・・」
いつの間にそんなことになってるんだ。
とりあえずそこでの仕事を済ませたミカエルだったが、頭の中はぐるぐると将軍の言葉が回っている。
一体どういうことなんだ・・・王妃はヴィラとあってるのか?
砦の休憩所をのぞくと、若い女戦士たちがキャッキャッとなにやら話していた。そして、皆ミカエルを見て口を閉ざした。
そこにはジュメもいた。
ミカエルはジュメを呼び出した。
「な、なんですか?ミカエル様」
「何の話してた」
ミカエルがじろりとにらむとジュメの顔がびくっとひきつった。
「何って、別に何も」
「嘘つけ、私の事はなしてたろ」
「自意識過剰ですね。」
ジュメが言うと、ミカエルの目つきが鋭くなった。
「何をそんなに怒ってるんですか?」
「王妃がヴィラを気に入ってるという噂が流れている」
「私も聞きましたよ。将軍が楽しそうに言ってました」
「最近王妃にあったか?」
「いいえ」
「ちょっと探りを入れてきてくれ」
「えー?なんで私が」
ジュメは抗議の声をあげた。
「私が聞いても教えてくれない。王妃がだめならミラにそれとなく聞いてきてくれ」
「ミラは無理だと思いますけど・・・まあいいです。次の休みにいってみます」
「頼む」
ジュメはジュメで興味を引かれて、ゆりに手紙を出して、その日にあってほしいと書いた。
ゆりからは心良い返事がきて、ジュメは休みの日に王妃の元に行ったのだった。
久しぶりにあったゆりはジュメの目から見て、なにやら女としての魅力にあふれて見えた。
「なんだかとても素敵になりましたね。王妃」
「まあ、ジュメったら」
「おなかに触ってもいいですか?」
「いいよ」
ジュメはゆりのおなかに触らせてもらった。
とっても幸せな気分だ。
「あれ?王妃の匂い・・・」
「なんだか王様と同じ匂いがするって言われたよ。みんなに」
「そうですよ。いいにおいです」
二人でにこにこしてたら侍女がお茶とお菓子を運んでくれた。ミラではなかった。
「ミラはいないんですか?」![]()
「休みだよ。」
「そうですか。」
「お茶しましょ」
「はい」
「最近、みんなの表情も明るくなりました。王妃のおかげです」
「私のおかげ?」
「今までは、憂さを晴らすためにお酒を飲んでいましたけれど、最近は、うれしいお酒になってます」
「そう。でもまだ、ちゃんと産まれるまではなんともいえないけどね」
「・・・あの・・・王妃は、お気に入りの男性っていますか?」
ジュメはずばり聞いてみた。
「お気に入り?王様」
「王以外ですよ〜」
「みんなお気に入りだよ。なんかこの前も聞かれたなあ」
「フリット様とかどうですか?」
「昨日あったよ。気もらったの。フリットって何かと気遣ってくれて、優しいよね」
実は女性たちの中では、ロアンナがゆりの相談役になったことから、フリットが有力だったりして、という
噂も出ていたのだった。
「じゃあミカエル様は?」
「ミカエルも好きだけど、なんか最近一緒にいると変なこと言ってくるんだよ」
「変なこと?」
「妙に迫ってくるの。」
ゆりが神妙な顔で言った。
「なんかミカエルってあの顔だからやばいよね。」
「や、やばい?」
「私いい男に弱いから困るよ。ああいう冗談は」
「・・・」
それは本気です。本気でくどいてるんですよ。
そういいたいジュメだったが、やめておいた。
実はラクシュミの母親である王妃の一番のお気に入りは、ミカエルの父親だった。戦いでなくなってしまったが、
その子供であるミカエルが王妃のお気に入りになりたいのもしょうがないことだ。
「じゃあヴィラ様はどうですか?」
「ヴィラ?ヴィラもいい人だよ」
おや?とジュメは思った。ゆりの頬がちょっと赤くなってきたからだ。
噂はまんざらでもないようだ。
ジュメはそれとなく話題を変えて、いろいろ話して出て行った。そして夕方ミカエルの屋敷に行った。
「・・・お前の言うことはよくわからないぞ」
ジュメの報告を全部聞いた後、ミカエルは言った。
「私が思うに、ミカエル様があからさまに誘惑するのがいやなんじゃないですか?」
「え・・・そんなに誘惑なんてしてないぞ」
「そうですか?何か警戒してる感じでしたよ」
「ヴィラのこと聞いたか?」
「ちょっとした思いがあるみたいですよ。ヴィラ様には」
「・・・」
ミカエルは口をへの字にした。
ジュメは上等な酒をもらって去って行った。
よくわからん・・・
最初の方は好みだといってくれたのに・・・
いつの間にヴィラのほうが上になってるんだ。
ミカエルは次の日の午後、ゆりの元に行ってみた。すると、ゆりはフリットとくっついていた。
「・・・王妃・・・」
「あ、ミカエル、こんにちは」
ゆりはフリットにくっついたまま言った。長椅子でフリットはゆりの体に腕を回して、ゆりは抱き寄せられているような
体勢である。
「今ちょっと具合悪くて、フリットに気もらってたの」
ゆりがだるそうに言った。
部屋の中には侍女もいて、別にゆりとしては妖しい気持ちはない。
「気なら私があげるのに」
「また今度ね〜」
ーお前変われ
ミカエルはフリットに思念を送った。
ーいやだ。それにこれは、王妃のご指名なんだ
ーなんでだ。なんで王妃がお前を指名する
ーさあ
「王妃、今度具合悪くなったら遠慮なく呼んでくださいね」
仕方なくミカエルは言って出て行った。
面白い奴・・・
フリットはふっと笑った。
「王妃、どうして私を指名してくれたんですか?」
フリットは聞いてみた。
「フリットって優しくてお兄さんみたいだから。」
「そうですか」
フリットは優しくほほえんで言った。
確かにあいつはお兄さんって雰囲気じゃないしな・・・・
「迷惑かけてごめんね」
「何を言ってるんですか。王妃、眠そうですね。ベッドのほうに行きましょう。何もしないから、安心して寝てください」
「うん。ありがとう」
ゆりはベッドの上でフリットに寄り添って眠った。
しばらくすると、ゆりは安らかな寝息をたてだした。
フリットはじっとしてゆりを見ている。
この体の中に王の子供がいる、そう思うと、愛しくてならない。
やがて、何か白いもやがふわっと出てきてフリットはそれに目を留めた。それはゆりの体の方からでてきたのだ。
よく見ると、それは赤ん坊のような形をしていた。目が見える。口も鼻も。髪も、
「あ・・・」
白いもやのような赤ん坊は、ベッドから降りて部屋の中を四つんばいで歩いていった。
部屋にいた侍女もそれを見てぎょっとしている。
ー王ー!
ラクシュミの元にフリットからのすごい思念が届いてラクシュミは驚いた。
ーな、なんだ!
ー早く!今すぐ王妃の部屋にきてください!早く!
「ゆりに何かあったようだぞ?」
「え?」
その時王の間にはラクシュミのほかにザメハと南の砦の将軍がいた。
ラクシュミが部屋に飛び、後の二人も続いた。
ラクシュミはゆりの部屋で、床にちょこんと座っている赤ん坊のようなものを見た。
赤ん坊は白みがかっていて、どこかぼんやりしていた。ルーと他の蛇を持って遊んでいる。
奥のベッドを見ると、フリットは座って泣いていた。
「ゆりは?」
「眠ってます」
「これは!」
「おお、なんとかわいらしい!」
ザメハと将軍が赤ん坊を見て言った。
二人とも、涙がだーと流れている。
やがて部屋の中に大勢人が集まってきた。みんな赤ん坊の姿を見ては泣いている。
夢ではないのだ。
ちゃんと王妃の体に赤ん坊がいる。
我らの希望が!
ラクシュミ自身でさえ、どこか半信半疑の部分があったが、こうして目の前で見ると、
信じざるをえない。
「うーん・・・」
ゆりが寝返りを打った。
「もうそろそろ帰れ」
ラクシュミが優しく言うと、赤ん坊はラクシュミに両手をのばした。どうやら連れて行けといってるらしい。
ラクシュミは赤ん坊の体を抱き上げて、ゆりの体の上においた。全く体重はなかった。
赤ん坊はみんなにばいばいと手を振って、ふっと消えた。
ゆりは目を開けて、部屋の中にいっぱい人がいたのでぎょっとした。
しかもみんな泣いている。中には号泣しているものもいる。
「だれが死んだの?」
ゆりは不安そうに聞いた。
その後、自分の子供が現れたと知って、悔しがったゆりだった。
「ねえ、王様、子供って、男の子だった?」
夜ゆりはラクシュミに聞いてみた。
「そこまでは見えなかったぞ」
「そうなんだ」
「男だと思うのか?」
「どっちでもいいけど、そうかなって」
「私は女だと思うぞ」
「そうなの?元気ならどっちでもいいけどね」
「ああ」
ゆりはラクシュミに寄り添った。
「抱いてほしいか?」
「うん」
ゆりはラクシュミに抱かれた。
なんだろう・・・なんだか、蛇が浮かぶ。
脳裏に大きな蛇の姿が浮かんだ。黒っぽくて、透けていた。
「蛇・・・」
「ん?」
ラクシュミが聞いた。
「なんでもない」
夢の中にも蛇が出てきた。
別に恐ろしくはなかったが、蛇はなにやらいいたそうにゆりを見ていた。