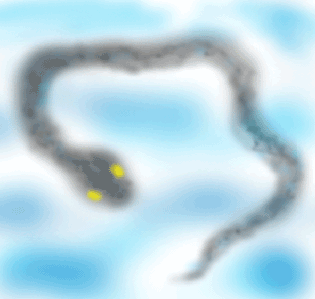
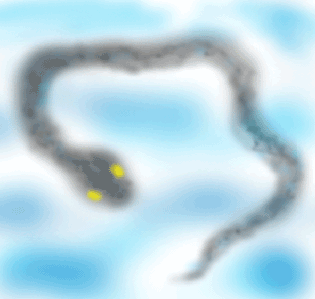
最近やたら夢の中に蛇が浮かんでくる。
すごく大きな蛇で、宙を泳いでいる不思議な蛇。
蛇はまるで幻影のように透けて見える
あの蛇はなんなのだろう。
第16話 〜儀式〜
ゆりはその夜も、ラクシュミに抱かれていた。
ラクシュミの上にまたがり、自分で腰を動かしている。
「あ・・・ああ・・・」
ゆりは淫らに髪を振り乱している。
やがて達すると、ラクシュミはゆりの体を抱き寄せた。
「最近毎日だな。大丈夫か?」
ラクシュミが聞いた。
「うん・・・ごめんね・・」
ここの5日ほど所、毎日のようにゆりはラクシュミを求めていた。
なぜか性欲がぐんと増しているのだ。
「ごめんね。ごめんね」
ゆりがしくしくと泣き出した。
「なぜ泣く。泣くな」
ラクシュミは優しくゆりの髪をなでた。
最近変。とうとう、淫乱ってやつになったんだろうか・・・
ラクシュミに夜抱かれても、昼間一人でいると、なんだか体の奥がむずむずしてくるのだった。
まさか昼間からそんなことができるわけでもないから、ゆりは我慢してるが、そういう気持ちになるってことが、
いやでたまらない。
次の日の午後、ゆりは気を紛らわすために庭園を散歩していた。
空はちょっと曇っている。
ゆりの横にはミラもいた。
庭園は結構広いので、歩き回っていれば、一応運動にもなる。
その時、ジュノーが飛んできた。
「こんにちは。王妃」
ジュノーは優しい顔で言った。
「こんにちは」
ゆりがジュノーを見て言う。
「お散歩ですか?」
「うん。運動」
「そうですか、最近気はいらないんですか?」
「今大丈夫よ」
「いる時は言ってくださいね」
「ありがとう」
ジュノーって・・・素敵ね・・・
ん?私何考えてるんだろう。
ゆりは自分の考えに戸惑った。
なんだか胸がどきどきしてくる。
「王妃?なんだか顔が赤いですよ?」
ジュノーが心配げにゆりの頬に触れた。
「真っ赤ですよ。熱あるんじゃないですか?」
その手がゆりの額に触れる。
どきどきが頂点に達したゆりは、ジュノーに抱きついていた。
「・・・王妃?」
ジュノーはきょとんとして、ミラは大きな目をさらに見開いている。
「あれ?」
ゆりは正気に戻って体を離した。
「わ、私今なにかした?」
「・・・」
ゆりの顔は燃えるように赤くなり、「ごめんなさ〜い!」といって走って逃げた。
「?」
ジュノーは首をかしげた。
「王妃!」
ミラが追いかけた。
わ、わたしってば、何してんのよ!
欲求不満にほどがある!
って言うか、別に欲求不満じゃないはずなのに
他の男にときめくなんてだめじゃんよー!ばかばか!
ゆりはよろけながら自分の部屋に戻ってぎょっとした。中にミカエルがいたからだった。
「こんにちは。王妃」
「な・・なんで?何してるのここで」
ゆりの顔は引きつっている。今一番見たくない顔だった。
「王妃が全然呼んでくれないから、きました」
「え?・・・今気いらないから」
「そうなんですか?では話でも」
「いや!」
ゆりがでかい声で言って、ミカエルはびっくりした。
「どうしたんですか?」
「今はだれとも話できないの。ごめんね。出て行って!」
言いながらもゆりの胸はどきどきしている。
「・・・」
ミカエルがさびしそうな顔をした。
「お願いだから出て!」
「わかりました」
ミカエルはさびしそうに出て行った。
あーミカエルってやっぱりいい男![]()
考えてはっとする。
何考えてるの私・・・
あなた人妻よ。
しかも子供までおなかにいるってのに
何考えてるのよ!
ゆりは自己嫌悪に陥っていた。
そのころ、ラクシュミは休憩室で、酒を飲んでいた。一緒にいたのは北の砦の将軍、ヴィクターである。
「フレイに聞いたんだが、ヴィクターは私の母の恋人だったんだったな」
「はあ、恋人といわれれば、そうでしたね」
ヴィクターは答えた。ヴィクターはラクシュミよりもかなり年上である。年齢も100ほど違う。といってもまだ元気だし、
ゆりの国の年齢でいえば、40才くらいというところである。王妃は一族の男に限り、自由にだれでも恋人にすることができるのだ。
「フレイはなにやら言いにくそうにしていたが、妊娠中に儀式があったんだろ?」
「・・・はい、蛇霊神を取り込む儀式をしました。もうひとつは古の王ザクート王を召喚する儀式でしたが・・」
「儀式ってどんなだ?」
「・・・いいにくいです。非常に」
「言ってくれ」
「・・・男たちが王妃と交わるんです」
「やはりそうなのか・・・」
ラクシュミはため息をついた。
「大昔は巫女がその役をやっていたようですが、巫女がいなくなっために、王妃自身が儀式をやらなければならないとかで、ご存知の
通り、一族の女性は普段はそう性欲を感じませんから、儀式までが大変でした。儀式になれば巫女がおりてくるのですが」
「男は何人いた」
「10人です」
「そんなにいたのか?」
ラクシュミが目を見開く。
「はあ・・・」
「ゆりにそれをやらすのは無理だろ。どう考えても」
「ザクート王の儀式はやった方がいいと思いますが、赤ん坊に保護の魔法をかけてくださるんです。」
古の王ザクートとは、蛇の国の歴史上、最も力がある偉大な王といわれた王だった。
「それも同じなのか?」
「そっちは、よくわかりません。呼ぶのは王妃ではなく、蛇ですから、」
「蛇?」
「やろうと思ってできるものでもなく、いつ起こるかも全くわからないんです。王妃と交わったことは交わったんですが・・・」
「はあ・・・困ったな・・・」
「王妃はその、他に恋人は」
「ゆりは私以外とはしたことがない。前に言ったら、いやだといっていた。」
「そうですか。」
まさか無理やり10人の男とやらすわけにもいかない。
そんなことをすれば、死んだふりどころか、どっかいってしまうかもしれない。
前回ゆりの死体を見せられるというひどい目に合わされたラクシュミなだけに、強引なことはできなかった。
ラクシュミが夜寝室に行くと、ゆりはいなかった。枕元に紙がおいてあった。
しばらく自分の部屋で休みます。 ゆり
そう書かれていた。
ラクシュミはベッドで寝転んだ。
すると、ぱっと横にゆりが来た。
左目は黄色と黒になっている。
「ゆり。どうして向こうで休むんだ?」
ラクシュミは聞いてみた。
「王様の顔みたらまたやりたくなるからみたい」
「そうか」
「・・・ねえ王様、最近変なんだよ。すっごいやりたくてたまらないの」
「ん?お前がか?」
「ううん。向こう。それで何か落ち込んでるよ」
「・・・」
ラクシュミは体を起こした。
「それって他の男でもやりたくなるのか?」
「うん」
「・・・儀式が関係してるのか?」
「儀式って何?」
ラクシュミはこちらのゆりに説明した。
「へえ、そんなのあるんだ。蛇霊神っての呼んだら何かいいことあるの?」
「子供の力があがるらしい」
「じゃあやらなきゃ」
「そういってもな・・・ゆりが簡単に他の男とするか?」
「王様が相手すれば?」
「男10人とするものを、私一人で相手はできないぞ?」
いくらなんでもそんな体力はない。
「私ならやってもいいよ」
ゆりが気楽に言った。
「本当か?」
「うん。だけど、向こうが抵抗するかもしれない。それに男10人はちょっと無理よ。体壊れちゃうよ。まずは二人ぐらいからで様子
みないと」
「・・・お前が抱かれたら、向こうのゆりは大丈夫かな」
「愛撫だけさせればいんじゃないの?私が気持ちよくなればいいんでしょ?」
「さあ、よくわからん。できることならやらせたくないんだぞ。私は」
「子供のためだからしょうがないじゃなーい」
ゆりはどこか楽しそうだった。
変な女だ・・・
瞳が変わったゆりは、瞬間移動もできるし、一族の女っぽいのだが、性格は全くそうというわけでもないようだ。
第一、一族の女は、普段は男に触れられるのを喜ばない。やはりそこは、体が違うからだろうか。
そして次の日の夜、ゆりの寝室にミカエルとフリットがやってきた。二人とも普段着だ。
「こんばんは。王妃」
「こんばんわ」
二人ともうれしそうだった。
ゆりは湯浴みもして、寝巻きを着ている。
「かわいいですね。それ」
フリットが言った。
「ふふ」
フリットはゆりの体を抱きしめた。
「・・・なんか雰囲気あやしいな」
ミカエルが言った。
「フリットとはもう裸で抱き合った仲なの」
ゆりがあやしく言った。
「いつの間に?」
「だめですよ。ミカエルはすぐ妬くんだから」
「私のことは避けるくせに。なんで・・・」
「まあいいじゃない。今日は仲良くなれるし、多分。あっちが抵抗しなかったらだけど」
「愛撫だけしろって王はいってましたよ?」
フリットが言った。
「うん。じゃあ、さっそく」
ゆりはベッドに上がった。二人もあがり、上着を脱いだ。
「わお、ミカエルの蛇って紫ね」
ゆりはミカエルの背中を見て言った。紫の蛇がいる。
「じゃあフリットから」
ゆりはあっさり言った。
「なんでです?」
ミカエルは不服そうだった。
「だって、ミカエルって刺激強そうだから、まずはフリットにそっとやってもらう」
「そっとですね」
フリットは優しくゆりを抱きしめて、軽く頬にキスしていった。
頬を優しくなでながら、、唇を覆ってみた。
あ・・・今日は大丈夫みたい・・・昼間激しく興奮してたせいかな・・・・
「大丈夫ですか?」
「うん・・・続けて」
フリットは優しくゆりの服を脱がして、肌に触れた。
優しく触れられていたら、ゆりも興奮してきた。
フリットの背中に腕を回して、抱きついている。
二人はやがて、激しくキスしだした。
ミカエルは仕方なく、それをじっと見ている。
蛇の目を持つゆりは、王以外の男に何をされてもあんまり抵抗を感じない女だった。
だが、普段のゆりとは違い、キスされても、肌に触れられても、頬が赤く染まったり、というようなことはない。
男たちに好意はあっても、それ以上の感情はもってはいないのだ。
フリットはゆりの胸をなでて、下半身をまさぐっていた。
「ん・・・」
フリットの舌が優しくゆりの胸をなめまわした。
「あん・・・」
フリットの指がゆりの体の中に入ってくる。
「すごくその気になってくれて、うれしいですよ」
体の中は、うるおっていて、指は何の抵抗もなく入って行った。
「あ・・・あああ・・・」
指を動かされて、ゆりはいってしまった。その瞬間、ゆりのおなかに金色の小さな蛇が浮かんで、フリットはぎょっとした。
「すごい・・・」
「なんだ?」
ミカエルからは見えなかった。
「金色の蛇だ。」
フリットが体をどけて、ミカエルの目にも入った。
「本当だ。これはすごい。初めてみましたよ。」
二人は興奮している。
「次ミカエルきて」
ゆりが手を伸ばした。
「はい、待ちわびましたよ」
ミカエルはゆりの上に乗った。
ミカエルの愛撫は、フリットよりも激しく、やはり刺激的だった。
ゆりは早めに達してしまった。ミカエルはそれでも、ゆりの体の中に指を入れている。
「ねえ、王妃、ここに入りたいな・・・」
ミカエルはゆりを抱きしめたまま言った。
「あ・・・・」
「このやわらかい所に入りたい」
「ミカエルやめろ」
フリットが軽くとがめた。
ゆりはじっとミカエルを見上げた。
「いやですか?王妃」
「・・・試してみる?」
「はい」
ゆりは足を広げて、ミカエルはズボンを下ろして自分の体をあてがった。
その時、ゆりは思いっきりミカエルの肩のあたりをけとばした。
「王妃」
「無理みたい。抵抗された、強引にやったら向こうが起きるかもしれない」
「そうですか。残念ですね。」
ミカエルは仕方なくズボンをはいた。
「ごめんね」
「いいんですよ。」
二人はそれぞれゆりにキスして去って行った。
儀式かあ・・・よくわからないなあ・・・・
気持ちよかったけど・・・
まあいいや。明日はジュノーとヴィラ呼んでもらおう。
ゆりは次の日の晩、ジュノーとヴィラと、同じようにしてもらった。
だが、別にそれだけだった。
ラクシュミの母親の時は、その気になるような香を使って王妃が男たちと交わり、それで儀式になったらしい。
もっと興奮しないとだめなのかしら。
でもあんまり激しくすると、向こうが起きちゃうし・・・
突然目の前に裸の男がいたら混乱してしまうだろう。
次の日の晩は、ゆりは王の寝室でラクシュミに報告した。
「まあ、別に儀式がないならないでしょうがないだろう。ここは、ゆりの心の方が大事だ」
心が壊れては、どうにもならないのだから
子供の力が多少落ちても仕方がない
そうラクシュミは思っている。
「王様って物分りいいのね。」
「ゆりが一族の女ならやらせるが、価値観が違うのだから仕方がない。」
「でもさ、向こう、性欲あがってるんだよね。何か関係あるんじゃないかな。夜に、ヴィラにちょっと強引にしてもらってみたら
どうかな」
「しかしな・・・」
「ヴィラならうまくやるよ。無理ならやめてもらえばいいし」
「・・・そうだな・・・ところで、お前が出てる時って向こうは全く記憶ないのか?おかしいと思わないのか?」
「適当に記憶つないでるみたいよ。」
「そうか・・・」
そしてその次の晩ゆりは、自分の部屋で寝ていた。
相変わらず、性欲があって仕方がない、ゆりは自分で自分の胸をまさぐったりしてみたが、なんともおさまらない。
明日は王様にしてもらおうっと・・・・
もうそろそろいいよね。
二晩にわたって男がここにきたなど、今のゆりは全然知らなかった。
なんだか眠れないなあ・・・・
その時、ベッドの横に不意に人影が見えてゆりはびっくりした。
「あ・・あれ?ヴィラ?」
「そうですよ。王妃」
ヴィラは顔を寄せていった。
「どうしたの?今日は何?」
「あなたに会いたくてきてしまいました。」
「え?」
「王妃は私に会いたくなかったですか?」
「・・・別に」
「つれないですね」
「だめよ。王妃の寝室に忍んできたら」
ゆりの胸はどきどきしてきた。
「なら話だけして帰りますよ」
「・・・・」
体の奥が熱い・・・・
ヴィラはゆりの頬をなでた。
「熱いですね。とても。」
「触っちゃだめ・・・」
「あなた、性欲があがってるんじゃないんですか?」
「え?」
「王妃は子供を孕むと、そういうことがあるみたいですよ。だから、恥ずかしくないんですよ?」
「やだ、恥ずかしい」
「満たされたかったら私を呼んでください。王妃」
ヴィラはゆりの唇を覆った。
「ん・・」
ゆりが顔を背けて抵抗する。
「王妃・・・素直になって・・・前のように・・」
「ヴィラ・・・・」
ゆりは不意に前のことを思い出してしまった。
前のように愛撫されたい、そう思ってしまったのだ。
今度は授業じゃなく、優しくされたい・・・
ヴィラは布団に入り、横からそっとゆりを抱きしめて口付けた。
激しく口付けながらゆりの服を脱がせて、愛撫した。
「あ・・・ヴィラ・・・」
理性を離すと、ゆりはそのまま欲望へと身をゆだねた。
「あ・・・ああ・・・」
ヴィラはゆりの胸をなでてゆりの足を広げて、舌で下半身を愛撫しながら、指を差し入れていた。
ゆりの体がびくびく痙攣している。
「気持ちいいいですか?」
「いい・・・・はあん・・」
やがてゆりは達した。
以前よりもかなり体は快楽を感じやすくなっているとヴィラは感じていた。
「はあ・・・」
「とてもかわいいですよ。王妃」
ヴィラはゆりの髪をなでた。
「私も・・・・あなたに何かしたい・・・」
ゆりはうるんだ瞳を向けていった。
「何か?」
「口でしたい」
「え?」
「あなたをいかせたい」
「王妃・・・・ああいう行為は、身分の高い女が、身分の低い男にはしないんですよ?」
「でもしたい」
「・・・わかりました・・・」
ヴィラは服を全部脱いで裸になった。
「どうぞ」
ヴィラはゆりの口元に、自分の下半身を近づけた。ゆりはそれを手探りでさわり、口に入れた。
「・・・う・・・」
あまりにうまい舌使いだったので、ヴィラは思わずうめいた。
ゆりは何の抵抗もなく口で奉仕している。手でさすりながら、口を動かしていた。
「気持ちいい?」
「よすぎますよ・・・」
「ふふ・・・びくびくってしてる・・」
「・・・・」
ゆりは楽しむように口で奉仕していた。
「はあ・・・・ああ・・・王妃・・・も、もういいです」
ヴィラは口から離して、達した。
「とてもよかったですよ。王妃」
「・・・もう一人くらいとこうしたいな・・・・」
ゆりはぽつりと言った。
「だれか呼びましょうか?だれがいいですか?」
「・・・こんなことしても私を軽蔑しない人」
「だれも軽蔑しませんよ。ジュノーでいいですか?」
「うん」
やがてジュノーがやってきた。ジュノーは何も聞かずに、ゆりの体を抱き寄せた。
「ジュノー・・・」
「可愛い王妃」
ゆりは抵抗なく身をゆだねている。瞳はとろんとしていた。
ジュノーはゆりに口付けた。やがて愛撫されて達すると、ゆりはまた口でしたいといいだした。
ジュノーは戸惑ったが、ヴィラが視線を送り、ジュノーも裸になった。
やがてジュノーも達した時、ゆりの顔つきが変わった。少し目じりがあがっている。
「王妃?」
「もっと、もっと愛して」
ゆりはギラリと光る瞳を向けて言った。その体からは、妖しげな気がたちのぼっていた。
「王妃・・」
ヴィラはゆりを抱きしめた。
「愛して。私を愛して」
「愛してますよ。王妃」
ゆりの体から発する妖しげな気は、二人の男を変化させていた。それぞれ瞳の色は変わり、体の蛇は、濃くなっている。
ゆりの肌には、大きな金色の蛇が現れてゆりの体を取り囲んでいた。
「美しい・・・」
ジュノーが言った。一族の男は女の蛇紋を見ると興奮してしまうのだ。
二人の男はゆりの肌に触れて、ゆりの体を愛撫し、ゆりも、男の体を愛撫している。
一人の下半身を口で奉仕しながら、もう一人の体には手を伸ばしていた。
「はあ・・・・」
「ああ・・・王妃・・・」
二人の精液がゆりの肌へと注がれる。
まるで交わりの月のように、男たちは興奮して何度も達していた。
やがて、ゆりが口を開いて、なぞの言葉を吐いた。
「kdjigdkgkg」
二人が何かと思って顔を近づけた。
「rerrrrrrrrrryyurrtttttbbbddfggggg」
ゆりはなぞの言葉を言い続けている。
すると、どこかからか巨大な蛇がぬっと部屋の中に入ってきて、ヴィラとジュノーは驚いた。
「蛇霊神!」
それは透けている幻の蛇だった。蛇は宙を泳ぐように飛んでいる。
ゆりは体を上げて、手を出した。蛇はゆりの体の周りを回っている。
「xddddffwsssdggpggggl」
ゆりがなにやら言うと、蛇はすっと頭からゆりのおなかの中に入って行った。
蛇はいなくなり、ゆりはそのままぱたりと倒れてしまった。
「・・・・これが儀式・・・」
ヴィラがつぶやいた。二人とも、すっかり元の姿に戻っている。
「すごかったな。交わりの月以上に興奮してしまった」
ジュノーが言う。
「ああ・・・」
「・・・ちょっとまずいんじゃないか?これは」
ジュノーはゆりの体を見下ろした。
ゆりの肌には、かなりの愛撫の跡が残っている。
「とりあえず、体洗おう。このまま王には渡せないぞ」
「そうだな」
二人はきれいにゆりの肌を洗って服を着せた。ヴィラはゆりを抱き上げて王の寝室に連れて行った。
「王、儀式終わりました」
ヴィラはゆりをベッドに下ろしながら言った。
「終わった?本当なのか?」
ラクシュミは瞬いた。
「ええ、蛇霊神が一匹きて、王妃の中に入りました。」
「お前だけでよかったのか?」
「いえ、ジュノーもきました。・・・あの、すいません。ちょっとやりすぎまして・・・王妃の肌に、ちょっと痕が・・・」
ラクシュミが見ると、ゆりの首は、かなりあざになっていた。
「そうか、まあご苦労だったな」
「では。詳しいことは明日に」
ヴィラは消えた。
・・・男10人いなくてもよかったんだな・・・
ラクシュミは、なにやら複雑な目でゆりを見ていた。
朝になり、ゆりは目覚めた。
うーん・・・なんかすごい夢みちゃったような気分
目を開けると、横にラクシュミがいて、目を開けていた。
「あれ?昨日王様の所で寝たっけ」
ゆりは何かがおかしいと思って体を起こした。
「いたたた」
髪が引っ張られてゆりは驚いた。自分の髪を見てみると、なんだかすごくのびていた。異常なほど。
「何これ、どうしたの?」
「朝方のびたぞ」
「え?どうして?」
「儀式の後遺症のようなものらしい」
「儀式?なんのこと?」
「昨日のこと覚えてないのか?」
ラクシュミが聞くと、ゆりは上を向いて、なにやら思い出した。
「・・・・」
そしてラクシュミから目をそらせた。
「なんか蛇がきた」
「それは蛇霊神というものだ。お前は無意識の内に儀式をして、蛇霊神を呼び出したようだ。」
「え?なんで?」
「あれを体に取り込むと、子供の力があがるらしい」
「そうなんだ・・・」
「大丈夫か?」
ラクシュミは不安げだった。
「・・・」
ゆりは昨日のことをかなり覚えていたが、不思議なほど嫌悪感はなかった。ただ、ラクシュミに後ろめたい気持ちはある。
自分がしたことは、いわば不倫とも言えるものだ。
「お前にそんなことさせてすまなかったな」
ラクシュミが謝るように言った。
「・・・王様私のこと嫌ってない?」
「ああ、嫌ってない」
「じゃあ抱いて」
「いいぞ」
ラクシュミはゆりを抱き寄せた。
ゆりの肌には、昨晩の愛撫の跡はすっかりなくなっていた。
肌はまるで再生されたようになめらかで、すべすべしていた。
終わったあと、ラクシュミは優しくゆりをなでていた。
「実は・・・儀式はもうひとつある」
ラクシュミがぼそっといった。
「もうひとつ?」
「ああ。いつ起こるかわからないが・・・」
「ふーん・・・」
「・・・意外と冷静だな。泣くかと思って心配してた。お前は他の男とするのいやそうだったから」
「してないよ」
「え?抱かれたんじゃないのか?」
「うん。抱かれてない」
ゆりはきっぱり言った。
「・・・」
まあいい、後でヴィラに聞こう。
その日の午前中、王の間の前にヴィラがいて、訪問者が出て行くのを待っていた。すると、ミカエルが
瞬間移動で門の外にきた。中にいたのはミカエルだというのを、ヴィラは知っていた。
ー儀式、もう終わりましたから
ヴィラが思念を送ると、ミカエルはぎょっとした顔を向けた。
「え?」
ーそれでは
ヴィラは消えて、王の間に入って行った。ミカエルは唖然としている。
「ミカエル様、どうされました?」
門の外の番兵が聞いた。
「・・・いや、なんでもない・・」
ミカエルは歩いていった。
王の間で、ラクシュミがヴィラと話をしていると、ぱっとゆりが現れた。左目は変わっていて、髪は元の長さになっている。
「髪切ったのか?」
ラクシュミが聞いた。
「うん。邪魔だからね。ねえ、王様、結界の外行きたい」
「だめだ」
即答だった。
「いやよ。行く。外出たいんだもん」
「お前の護衛が大変なんだ」
「敵いぶりだして殺せばいいじゃない」
ゆりはあっさり言っている。
「赤ちゃんにもいろんな物見せなきゃだめなの。」
「しかし・・・何かあったら取り返しがつかないんだぞ。」
「私は逃げ足速いから大丈夫だよ。そうだ、だれか将軍に付き合ってもらおう。たまにはおじ様とデートもいいなあ」
「・・・」
ラクシュミもヴィラも、あきれたような顔をしている。
「まあいいじゃない。たまには、毎日は行かないから」
「・・・しょうがないな。」
「いいんですか?王」
ヴィラが聞く。
「だめだといったら勝手に行くんだろう。お前」
「そんなことしないよ。不機嫌になるだけよ」
「・・・・」
ラクシュミの前に東の砦のロナウド将軍が現れた。
「お呼びでしょうか。王」
「ああ、すまないが、このわがまま王妃に少し付き合ってやってくれないか?」
ロナウドはゆりを見た。ゆりはにっこり微笑んだ。
やがて、ゆりはロナウドと消えた。
「・・・私も行きましょうか」
ヴィラが言う。
「ミルキダスとダノンにもいかせた。まあ、数人で見張ってれば、いざという時も対処できるだろう。」
「・・・どうもあの王妃は、まるっきり一族の女でもないようですね」
一族の女ならば、王に反抗するような言葉は使わない。
「まだよくわからん。悪い女ではないが・・ところで、お前ゆりを本当に抱いてないのか?」
「はい」
「ならなんでそんなに精力が減ってる」
「・・・」
さすがにヴィラもいいにくかった。
ゆりが目覚めた時、すでに夕方だった。
なんだか随分眠ってしまったようだ、と思いゆりは起き上がった。両方黒目のゆりである。
「んー・・・頭ぼうっとする・・・」
ゆりは頭をかきながらテーブルの上を見た。なにやらいろんな包みがおいてあった。
「これなあに?」
ゆりが部屋にいた侍女に聞いた。
「料理人からの差し入れです」
そう侍女は言った。
「へー」
ゆりは包みを開けてみた。すると、いろんなお菓子や、饅頭のようなものや、平べったいお好み焼きのようなものが出てきた。
「おいしそう」
ゆりは座ってむしゃむしゃ食べだした。
まさか自分が昼間街で買ってきたとは夢にも思わない。
「そういえば面白い夢みたなあ。湖行ったり、街にいったり、お店の中入ってご飯食べたりしたの。楽しかった」
「そうですか」
意外にも、ゆりはあちこち行きながらも危ない目にはあわずにすんだ。ずっと将軍と一緒だったせいもあるが、
雑魚の敵は周りを見張っていた戦士たちが全て片付けたからだった。
「おいしいな。これってりんご飴みたい。なんだか屋台で買ったものみたいね」
果物に飴をからめたようなおかしを、ゆりはしゃりしゃりかじっていた。
一方ミカエルは少々沈んでいた。
自分がゆりにとって、そんなに重要な男ではない、ということがショックなのだった。
しかもなにやら嫌われている。普通に気ももらってもらえないし・・・
ミカエルは一族の女性の人気も高く、プライドも高いために、一番位の高い王妃に好かれていないというのが
ショックだったのだ。
一方、フリットがいる屋敷では、フリットは母親のロアンナと一緒に夕食を食べていた。ロアンナは、何か言いたげに
フリットを時折見ている。
「なんですか?」
「・・・情けない」
ロアンナがボソッと言った。
「は?」
「お前は王妃と親しくしていると思っていたのに」
「なんですか?突然」
「蛇霊神の儀式はもう終わってしまったわよ」
「え?そうなんですか?」
フリットは驚いて聞いた。
「いつやったんです」
「昨日の夜よ。ヴィラとジュノーが相手したんですって」
「そうなんですか・・・」
ロアンナはため息をついた。
「よかったじゃないですか。儀式ができて」
フリットはあまり気に留めない様子で言った。
自分がその中に入れなかったのは少々悲しいが、儀式ができたのなら、喜ばしいことだ。
「私はてっきりあなたがそのメンバーに入るんではないかと思っていたから、ショックだわ。」
「練習のようなことはしましたよ。でも何もなかったですね。あの時は」
「あなた女の扱いがまだまだなんじゃないの?」
「え・・・」
なぜ母親にそんな指摘をされなければならないのか・・・
フリットの顔は引きつっている。
「そういう重要な儀式に参加できないと、一族の中での格がジュノーやヴィラよりも下になるわよ」
「なんでそうなるんです。大体、あの二人と儀式をしたなど、外に広まらないでしょう。まさか誰かにべらべら言ってるんじゃ
ないでしょうね」
「言うわけないでしょう。だけど、こういうことは自然と外にもれるものなのよ。耳ざといものがいるんだから。ザメハ様だって、
あの二人が相手とは意外ですなあ、とか楽しそうに言ってたし。」
「あの二人より私の方が力は上ですよ。別に周りにどう思われようがかまいはしないですよ」
「甘いわね。あなただって、あなたの父さんが儀式に参加したおかげで、周りに一目置かれてるんじゃない。こういうことは、あなた
の子供にも影響するのよ」
・・・まだ産まれてもない子供のことなんて知りませんよ・・・
フリットはため息をついてさっさと食堂を出て行った。