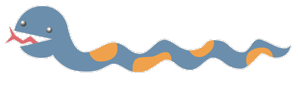
「はあ・・・はあ・・はあ・・」
ベッドの上ではゆりが苦しそうにうめいていた。
「王妃、がんばってください」
ロアンナがゆりの手を握り締めている。ベッドの周りには5人もの女たちがゆりの出産を手伝うためにいた。
横には医師のフレイもいる。
「はあ・・・はあ・・・はあ・・・」
ゆりの額には大粒の汗が浮かび、横にいた女がタオルで丁寧にふいていた。
「がんばって・・・もう少しですから・・・」
皆祈るような気持ちで、ゆりを見つめている。
王様・・・私がんばるよ・・・絶対にちゃんと産んでみせるから・・・
ゆりはラクシュミの顔を思い浮かべながら、必死にがんばっていた。
第27話
次の朝になり、ゆりはとうとう子供を産んだ。
「おぎゃあ、おぎゃあ!」
子供が産声をあげる。
「女の御子様です!」
産婆が声をあげ、4人の将軍たちとミカエルが部屋の中に入ってきた。
「王妃!気を確かに!」
ゆりは、体力も気も消耗し、息も絶え絶えだった。
「王妃!がんばってください!」
ミカエルは涙を流しながらゆりに触れて強制的に気を送り込んだ。ぎりぎりまで送ったのだが、それでもゆりの目はうつろで、
正気が戻らない。
「ゆり様!しっかり!」
ミカエルはその場にくずれて、二人目の将軍が、気を送り込んだ。
外では敵の攻撃が始まっていた。ラクシュミは王の間で、一心に念じて、一族の者たちに力を与えていた。
どうか持ちこたえてくれ・・・
力の強い5人はゆりに力を与えて戦いに参加することはできない。
王妃はがんばられたのだ・・・我々もがんばろう・・・
戦士たちは、皆同じ思いで戦っていた。
龍族の強さは龍自体が、協力な武器になるということだった。胴がずんぐりとした龍は背中に巨大な翼もあり、空を飛び、
火も吐ける。その巨大な爪で人を捕らえることも。10頭ほどの龍が敵勢と共にやってきており、龍にはそれぞれ龍族の者が乗り、
操っていた。その龍を殺すのが至難の業だった。
一方、5人がぎりぎりまで気を与えたものの、ゆりの体力は、わずかしか元に戻らない。
このままでは危ないとだれもが感じていた。
「ゆり様!しっかりして」
「ゆり様!」
「王妃!」
女たちは皆泣いている。
「おぎゃあ、おぎゃあ!」
母親の危機を感じたのか、子供は泣きじゃくっていた。
城の結界がゆがんできていた。
子供の力にひきづられている、というような感じではなかった。
ゆりの死の予感が、そうさせていたのだった。
ラクシュミとて神ではないのだ。
ラクシュミの母は、ラクシュミを産むと同時になくなった。その時結界がゆがんだのは、子供のせいではなく母の死が
原因だったのかもしれないと、初めてラクシュミは悟ったのだった。
死ぬんじゃないぞ・・・ゆり・・・
ゆりの事ばかり気にかけてはいられない。外では戦いが行われているのだから。
その時、ゆりがいる部屋にある人物が現れた。
「ラクシュミ様!?」
侍女が声をあげる。それほど、その男はラクシュミに似ていた。金色の輝く瞳、銀の髪を後ろで結び、蛇の模様のついた銀色の
上着にいつもラクシュミが着ないようなズボンをはいていた。その男はゆりに近づいて、ゆりの頭に手をあてて、ゆりに口付けた。
すると、じょじょに、ゆりの顔の色が正常に戻ってきた。
ようやく、ゆりはわずかに正気を取り戻した。
ゆりは目の前にいる男の顔を見て微笑んだ。
「王様・・・やったよ・・・・わたし・・・」
「ああ・・・よくやったな。ゆり。えらいぞ」
ラクシュミそっくりの声で、男はそういって、ゆりの頭をなでた。
「ゆっくり休め」
「ん・・・」
男は、ゆりの腕からブレスレットをとり、自分がもっていたものをはめた。
女たちはぼんやりして男を見ている。
男は倒れている将軍たちに気を与えていった。
外の戦いの場でも変化がおきていた。
宙に現れたのは、二人の黒髪の男女だった。
ラクシュミも、王の間でその存在を感じていた。
あの時に助っ人を送ると言った。それが・・・
一人は、前に来た男だった。短い黒髪、金色の瞳、上級戦士の服装をしたその男は、異常なほどの強い気をその体から放っていた。
そしてもう一人は、黒髪の女である。長い髪を上の方で結んでいた。女の方は鎧も何もつけず、普通の青いドレスを着ていた。
―戦いは僕らに任せて結界の力に集中してください。
男がラクシュミに思念を送る。
戦いの場では大きな防御の魔法が広がっていた。女が唱えているのだ。その魔法は一人一人の身にかかった。
「皆!がんばって!敵の魔法は私が食い止めるからね!」
女はにこりと微笑んで言った。瞳は金色に輝いていた。
「皆死ぬなよー!これからおもしれえ時代がくるんだからよ!いくぜ!」
男は叫び、腰の二本の剣を抜いて敵に向かっていった。
空には巨大な蛇の姿がゆらめいていた。
城にいたハザークは、窓からその蛇を見つめていた。
そしてつぶやいた。
「どうやら面白いことがおきそうだな。王よ・・・」
一族の者たちは二人の姿に勇気付けられ、ともに戦っていった。
敵がかけた魔法は、黒髪の女が相殺していく。
龍たちが黒髪の女に狙いを定めて向かっていく。戦士たちは女の前に立ちはだかり、守ろうとした。
その時、女の瞳が光り輝いた。
「デラード!」
少女の魔法は自分の周りにいる戦士たちに注がれた。
「うがー!」
魔法を注がれた戦士たちの両眼が蛇の瞳に変わる。それは、力を強化する呪文だった。力を増した戦士たちは、
先ほどの倍の速さで動き、龍を切り裂き、敵兵を葬っていく。
敵には動揺がひろがっていた。
再びこんな結末になるとは思わなかったのだろう。空を飛んでいた龍はあらかた葬られてしまった。しかも、半分以上は、一人の男
にやられている。
「ジス・ラ・ラレニペウタ!」
男が呪文を唱えた。
空をゆらめいた巨大な蛇の姿が鮮明になり、敵に向かって口を開けた。
口から放たれたのは、すさまじい吹雪のような冷気であった。
「おのれ!ひけっひけー!」
敵は次々と引き上げていく。
敵は退散していきそれに呼応するように、城の周りにいた雑魚の敵たちも、引き上げて行った。
「さすが龍殺しだな・・・お見事お見事・・」
ラクシュミによく似た男が部屋で座り込んだままつぶやいた。
やがて、黒髪の男女がその部屋に現れた。
部屋の中では女たちも、将軍たちも、ミカエルも、みんな泣いていた。
「帰るぜ」
黒髪の男はラクシュミそっくりの男の体に腕をかけて、立ち上がらせた。男は気を消失して、ぐったりしている。
「父様にあいさつしないの?」
黒髪の女が言った。
「まあいいさ。どうせそのうちに会えるしな。じゃあな、みんな」
男はちゃっと左手をあげて、消えた。女も消えてしまった。
王の間に、一族の者たちがなだれこんできた。
「姫君誕生、おめでとうございます!」
「不思議な2人組みが現れたのですが一体・・・」
「男性は前に見た男性と同じでした」
皆興奮した様子で話している。
「皆、とりあえずは、宴会の準備だ。第一子誕生を祝ってくれ」
「はい!」
ラクシュミはゆりがいる部屋に行った。侍女たちが部屋を出る。
ゆりはベッドで眠っていた。赤ん坊は別室にいる。
「よくやったな。ゆり」
ラクシュミはゆりの頬をなでた。ラクシュミはゆりのブレスレットが変わっている事に気づいた。力が満ちているのを感じる。
どうやら子供らが変えてくれたらしいとラクシュミは悟った。
その夜は、各砦や、国のあちこちにかがり火が燃やされた。戦いは無事終わり、街の人々の顔にも、笑みがあふれていた。
城の中や外、あちこちに、大きな深めの皿がおかれて酒がなみなみと注がれた。蛇たちが飲むための酒である。
この日ばかりは、あちこちで蛇も人も酔っ払っていた。
夜中、ラクシュミはハザークの塔を訪れて一緒に酒を飲んでいた。子供が生まれたお祝いだが、別段ハザークは
喜んでいる風でもなく、普通の表情をしていた。
「あの男はなかなかだな。大昔の戦いでは、あんなふうによく蛇が浮かんでいた」
ハザークが言った。
「そうだな。あの二人が使っていた魔法は、古代魔法じゃないかと思うんだが・・・」
「そうか」
どちらも相当の魔力を持っていた。王族だからなのかどうかはわからないが、力は桁外れなのを感じた。
「お前は先代の王のように王妃を我の所にこささなかったな」
ハザークがぼつりと言った。
「何だお前、ゆりを抱きたかったのか?」
ラクシュミが茶化すように聞いた。
「いいや。お前の王妃は見かけが悪いからな。あんまり抱きたくない」
「そんなに悪くないだろ。ただ人よりちょっと足が短いだけだ」
「ちょっと?」
「角も触覚もない、そんなに悪くはない」
「・・・」
二人はゆりがその場にいればむっとするような事を平気で言っていた。
「なぜこさせなかった?子供のためだろうに」
「また死んだ振りをされたら困るからだ。お前だって、本当は嫌なんじゃないのか?そういうのは」
ハザークは抱いた女にはちょっとした情を持つらしく、その時お腹にいた子供にもそれなりの愛情を
感じるらしかった。そのため、その子供の力が増すように手助けをしてきたのだ。
代々の王はそれを知っていて、自分の王妃が孕むと、ハザークの元に行かせていたのだった。
ラクシュミはそれを知っていた。ラクシュミの母親もそうしたし、ハザークがラクシュミをいろいろ
助けようとするのも、そういう心理が働いているからだ。
それもわかっているのだが、だからといってゆりに、子供のために抱かれてこい、と言えるわけもない。
「それに、お前はゆりに全く興味ないだろ」
「お前は我が愛し子だ。お前のためならそうしてもいいとは思っていた」
「別にいい。ゆりは十分よくやってくれた。」
「そうか」
ハザークはそれに関しては、もう何も言わなかった。
ゆりは3日間眠り続けて、ようやく目を覚ました。
「あ!ゆり様―!よかったー!」
側にいたミラが声をあげた。
「ん・・・と・・・」
ゆりは目をこすった。なんだか体がひどくだるい。
「ゆり様、今薬湯をお持ちしますからね」
ミラは出て行った。
「えと・・・私・・・・?」
記憶が混乱していた。一体自分は何をしていたのだろう。
赤ちゃん・・・
ゆりは自分のおなかに手をあてた。
「赤ちゃんいない・・・」
その時、部屋に年配の侍女が赤ん坊を抱いて現れた。
「あぶーあぶー」
赤ちゃんはゆりに手を伸ばす。きれいな銀色の髪、金色に輝く瞳をもっていた。
「ゆり様、抱いてあげてください。アナスターシャ様はずっとゆり様がお目覚めになるのを待っていたのですから」
ゆりは手を伸ばした。
「あぶー、あー」
赤ん坊はゆりの腕に抱き寄せられて、うれしそうに笑った。
ゆりは知らず知らずの内に涙を流してた。
「あーあー」
「かわいい。うれしいよ。アナスターシャ。やっとあえたね」
「あー・・・あー・・」
赤ん坊はゆりの頬に触れた。ゆりはその指に触れた。小さくて、かわいい手だ。
その時、ミラが戻ってきた。
「さあ、ゆり様、薬湯ですよ」
「ん・・・」
ゆりは体を起こして薬湯を飲んだ。アナスターシャはゆりのひざの上に乗り、べったりゆりにひっついている。
「私一体どのくらい眠っていたの?」
ゆりが聞いた。
「3日ですわ」
とミラ。
「そんなに?赤ちゃん産んだ時はもうだめかと思ったよ。よく生きていたなあ・・・」
「いろんな方が助けてくれましたから。」
「なんだか王様の顔見た気がするの・・・」
「ええ、ラクシュミ様がいらっしゃいましたわ」
と侍女が言った。ミラも、この侍女も、ラクシュミに似た男の姿を見ていた。将軍たちも。だれもがその男に安心感を覚えた。
だが、ゆりには王がいたということにした方がいいだろうと思ったのだ。
「やっぱり王様だったんだね」
ゆりは微笑んだ。
「王様に会いたいな・・・」
「今晩にもお会いになれますよ」
「その前にお風呂に入りたい」
「もうしばらくは、安静にしていてください。気になるのでしたら体をぬれたタオルでお拭きしましょう。それから一ヶ月は絶対
安静ですよ。庭の散歩もいけません」
「そうなの・・・・」
「はい。ゆり様は体内の力を著しく失っておりますから、急に動き回れば倒れる可能性がございます。絶対に守ってくださいね」
侍女が念を押すように言った。
「はあい。一ヶ月はおとなしくします」
「あーあー」
アナスターシャがゆりの服を引っ張った。
「そういえば、こっちの赤ちゃんって、しっかりしてるね。もう首すわってるし。むこうの赤ちゃんは、ずっと抱っこしてなきゃな
らなかったような・・・」
アナスターシャは一人でも平気で座っている。
「そうですか?これが普通ですよ。さあ、そろそろ行きましょうか。」
侍女がアナスターシャを抱き上げた。
「いっちゃうのお?」
ゆりが寂しそうに言う。
「一族の者全てがアナスターシャ様にお目どおりしなければなりませんので。」
「そうなんだ。」
「ふふふ。どんな戦士もアナスターシャ様を見ると、もうでろでろなんですよ。」
ミラがおかしそうに言った。
侍女は子供をつれていってしまった。
「そういえば、おっぱいあげないのかな・・・」
ゆりは自分の胸をなでた。
「おっぱい?ああ、この一族は母親がお乳をあげたりしないみたいですよ」
ミラが言った。
「そうなんだ。アナスターシャは一体何飲んでるの?」
「ゆり様がお飲みになってるのと同じシシーのミルクですわ」
「ええーあれでいいの?」
「はい。あれは栄養満点でございますから。」
「ふーん・・・」
「今はおとなしく寝ていてくださいね」
「うん。わかった」
ゆりはおとなしく寝ていることにした。
体はだるくて仕方なかった。
今は元気になるのが先・・・・
夕方になると医師のフレイが診察に来た。
ゆりは胃に負担をかけないものを食べて、薬湯を飲んで休んだ。
しばらく休んでいると、赤ん坊の声で目を覚ました。
「あーあーー・・・」
「起こしてしまったか?」
薄暗い部屋に、ラクシュミが赤ん坊を抱いているのが見えた。
「王様・・・」
ラクシュミの顔を見ると、ゆりは涙が出てきた。
「どうした?」
「また王様に会えてうれしい」
「そうか・・・」
ラクシュミはアナスターシャをゆりの横においた。
「あー・・あーー」
「よしよし」
ゆりがアナスターシャの頭をなでる。
「よくがんばったな。お前はたいした女だぞ、ゆり」
ラクシュミにほめられてゆりは微笑んだ。
「ゆり、しばらくおとなしく寝ておれよ?」
「はい・・・」
ラクシュミはゆりの頭をなでた。
「あんまり触らないで・・・」
ゆりがぽつりと言った。
「なんでだ」
「お風呂しばらく入ってないから」
「ばかだな・・・」
「王様、赤ちゃん産まれてうれしい?」
「ああ。うれしいぞ」
「アナスターシャ・・・」
ゆりは小さなぬくもりを抱きしめた。
アナスターシャはゆりの服を握り締めて目を閉じている。
ふいにここに来た時出会った不思議な男の言葉を思い出していた。
僕の時代の母さんは幸せだよ
男はそう言ったのだ。
「私、今幸せだな」
ゆりはラクシュミを見上げていった。
「そうか。」
ラクシュミは優しく微笑んでいる。
ゆりはその笑みを見て、安心したように眠りについた。
おしまい
最後まで読んでくださった皆様ありがとうございます。
とりあえず一部終了いたしました。
でもまだまだ話は続きますが・・・