第6話
結婚式の前夜、一族の女たちは、泣きながらラクシュミに訴えた。異界の女を王妃にする事はしょうがない。
その代わりに、女たちの誰か一人でもいいから側に召してほしいと。それは、ラクシュミの子供が産めない女たちの、
いわば意地だった。どうして自分にそれほどの力がないのかと、泣いた女たちも多い。自分達の愛しい男を、他の種族の者
に奪われる。その悲しみは、計り知れないものがあった。
「王は、我らがお嫌いなのですか?ですから、交わりの月の時にも召してくださらない。我らが力がないから、
ですからお怒りになっておられるのですか?」
「バカな事を。お前達は皆、等しくわが娘同然。嫌うはずがない。お前達を抱かないのは嫌いだからではない。
他の者と交わり、子を為してほしいからだ。」
ラクシュミは優しく言った。
「ですが・・・悔しゅうございます・・・我らの王であられるのに・・・」
女たちは皆しくしく泣いていた。ラクシュミは立ち上がり、女たちに近づいた。
「ゆりはもう、異界の女ではない。一族の気を帯びた、一族の女だ。蛇たちは認めておる。お前たちも認めるのだ。
お前たちがそっけないと、一族の男たちも気をもんでおったぞ。このままでは一族の男たちは、他の女に目が行って
しまうかもしれんぞ。それでもよいのか?」
ラクシュミは女たちの頬をなでた。
「王よ・・・」
「ああ・・・」
女の一人がラクシュミに抱きついた。ラクシュミが女の体を抱きしめた。
「ゆりが私の子供を産めば、お前達の子供と結ばれる事だってあるのだ。それが私の夢なのだ。わかるな?」
ラクシュミは、一人一人を抱きしめて、頭をなでた。
ゆりにとってはあっという間の10日だった。
一族の者の前で、ラクシュミがゆりの頭に冠をかける。それが結婚の儀式だった。そして夜、ゆりはどきどきして
ラクシュミの横に入った。
10日の間ずっと、一緒のベッドに寝ていたけれど、ラクシュミはゆりに何もしていない。ゆりがねだると、優しくキス
してくれた程度だった。しかも頬に。でも、今日は初夜である。
どうしよう。わたし、悲鳴あげないようにしなきゃ、目閉じてた方がいいかな。
なにせ最初だし、ゆりもどきどきである。
だが待っていてもラクシュミは何もする気配もなかった。
え、まさか何もないってことないよね。だって子供作らなきゃ、だし。
「ねえ、王様?」
「ん?」
「何もしないの?」
「何がしたい?」
ラクシュミに逆に聞かれてしまった。
「何って、私たち、結婚したんでしょ?こっちでは初夜とかないの?」
「初夜?」
「私を抱かないの?」
「・・・・それを待ってたのか?」
「うん・・・だって・・・私の世界ではそうだから・・・」
「そうなのか?」
「うん・・・」
「この世界では、一年に10日だけ、赤い月が出て、その時に交わって子供を作るのだ。いつもはしない」
「たった10日?そんだけ?」
「ああ。その時ばかりは発情して、皆性格が変わる。私でさえな。その上姿も変わる」
「え?」
「最初は大変だろうが、まあ暗闇ですれば大丈夫だろう」
「どう変わるの?」
そんな話は初耳だったので、ゆりは驚いた。
「さあな。言わないほうがいいだろ」
「・・・」
むちゃくちゃ気になるじゃないの・・・
「交わりの月っていつあるの?」
「6ヶ月ほど先だな」
「そうなんだあ・・・ねえ王様、その姿で私を抱いたりはできないの?」
ゆりはおずおずと聞いた。
「抱いてほしいのか?」
「え・・・だって・・だってさ」
ゆりはもじもじした。
「ただ横で寝るだけじゃ、今までと変わらないしさ」
「私は、普段はそういう気にはならないのだ。悪いな」
ラクシュミはそっけなく言った。
「そーですか・・・」
「もう寝ろ」
「はい・・・」
ゆりは拍子抜けしたような、ほっとしたような複雑な気分で眠りについた。
結婚して10日ほどたったころ、ゆりは台所を貸してもらって料理をする事にした。
今まで誰かが作ってくれていたのだが、自分でしたくてたまらなかったのだ。
「異界の料理ってどんなんでしょうね?」
ゆりの侍女たちは興味津々だった。ミラもゆりの侍女になってくれた。
「和食はさすがに無理よねー。でも醤油っぽいのみつけたから、何か煮物作れるかも。ふふ」
ゆりはミラたちと共に野菜を刻んだりしてわいわい料理を作った。
しばらくして、テーブルに一杯の食べ物が並んだ。
「わーい。できたっと。みんな食べてみましょ」
「はーい」
その時、ゆらりと、部屋に誰かが現れた。
「きゃあ!」
「だれ!?」
「王妃!」
ミカエルが現れた。ゆりはその人物をじっと見ている。
「食べ物・・・」
調理場に突然現れたその女は、テーブルの上の食べ物を見るなり、手づかみで口に運びだした。
「うう・・・おいしい・・・おいしい・・・・」
といいながら。
黒髪のおかっぱ、黒い瞳の女である。その肌の色はゆりとまったく同じ。耳もとがっていなかった。
「アヤコ様じゃないですか」
ミカエルがいった。
「アヤコ?」
「おいしい。ああおいしい!おいしい!」
アヤコといわれた女性は、すごい勢いで10人前ほどの料理をぺろりと平らげた。
他の女性達も唖然としている。
そして部屋の隅にいる蛇を見るなり
「きゃあ!蛇!」
そういって姿を消してしまった。
「なんなの?あれ」
ゆりがミカエルに聞く。
「一応、王にご報告しておきましょうかね」
そのころ王の間では、ラクシュミがうるさそうな顔で壁の鏡を見ていた。
「ラクシュミー!!アヤコが朝からいないんだよーどこにもいないんだよー!」
鏡の中では、体格のいい男がワンワン泣いている。
「人攫いだ!人攫いに決まってる!ちくしょう。さらった奴は殺してやる!殺してやるー!」
まるで吼えんばかりの勢いである。
「ガット様落ち着いて」
臣下が止めようとすると、
「うるさい!」
ガットは2人を振り切った。
「頼む、一緒に探してくれー!」
「なぜ私に言う。国の中を探せばいいだろう。一人で国を出れるわけはないのだから」
ラクシュミがあきれていった。
「だから、どこ探してもいないんだ!」
「私に言われても知るか」
ミカエルとゆりが王の間に現れたのは、まさにそんな時だった。
「ガオーガオー」
ものすごい咆哮にゆりは耳を押さえた。
「ガット、それ以上吼えると、切るぞ?」
「わかったよう。お願いだから探してくれ、な、な、な、」
「あの・・・どなたかが行方不明ですか?」
ミカエルがラクシュミに近づいた。
「ああ、アヤコがいなくなったそうだ。」
「アヤコ様なら先ほどー」
ミカエルがそういいかけた時、
「何!?貴様がさらったのか!ゆるせん!」
ガットが突然怒りだした。その瞬間、顔に虎縞が現れた。
「違います!」
「落ち着けと言っているだろう!」
ラクシュミが怒っていうと、ガットはしゅんとした。
「詳しく話てやれ」
ラクシュミは頭を抑えて言った。
「はい、実は、調理場にいきなり現れて、食べ物を食べてすぐ出て行かれました」
「どこに?」
「それがふっと消えてしまったのです」
「そんなばかな。アヤコはふっと消えることなんてできないんだ。やっぱり、魔術にかけられてるんだ。何かの罠だ」
ガットは再び泣き出した。
その時、ガットの後ろの方を、あくびをしながら歩いていく黒髪のおかっぱの女の姿が見えた。
「アヤコ様!」
と臣下の声。その声に振り向くガット。
「アヤコー!」
ガットはアヤコに抱きついた。
「何?どうしたの?」
「よかったー」
ラクシュミはあほらしくなって鏡を閉じた。
「まったく騒がしい男だ」
「本当に・・・・」
ミカエルが同調して言う。
「王様、あの女の人って・・・」
「ああ。お前と同じ異界の女だ」
ラクシュミがあっさり言った。
「そうなの?でも瞬間移動とかしてたよ?」
「同じ異界の女だとしても、ゆり様とは比べ物になりませんね。」
ミカエルが言った。
「まったく下品な・・・」
ぶつぶつ言っている。そりゃ、手づかみでご飯をかっくらう女は下品かもしれないが。
「でも10人前はあったのよ。それを全部食べるなんて、いくら大食いでも異常だよ。食べ方もおかしかったし」
ゆりが言った。
「ふうむ。多分、あの女妊娠でもしてるんだろう」
ラクシュミが言った。
「妊娠?」
「王族の子供をはらむといろいろ不思議な事がおこるからな」
「そうなんだ・・・」
ミカエルとゆりは王の間を出て行った。
初めて出会った自分と同じ世界の人間に、ゆりは興味津々だった。
「ねえ、ミカエルさん、アヤコさんとさっきのガットって人のこと、詳しく話してくれません?」
そういうと、ミカエルはいやそうな顔をした。
あれ?なんでだろ?
ゆりは不思議に思った。今までミカエルがこんな顔をしたことはない。
「ガット様は、虎族の方ですよ。国王の弟です。それであの女が妻ですね」
「はあ・・あの、ミカエルさんってアヤコさんのこと嫌いなの?」
「嫌いです」
「どうして?」
「彼女は蛇を嫌いなんですよ。だからです。蛇が嫌いな女を好きにはなれません」
「そうなの」
そういえば蛇見て悲鳴あげてたもんね。
「それよりも王妃、ミカエルと呼び捨てにしてください。遠慮しなくていいですから」
「はあ・・・・中々慣れなくて・・・せっかく料理一杯つくったのになー一口も食べられなかった。残念」
「残念でしたね。」
「今度つくったら、ミカエルも食べてみてくれる?それでおいしいっていったら、王様に食べてもらうの」
「いいですよ」
ゆりがもじもじしていうのがかわいらしくて、ミカエルは微笑んだ。
その夜、虎の国の城の一室では・・
「アヤコ、もうふっと消えたりしないでくれよ?」
ガットがベッドの上でアヤコにくっついて言った。
「うーん。全然覚えてない。それよりも、いい夢だったー。おいしいご馳走食べたの。おいしくておいしくて。あれが現実
だったらいいのになあ。あっちの料理に似てたんだよね。懐かしい味がしたの」
「アヤコ、蛇の国に行ってたっていってたよ。そこでご飯食べたんだよ」
「嘘よー。私があの国に行くわけないでしょ。あんなにょろの王国なんて死んでもいかないわよ。
第一どうやって行ったのよ」
「わからないけど、あっちではアヤコがご飯食べていなくなったって言ってたよ」
「本当に?」
アヤコは眉をひそめた。
「そうそう、蛇の国にね、アヤコと同じ異世界の女がきたんだよ。ラクシュミと結婚したんだよ」
「ええ?嘘!」
アヤコは飛び起きた。
「本当なの?それ!」
「本当だよ。」
「もしかして・・・その子が作った料理?ガットのばか!なんでその子うちに連れてこなかったのー?」
「え、俺に言われても、知らないうちにもう結婚してたし」
「きっと、あのにょろにょろの王様に騙されてるんだわ。かわいそうに。助けてあげないと。ガット、明日あの子と話さ
せて、ね」
「うん。いいよ。その代わり、もうどこにもいっちゃいやだよ?」
「わかってるわ」
次の日、鏡からまたやかましい声がして、ラクシュミは、ほっておこうかと思ったが、しょうがなく鏡をあけた。
この鏡同士にうつると話をすることができるのだ。魔法の鏡だった。
「今日はなんだ?」
「昨日はごめんな。いろいろと、あのな、アヤコがラクシュミの妻になった異界の子と話がしたいっていうんだ。
話させてやってくれないか?」
「ゆりとか?」
ラクシュミはまたうるさい事になりそうだ、と思ったが、仕方なくゆりを読んだ。
「はじめまして、私、アヤコよ」
「はじめまして、ゆりです」
2人は鏡のこちらとあちらで紹介しあった。
「ああ、うれしー。あっちの人と会えるなんて、ごめんなさいね、もっと早く知っていたら、こっちに呼んであげられたのに」
「え?」
「今からでも遅くないわ。こっちにこない?」
その時王の間には、フリットとミカエルがいて、2人は目を合わせて次にラクシュミを見た。ラクシュミは顔色一つ変えてい
い。
「毎日泣いて暮らしてるんでしょう?かわいそうに」
言いながらアヤコは涙ぐんだ。
「え?私は幸せですけど」
「脅されてるのね。本当のこと言ったら殺すとか言われて!」
「いえいえいえ」
ゆりは手を横に振った。
「勝手に勘違いしないでください。」
「でもそこには長いにょろが一杯いるのよ!」 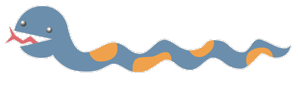
「私は蛇好きなんです!」
ゆりがそういうと、アヤコは二歩もあとづさった。
「嘘・・・」
ゆりは頭が痛くなってきた。
「アヤコさん・・・そういうことばっかり言ってるともういきますよ?」
ラクシュミはすぐ横にいるのだ。蛇の悪口は聞かせたくない。
「あ、待って!私ね、昨日夢を見たの。ハンバーグと煮物食べた夢。それって」
「私が作ったやつですよ」
「やっぱりー!?ゆりちゃんすごーい!お願い!お願い!こっちに来て作って!」
「はあ?」
「私、20年ぶりにああいうの食べたの。20年ぶりだったのよー」
「かわいそうなアヤコ・・・」
後ろでガットが泣いている。
「もっと食べたいの。お願い。一生のお願い。少しの間でいいからこっちにきて」
ゆりはラクシュミの顔を見た。すると、ラクシュミは小さく首を横に振った。
「私いけません」
ゆりは言った。
「ゆりちゃん、お願いだから」
「無理です。そうだ、作り方教えてあげますから」
「私料理作れないのよー」
「この前みたいに食べにきたらいいじゃないですか」
「どうやって行ったかわからないのよ。」
「だめですよ。妊娠してるからってあんなにどか食いしたら」
ゆりがいうと、アヤコはきょとんとした顔をした。
「妊娠?だれが?」
「え・・・?違うの?」
「妊娠?!アヤコ妊娠してるのか!?」
とガットが驚いて聞く。
「知らないわよーあ!それでずっと食欲があるのかしら」
「い、医者だ!医者呼んでこーい!」
一段と騒がしくなってきた。
「もういいだろ」
ラクシュミは鏡を閉めた。
「本当に妊娠してるの?」
「多分な。」
「全然きづいてなかったけど」
「ほっとけばいい」
その夜、ゆりはラクシュミに聞いてみた。
「ねえ王様、私、違う国に行ってみたりって、やっぱりだめかな」
「だめだな」
ラクシュミはあっさり言った。
「虎の国ってどんなところ?」
「・・・見せてやろう。目閉じろ」
ゆりが目を閉じると、ラクシュミがゆりの額に手をかざした。
「これが城だ」
それは、虎の頭のような形をした城だった。どうやら、熱い国のようだ。ジャングルもある。
「あの連中は、毎晩宴会で大騒ぎだ。騒がしいのが好きな連中なんだ」
「そうなんだ。あの男の人も騒がしかったもんね」
「あいつは騒がしすぎる」
「そうだね」
でもあの2人はどうやって出会ったんだろう。
アヤコさんと2人きりで話がしてみたいなあ。
せっかく出会えたんだもの。いろいろ情報を仕入れたい。
「ねえ、王様、2.3日でいいからあやこさんのところに行っちゃだめ?」
「だめだ」
「どうしても?虎の国は同盟国なんでしょう?ならいいじゃない。」
「だめなものはだめだ。あきらめろ」
一刀両断である。ゆりはしゅんとした。
「寝ろ」
「はい・・・」
ゆりはラクシュミに背中を向けて寝た。
夫婦、なんだよね。私たち。
でもこれで本当に、夫婦なのかな。
新婚生活は、ゆりが思い描いているものとは大分違っていた。
眠る前に少しだけ会話をして眠る生活。ラクシュミはまったくゆりにふれることはなく、2人でどこかにでかけることも
なかった。庭を散歩することさえ。そんな誘いがかかることもなかった。ゆりが夢見ていた甘い新婚生活とは程遠い。
なんだかつまらないの・・・たまにはデートとかできればいいのに。外に出れても城の周りだけで、それより外は、行かせ
てはもらえないし。
他の女の子のように町にでてショッピングを楽しむこともできない。
大体が、出会いから結婚までが早すぎた。好きかも、と思った時にはもう結婚が決まっていたのだから。もっと期間を置い
たほうがよかったのかも、とゆりは今更ながらに思ったが、遅い。
時にはラクシュミは深夜遅くに眠りにきて、ゆりと全く会話がない時さえもあった。
これで愛を育くめ、というほうが無理だろう。
それからしばらく、外は毎日雨がしとしと降り続けていた。向うでいう梅雨のようなものらしい。外を散歩する事もできず
に、ゆりは暇だった。ミラや他の侍女たちが何かと気を遣ってくれるが、ゆりは憂鬱なままだった。それはラクシュミとの
関係が元だったからかもしれない。確かに大事にはしてくれている。だけどそれ以上ではない。
ラクシュミとの仲はいつまでたっても他人同士で夫婦という感じでもなく、2人の間に愛情があるのかさえわからなかった。
ラクシュミにとっては、ゆりが子供が産める女だから結婚したに過ぎないのだから。
ゆりはミラが出してくれたお茶を一口飲んだ。少しすっぱい。最近はずっとこのお茶だ。
「ねえ、ミラ、前出してくれたお茶のほうが好きだな。次からあっちにしてくれないかな」
ゆりは思い切って言った。
「それは・・・できないんです」
ミラがすまなそうに言った。
「なんで?」
「ラクシュミ様が、これをゆり様のお茶と決められましたので、他のものはだせません」
「え?どうして?」
ゆりはあぜんとした。どうしてお茶まで決められなければならないのだろう。
「別に何飲んでもいいでしょ?」
「ラクシュミ様がお決めになったことですから、逆らえませんわ。両方飲んでいただけるのなら他のもおだしできますよ」
「いいよもう・・・」
「最近食欲がないようだな」
ラクシュミがそういったのは、それから3日ほどたってのことだった。
「食べたくないんです」
ゆりがベッドに座ったまま答えた。確かに最近あまり物を食べる気がしない。雨はまだ降り続けている。
城の中にずっといなければならないし、憂鬱なのだ。何もかもが。
「なんでもいいから食べろ。体に悪い」
「・・・」
ゆりは沈黙した。
「王様、明日、アヤコさんと話をさせてくれませんか?」
ゆりは聞いてみた。
「だめだ」
あっけなく拒否された。
「どうして?」
「今はだめだ。そのうちにな」
「じゃあ・・・明日から、寝室別にしてください」
「・・・」
「何をするわけでもないし、そのほうが王様だっていいでしょ?」
「それはだめだ」
「どうして!」
「どうしてもだ。」
「何それ・・・」
ゆりは悲しくなってきた。
愛してもくれないくせに・・・キスも、抱きしめてもくれないくせに・・・話だって、必要なことだけ。一緒にいる意味
なんてないじゃない。
「それから、あのお茶はちゃんと飲め。」
ゆりはむっとして布団をひっかぶって眠った。
朝になると、もう横にはラクシュミはいなかった。
ゆりは窓辺にむかった。すると、雨は降っていないようだった。
これで外に出られる・・・
ゆりの心は心なしか軽くなった。
ゆりは顔を洗い、服を着替えて城の外に出ようとした。
「王妃様、どちらにいかれます」
侍女に声をかけられた。
「外よ。庭に行くだけだから」
「いけません!お部屋におもどりください!」
「少しだけだから」
ゆりは走って行った。
「王妃!」
侍女が追いかけてくる。階段を下りたところで、フリットに出くわした。
「王妃、お部屋におもどりください」
フリットはゆりの腕をつかみ、いやがるゆりを強引に部屋に戻した。
「どうしてよ!なんで外に出ちゃいけないの?!」
ゆりはフリットに言った。
「今は危ないんですよ。中でおとなしくしていてください」
「いや・・・」
「王妃、もうしばらくの辛抱ですから。梅雨の時は虫が発生しやすいんです。肌を刺されたら大変です」
「わかったわよ。中にいるからもう出て行って!」
フリットは爆発したようなゆりに少し困った顔をして、部屋を出て行った。
ゆりはその日も、ほとんど食事を食べなかった。ただ、ぼんやり部屋の中にいた。思いだされるのは、
向うの世界の楽しいこと、両親、友人のことだった。
今頃ホームシックになっちゃったんだ・・・私・・・
「王妃様、果物を持ってきましたよ。少しでも食べてくださいね」
ミラが果物が一杯入ったお盆をテーブルにのせた。
「ありがと・・・」
ゆりはミラの顔を見ずにいい、ずっと、窓から外の景色を眺めていた。
このままの状態で、交わりの時とやらがくるのだろうか。
姿が変化した、ラクシュミに抱かれる。
そう思うとゆりはぞっとした。人間の男ともそんなことをしたこともないのに、大丈夫なのだろうか。大丈夫なはずはな
い。自分はどうして、簡単に結婚を決めてしまったのだろう。
昼間廊下を歩いていると、王付きの侍女たちのひそひそ声が聞こえてきた。
(王があまりにも気の毒だわね)
(子供のためとはいえ、あのようなぱっとしない人を妻にされて・・・)
(妻といっても形式上でしょう?他に恋人がいらっしゃるんだもの)
(そうよね)
(一族の集まりにも全く顔を出させないものね)
どきりとした。
恋人?それってどういうことなの?
王様に恋人がいる?
夜になり、お風呂に入った後、ゆりは部屋にいた。
「王妃様、そろそろ王の寝室にいかれませんと」
侍女が促すように言う。
「今日はいかない」
ゆりは言った。
「王妃様」
「今日はここにいるから」
ゆりはてこでも動こうとしなかった。
侍女がラクシュミに報告すると、ラクシュミは少し眉をひそめた。
ゆりがいすに座ってぼんやりしていると、部屋の中に突然ラクシュミが現れた。
「王様・・・」
「なぜこない」
ラクシュミが聞いた。
「・・・」
「私が決めたことにいちいち逆らうな」
冷たい表情で、ラクシュミは言った。
この人は私を愛してはいない・・
ゆりはうなだれた。
ラクシュミは息を吐いた。
「ゆり、一度決めたら後には引けないと、式の前にそういったはずだ。」
「わかってます。ちゃんと子供を産めば、文句はないでしょう。交わりの月の時だけ相手をすれば、それで王様は満足なは
ずでしょ?他の時はほっといてください。」
ぽろぽろと涙がこぼれてきた。
「まったくお前は難しい・・・」
ラクシュミはゆりの前のいすに座った。ゆりは涙をふいた。
2人きりの時間なんて夜寝る前のわずかな時間だけ。それでもゆりはいろいろ聞こうとするのだが、そうするとラクシュミは
うるさがり、しまいには寝ろといわれて終わるのだった。
これでは、ラクシュミのことを知ることもできない。
「たいして話をするわけでもないし、別の部屋で寝たって一緒でしょ」
「お前が私の気になじんでいたほうが、都合がいい。子供を産むためにはな」
「・・・」
つまり子供のためってこと・・・
「この道を選んだのはお前だ。今更愚だ愚だ言うな」
ゆりは唇をかみ締めた。
どうせ何を言っても無駄だ。
愛情を期待するのは愚かな行為だと、なぜあの時気づかなかったのだろう。
この人は、そういうことに興味がないのに。
自分とは、何もかもが違いすぎる。
大事にされるのは愛情があるわけではなく、子供のためなのだ。
そう思うと、ゆりは悲しくなってきた。
考えてみれば、元々自分もラクシュミを愛していたから結婚を決めたわけじゃない。
彼が言ったから・・・彼がいなければ、そんなこと考えもしなかったんだから。
「長雨で気が参っているのだろう。もうしばらく辛抱していろ。」
「わかりました」
ゆりはうつむいたまま言った。
「今日はここで寝たいなら寝ろ。だが、明日からはちゃんと来い」
そういい残して、ラクシュミは消えた。
「私ってばかだね。」
ゆりはつぶやいた。
確かに、この道は自分で選んだのだ。今更どこに逃げることもできない。
しょうがない。だって選択の余地なんてなかったんだもの。
そして、あの人にも・・・私と結婚するしか道はなかった。
好きな人くらいいて当然だよね。私は、前の王様のことなんて何一つ知らないんだから。
今だって、他の人と何をしていても、私にはさっぱりわからない・・・
恋人と過ごしているなんて思いもしなかった。
こんなの惨め過ぎる・・・
その日はまた雨が降っていた。朝食を食べた後、ゆりは部屋を抜け出した。
ゆりは一人図書室に行く事にした。城の中は安全だから最近では一人であちこちに行っているのだ。
普段はあまり人が来ない場所だった。規模はそんなに大きなものではない。
その日ゆりが図書室に行くと、ミカエルがいた。ミカエルはゆりを見ると微笑んだ。
「こんにちは・・・」
「こんにちは。王妃」
じっくり見ると素敵だな。やっぱり・・・
ミカエルは耳がとがっていなければ、十分二枚目俳優としてやっていけるほどのかっこよさだった。耳が隠れるほどの
黒髪、黒い瞳。欧米人ほど彫りは深くなく、アジア的顔立ちだ。だから安心するのかもしれない。
それに・・・にてる・・・・
ミカエルは向うの世界でゆりがあこがれていた俳優に似ていた。その男よりも、こっちの方がさらにカッコいい。
「今日はお仕事?」
ゆりは机の上の書類を見て言った。
「ええ。王妃は本を探しに?」
「簡単な本でも読んで見ようと思って」
「そうですか。王妃はこちらの文字も読めるんですか」
「簡単なのはね」
文字と言葉の理解は、こちらへ来る時のプレゼントだった。だが古い文字とかはよくわからない。
「よければ一緒にお探ししましょう」
ミカエルが言った。
「いえ、いいの。仕事してて。勝手に見てるから」
「そうですか?では、」
ミカエルは席に戻った。ゆりは自分の背よりもかなり高い本棚を見て回った。奥には、埃がかぶった分厚い本が並ん
でいる。ゆりは薄くて字が大きくて、挿絵がついている本を探した。
ゆりはちらりとミカエルのほうをみた。
ミカエルっていいよねえ・・・・
全体的に蛇族の男はみな顔立ちが整っているが、ゆりの好みとしてはミカエルがだんとつである。
お、このへんいいんじゃない?
ゆりは簡単そうな本を発見した。
字がでかい背表紙の本をとってぱらぱらめくる。
きれいな挿絵もあった。
でもどんな本かわからない。
ゆりはミカエルとは離れた机の席に座って、本を開いた。さすがに近くに座るのは気がとがめたのだ。
ミカエルのほうをちらりと見ると、ミカエルが顔を上げてこっちを見て微笑んだ。ゆりは真っ赤な顔で下を向いた。
うう・・・私って何やってるんだろ。
でも、どきどきする。
だってすごいかっこいいんだもん。
ゆりは心を落ち着かせて、本をめくった。とりあえず挿絵だけ見てみる。
すると、翼のようなものがついた女の人の絵があった。
ん?こういう人いるのかな?鳥族とか?
すると、うさぎの垂れた耳のようなものがついた男の姿もでてきた。
うーん。これは兎かな。やっぱり。
「恋の話ですね」
その時すぐ後ろで声がして、ゆりは「きゃっ」と声をあげて後ろを見た。するとミカエルが立っている。
「すいません。驚かせたようで・・・」
「いえ・・・・」
ゆりの顔は真っ赤だった。
「このお話知ってる?」
「いいえ、みたところ、翼の一族の姫君と、兎族の王子の、恋の話なのでしょうかね」
「こっちでもそういうのあるの?多種族間の、恋とか」
「ありますよ。いろいろと。まあ多種族の王族同士の恋というのはあまり聞いたことがありませんけどね」
「そうなの」
「女性は恋の話に目がないですね。どこの世界でも同じですか?」
「そうかもね」
ゆりが微笑むと、ミカエルも微笑んだ。ゆりの頬がうっすらと赤く染まった。
ほんとミカエルって素敵な人だな・・・
ゆりは本を持って部屋に戻った。
ふう・・・ああ・・・なんだか胸がときめいちゃった。
ミカエルってすごい好みなんだもん。楽しかった。あっちでデートとかしてたら、絶対女の子みんな見るだろうな。
デートしてみたいなあ。こっちの世界でもいいんだけどな・・・
夫がいる、ということはすっかり忘れている。
その夜、ゆりは夕食を久しぶりに全部食べた。機嫌がよさそうなゆりにミラはちょっとほっとしたような感じだった。
その夜、ゆりはラクシュミの寝室で寝た。ラクシュミはいなくて、ゆりは一人で布団の中に潜り、眠った。
ラクシュミは夜遅くにやってきて、ゆりの横に入った。ゆりはその気配で目を覚ましたが、知らないふりをして
目を閉じていた。
まただ・・・匂いがいつもと違う・・・
ラクシュミの匂いがいつもと違うのを感じた。数日前もそうだったような気がする。
女と、会っていたんじゃないだろうか。遅くにくるのは、他の人と過ごしていたからじゃないだろうか。
その夜、ゆりはいやな夢を見た。得体の知れない物が迫ってくるような夢だった。
朝目覚めた時には横にラクシュミがいて、ゆりはぎくりとした。
「夢見が悪いようだな」
ラクシュミが言った。
「え・・・?」
「うなされていたようだ」
「そうですか?」
ラクシュミはそれ以上聞かなかったのでゆりはほっとした。あの夢は、ラクシュミに対する恐怖が原因ではないか、
とゆりは感じたからだった。当の本人に夢の内容など言えるわけがない。
ラクシュミの手がゆりの頬に触れて、ゆりの体が一瞬びくりとなった。
「大丈夫か?」
「え?・・・はい」
久しぶりに触れられた気がした。
だけど冷たい瞳・・・
最初はもっと暖かさを感じたような気がしたのに。
どうしてこの人は、こんなさめた目で私を見るのだろう。
その日もゆりは図書室に行ってみたが、ミカエルはいなかった。今日は王妃の作法の勉強があったのだが、さぼったのだ。
残念だな・・・会いたかったのに・・・
考えてみれば私ってろくに男の子とデートもしたことなかったなあ。こんなことならしておくんだった。
ゆりはしばらくいすに座って本を読んでいた。恋の話はやはり悲恋に終わるようだった。
窓の外を見ると、激しく雨が降り続いている。
ゆりは窓に向かい、外を眺めた。遠くの方はもやがかかっていて見れない。
ゆりは近くの塔に目を留めた。城から渡り廊下のようなものがでていて、高い塔がある。塔は城の周りにいくつもあった。
「行ってみたいなあ・・・いこうかな」
「いづこへですか?」
その時後ろで声がして、ゆりはぎょっとした。
「ミカエル・・・」
いつの間にやらミカエルが立っていた。
「また驚かせてしまいましたか?」
うっすらと笑って言う。
「今日は会えないかと思った」
「私に御用でしたか?」
「ううん。ただ、あって話がしたかっただけ。」
「そうですか」
「ねえ、あそこには何かあるの?」
ゆりは左の方にある高い塔をさした。
「何もありませんよ。」
「そうなの?行ってみたいな・・・」
「あそこにですか?連れて行ってもいいですが、本当に何もないんですよ?」
「それでもいい」
「では」
ミカエルは軽くゆりの体に手を回した。ゆりはどきりとした。きづいた時には、周りの景色が変わっていた。
「わ、すごい高い!」
窓から下を覗き込むと、めまいがしそうだった。
石でできていて、少しかび臭い匂いがした。本当に何もないところだ。
だけど、周りの景色がよく見える。
遠くに見える密集している建物。湖。山。雨が降っているのでうっすらとしか見えないが。
「ねえ、瞬間移動ってだれでもできるの?」
「誰でもではないですよ。力のないものはできません。」
「そうなんだ。いいなあ。便利で。私も使えたらいいのに」
「どこか行きたいところでもあるのですか?」
「いろんな所に行ってみたいよ。私は城の中しか知らないから」
「外は危ないですからね。あなたは今では狙われていますから」
「私が逃げたら、王様どんな顔するだろ・・・」
ゆりはぼそりと言った。
「王を困らせてみたいのですか?」
「うん」
「それはまたどうして?」
「だって・・・冷たいんだもの・・・」
「冷たい?そんなことはないと思いますが」
「何か聞くと、迷惑そうだし、」
「お互いに育った場所が違うのですから、ずれがあるのは当然ですよ。価値観も、習慣さえも違うのですからね。」
「そうだけど・・・ねえ、ミカエルが私に優しいのって、やっぱり私が王妃だからだよね」
「はい?」
「ううん。いいの」
やっぱりそうだよね。別に私に好意があるわけじゃないんだ・・・
なんだかむなしいな。
「あなたはとてもかわいらしいですよ」
ミカエルが言った。
「ありがとう・・・お世辞でもうれしい」
「お世辞ではありませんよ」
「城にいる女の人って皆美人でしょう?だから、なんだか肩身が狭くて・・・」
「王様の侍女だって皆きれいだし・・・」
王の侍女と何度もすれ違ったが、向こうでいうスーパーモデルのようにスタイルはよく足も長かった。
顔もそれなりに皆きれいなのだ。ゆりの侍女は、気を遣ってくれたのか割合普通の顔をしているが。
「あなたが他の女に比べて劣っているなどと、私は思いませんよ。自分を卑下することはないですよ。あなたにはいろん
な魅力があるのですからね」
「ありがとう。少し元気でてきた」
ミカエルは微笑んだ。
「そろそろ帰りましょうか」
「うん」
ゆりは図書室に戻された。
王様も、ミカエルのように少しはお世辞のひとつでもいってくれればいいのに。
あの人にそんなこと期待するのは無理な話かもしれないけど・・・
このままじゃ、あの人との距離は全く縮まらない。
そのころ、王の間では、ラクシュミが頭を痛めていた。
虎族のガットがゆりを来させてくれと泣きついてきたのだ。自分の妻のアヤコの頼みなのだが。最近は食への欲求がすごく
て手がつけられないらしい。
「頼む、もう手がつけられないんだ。一ヶ月とは言わない。10日ほどでいいから、お願いだよ。ラクシュミー」
「・・・・わかった、考える」
長い押し問答の末、ようやくラクシュミが言った。
「本当か!?ラクシュミ、ありがとう。恩に着る!いつ来るか決まったら教えてくれな!」
考えるとしか言ってないだろ!とラクシュミは突っ込みたくなるのを我慢した。すでにガットは向うにはいない。
ラクシュミは鏡をとじた。
「ラクシュミ様・・・いくらなんでもおやめになったほうが・・・」
横にいてずっとみていたのはフリットだった。
「同族の人間に会えば、王妃の心も揺らぎましょう」
「わかっている。だが、無碍に断り続けるわけにもいかないだろう。あやつは切れると手がつけられんからな。」
ラクシュミは端正な顔をゆがめて言った。
「だが、今は時期が悪いな・・・」
ラクシュミとて、ゆりが不機嫌になっているのはわかっていた。こんな時に同族の人間にあえば、帰りたくなくなるので
はないだろうか。
「まったく異族の女は難しい・・」
ラクシュミはつい愚痴るように言った。
「王妃と何かございましたか」
「私と別の部屋で寝たいと言ってきた。」
「はあ・・・」
「何が不満なのかよくわからん」
「もっとかまってほしいのでは?お寂しいだけなのでしょう」
「できる限り相手はしている。」
「我々は、王が多忙なのも、大変さもよく存じておりますが、異界の方ですし、こちらにきてまだわずかしかたっており
ません。じょじょにいろいろとわかってくるでしょう」
「・・・この国の命運も一人の女の気分しだいとは、情けないことだな・・・」
ラクシュミは珍しく、愚痴るように言った。
フリットがゆりの部屋に来たときには、ゆりはいなかった。
「王妃はいずれにいる?」
侍女に聞く。
「多分図書室でございますわ」
「多分?王妃の侍女ならば、王妃がどこにいるかきちんと把握しておかねばならないのではないか?」
フリットが言った。
「城の中くらいは一人で行動させてほしいとおっしゃられて。どうも最近御加減が優れない様子ですので、私たちも
あまりつきまとったりしないようにしているのです」
「そうか・・・」
フリットが図書室に行った時には、ゆりはまだミカエルと話をしていた。
「王妃。王がお呼びですよ。王の間にいらしてください」
「あ・・・はい。わかりました。それじゃあ」
ゆりは図書室を出て行った。
その後、フリットは怪訝な顔でミカエルを見た。
「なんだ」
ミカエルが聞く。
「別に」
フリットはそれだけ言って消えた。
ゆりは王の間に入った。中には、ラクシュミと、黒髪の女性がいた。ドレスではなく、動きやすい格好でミニスカートと
長いブーツをはいている。
ゆりはラクシュミに近づいた。
黒髪の女性は、ゆりの方をむいてひざをついた。
「ゆり、お前一月後、虎の国に行け」
ラクシュミの声にゆりはぽかんと口を開けた。
「え?でも絶対だめだって・・・」
「どうしてもと頼み込まれたんでしょうがない。アヤコがお前が作った料理が食べたいと暴れているようだ。向うの料理人
に作り方を教えてやれ」
「はあ・・・」
「この者はジュメだ、お前と一緒に行く。向こうでは常にジュメと行動を共にしろ。わかったな」
「はい」
ゆりは素直に返事をした。
「ジュメでございます。御見知りおきを」
ジュメは、少しキツイ感じの美人だった。目鼻立ちがはっきりしている。
「詳しいことは、お部屋の方でお話いたしましょう」
「はい」
ゆりはジュメと共に王の間を出て、部屋に戻った。
何なのよ。一体。アヤコさんと話をするのもだめだって言ったくせに!他人に頼まれたらあっさりオーケーするなんて。
「ゆり様、どうなされました?」
ぶつぶつ小声で言っているゆりに、ジュメが聞いた。
「あ、いいえ。何にも。ジュメさんは、戦士なんですか?」
ゆりは聞いた。
「ジュメと呼び捨てにしてください。そうですよ。私は、国を護る仕事をしています。」
「私、蛇族の女の人と話をするの初めて・・・」
ゆりはそのことにきづいた。侍女たちは、みな蛇族の者ではない。
「私は、半分ほど、蛇族の血が混じってます。純粋な蛇族の女性は皆王妃に嫉妬しておりますからねえ。
あまり合わせたくないのでしょう」
「嫉妬?」
「ええ、いたしかたありません。あのお方の寵愛を独り占めできるのですから。」
「寵愛?嫉妬されるような事なんて、何もしてないのに」
「毎晩お側に召されておるではないですか」
「ただ寝るだけだよ。話すらたいしてしないし」
「王妃・・・」
ジュメは少しとがめるような口調で言った。
「王のことを愛されているのではないのですか?」
「・・・・」
ゆりはうなだれた。
わからない。本当にわからなくなってしまった。
愛情を感じているのかどうなのか。
「・・・?」
ジュメはゆりの様子に少し困惑した。
その時ミラがお茶をもってきた。
「虎族の国に行くって本当なんですか?」
「ガット様の奥方が妊娠で大変とか。それでよ。なんでも食べ物がまずいと暴れて部屋を2.3部屋破壊したらしいわ」
「ええ!?」
とゆり。
破壊って・・・すごい・・・
「そうなんですか。よくラクシュミ様が了承されましたねえ」
「仕方なく、よ、あなたは他の侍女たちと一緒にゆり様の荷物をまとめて頂戴。そんなにもっていけないわよ?
必要なものだけにしてね。10日ほど滞在しますからね」
「わかりました。あの、私も一緒に行かせてください」
「ええ、いいわ。3人でいきましょう」
「はい!」
ミラは部屋を出て行った。
「あの奥方は蛇が大嫌いなので、蛇は連れて行かないようにとのことです」
「やっぱり」
ゆりが自分の足元にいるルーを見ると、ルーがしょぼんとした顔をした。
「ジュメ、虎の国ってどんなところ?」
「熱い所です。我々にはあまり住みやすい所ではありません」
「そうなの。やっぱり虎が一杯いるの?」
「おりますよ。一杯」
「そうなんだ」
「王妃、あなた様はもう、蛇族の一員だということを、しっかり肝に銘じておいでくださいね。」
「はあ・・・」
今は、ここから外に出さないほうがいのでは?
ジュメはそう感じて、ラクシュミに進言した。
「やめるとまたガットがうるさいからな、無理だろう」
ラクシュミが言った。
「王よ・・・ですが・・・」
「ゆりが何か言ったのか?」
「いえ・・・」
ジュメには、ゆりが何を不満に思っているのか理解できない。一族の女たちなら、王の横で眠れるなら、
それだけで有頂天になってしまうだろう。
「まさか向こうに残るとは言わないだろう。案ずるな」
「もし、そういわれたら私は、ひきずってでも連れ帰りますが、それでよろしいのですか?」
「ああ」
ラクシュミとて、その不安がなかったわけではない。だから一月の猶予をおいたのだった。
その夜、ゆりが王の寝室に行くと、ラクシュミはすでにベッドにいた。
珍しい事だった。
「今日、王の間に来るまでどこにいたのだ?」
ラクシュミが声をかけて、ゆりは立ち止まった。
「どこって、ずっと城の中にいましたけど」
「城の中のどこだ」
「自分の部屋にいました」
ラクシュミは少し不機嫌そうに眉をひそめた。
「私に嘘はよせ」
「図書室で本を読んでました」
「一人でか?」
この人は、知っていて聞いている・・・
ゆりはそう感じた。
「今日は王妃としての作法の勉強があったのだろう。なぜさぼる」
「・・・」
「それくらいの努めは果たせ」
王妃なんて・・・名前ばっかりだよ。何一つ自由にできないなんて・・・
授業の内容だっていつも同じじゃない。
王に逆らってはいけない。
王はこの国で一番貴いもの
洗脳するように毎回同じ事を言われる。
「ゆり、誰が強制したわけでもない。お前が選んだ道なのだぞ」
「わかってます。私には、いっつも選択肢なんてない。後悔したって仕方ないってわかってる」
「後悔しているのか?」
「してるよ・・・」
「お前は一体何を期待していた」
「・・・」
「外に自由に出られないのはしょうがないことだ。お前は狙われている。結界の外では、何が起こるかわからない。
それでも、何不自由ない生活はおくれているはずだ。」
「そういうことじゃないよ。言ったって、王様にはわからないよ」
ゆりはベッドにあがり布団の中にもぐりこむように眠った。
次の日からミラは旅行の準備をしだした。
「一体どれだけ服もって行くつもり?」
ゆりがあきれたように言った。ミラは山のような服をもってきていたからだ。
「そうですわねえ。一体どれをもっていきましょう」
「一月も後のことでしょう?今から準備って早くない?」
「そうですかねえ」
「私、お城の中、散歩してくるから」
「はい、お気をつけて」
ゆりは部屋を出て、図書室に行った。そこにはだれもいなかった。
ミカエルに会いたいなあ・・・
王様も、ああいう風に優しかったら、もっと身近に感じられたのかもしれないのに・・・
ゆりはいすに座って、ぼんやりしていた。
最初はこんな素敵な人と結婚できるなんて、って思っていたけれど、今ではその喜びもしぼんでしまっていた。ラクシュミ
に他に好きな女の人がいるんじゃ、楽しいはずもない。
しかも、ラクシュミはゆりに心を見せようともせず、ゆりのことを知ろうともしない。
ただ大事に側においているだけのような気がした。
このままじゃいけない。
なんとかしないと、私もだめになる。
王様と少しでも話をしないと。
ゆりはラクシュミの休憩中を狙って休憩室に行ってみた。
すると、部屋の中には、長椅子に寝そべるラクシュミと、違う椅子に、もう一人女の人がいた。長い金髪の、
きれいな人だった。手には竪琴のような楽器をもっていた。
「はじめまして王妃様、楽師のセレーンです」
女性がほほえんで言った。
「何か用か?」
ラクシュミが聞いた。
「・・・用がないと会いにきちゃいけないの?」
ゆりはつい可愛げのない言い方をしてしまった。
「・・・まあいい、お前もセレーンの竪琴を聞いたらいい。とても素晴らしいからな」
ゆりはいすに座った。
セレーンが竪琴を奏でた。
ゆりは竪琴のことはよくわからなかったが、とてもうまいということはわかった。
ラクシュミは目を閉じてじっと聞いている。
・・・来るんじゃなかった。なんだか、すごく惨めな気分・・・
姿形も麗しく、奏でられる曲も美しい。
セレーンとラクシュミなら、並んでいてもすごく絵になるだろう。
ゆりはそっと部屋を出た。
その夜、ラクシュミはゆりの顔を見るなり言った。
「曲の途中で席を立つのは無作法だぞ」
「・・・ごめんなさい・・」
ゆりは暗い顔で謝った。
「・・・私に何か言いたいことでもあるのか?」
「・・・別にないです」
もういや。なんでこんなに惨めな思いをしなければならないのだろう。
その夜も、いやな夢を見てゆりは早くに目を覚ましてしまった。
まだあたりは真っ暗だった。横を見ると、ラクシュミはぐっすり眠っているようだった。
大人が5人は余裕で眠れるであろうベッド。
そばにいても、とてつもなく距離が遠く感じられる。
ゆりはベッドから降りようとした。
「どこにいく」
「・・・私の部屋」
「朝までここにいろ」
「・・はい・・・」
ゆりは朝までそこにいたものの、全く眠れなかった。
次の日の朝、ミラが外に出ても言いといってくれたが、ゆりは外に出ずに図書室に行き、本を何冊かもってきて部屋で
読んだ。侍女も部屋から出している。しばらくすると、部屋の扉がノックされた。ゆりがしょうがなく出ると、
ミカエルが立っていた。
「外には出ないんですか?もうすっかり安全になりましたよ?」
ミカエルはほほえんで言った。
「うん。今日はもういい」
ゆりは目をそらしていった。
「何をしていたんですか?」
「本を読んでたの。」
「そうですか・・・」
ゆりは全くミカエルと目をあわそうとしなかった。
「・・・どうしたんですか?なんだか様子が変ですよ?」
「え?」
ゆりは顔をあげた。
「そんなことないよ」
「何か悩みでもあるんじゃないですか?」
「あるよ。いっぱい」
「・・・」
ミカエルが苦笑した。
「入っても?」
「だめ。一人で本読みたいから」
「そうですか・・・」
ミカエルはあきらめて行った。
・・・もし・・・もう一度あの扉を選んだ空間からやり直せるのなら・・・
今なら絶対蛇は選ばない。
犬がいいな。犬の国。なんか可愛い犬がいっぱいいそうだし・・・
私子供のころ犬飼ってたのよね・・・
ああ・・・違う所に行きたいな・・・
違う所で違う生活がしたい。
虎の国にいったら、それが可能なのだろうか。
ー僕を産んでくれないと、僕は過去のあなたを助けられない。
あの男の言葉が心をよぎった。
過去の自分を助けるためには、王様の子供を産まなければならない。
そのことが、ゆりの心に重くのしかかっていた。
進む