第7話
次の日の午後、ゆりは本を持ち出して、城の外にある東屋でお茶を飲んでいた。足元ではルーがとぐろを巻いている。
「私ここで本を読んでいるから、ミラはもういいよ?」
ゆりがミラに言った。
「そうですか?ですが・・・」
「しばらくいるから」
「では、後で様子を見に参りますわね」
「うん・・・」
ミラは去っていった。ゆりはしばらくぼんやり景色を眺めていた。
庭はきれいに手入れされている。あちこちに蛇の姿が見えた。
庭をすぎれば王の結界がある。それを超えてはいけない。何度も何度も言われたことだった。結界の外を過ぎれば、すぐにでも殺さ
れてしまうだろうと。
まあいい。どうせなら虎の国に行ってから逃げるほうがいいに決まってる。
アヤコさんに泣きつけばきっと、なんとかしてくれる。
しばらくすると、東屋に近づく姿があった。
二人の美しい女だった。
「これは・・・・王妃様」
二人は軽く頭を下げた。一人は長い黒髪、一人は水色の髪の女性だった。どちらも、美しく見事な身体つきをしていた。
「あ・・・どうぞ。私もう行きますから」
ゆりは本を持って立ち上がった。
「そうですか?」
「どうもすいません」
心なしか敵意のようなものを感じて、ゆりは東屋を去った。
「まだ子供なのね・・・それに美しくもないわ・・・」
「おやめなさいよ。聞こえるわ」
そんな声が聞こえてきた。
美しくない・・・か。そんなこと言われなくてもわかってる。
あの人たちが一族の女の人なのかもしれない。
男も美しければ、女も美女ぞろいか・・・
なんだかむなしい・・・
あれでは王様が私に興味がないのも無理はないかもしれない。
ボリュームのある胸の膨らみ、くびれた腰、長いすらりとした足、あんなスーパーモデル並みの女たちとどうやって張り合えという
のだろう。
その夜、ゆりは思い切ってラクシュミに言ってみた。
「ねえ、王様、街に行ってみたい」
「だめだ」
即答だった。
「誰か守ってくれればいいじゃない」
「何が起こるかわからない。ほしいものがあるならいえばよかろう。」
「・・・」
それじゃ意味がない。いろんな品物を眺めたり、いろんな人を見たりしたいのに・・・
つまんないの。
「せっかくだからアヤコさんに何かお土産持って行きたいの。この国では何が珍しいの?」
「侍女にでも相談しろ。私はもう眠い」
ラクシュミは、相手をするのも面倒だ、とばかりにゆりに背中をむけた。
「・・・・」
王様って、つまんない人だね。
ゆりはそういいたいのを我慢した。
結婚するまでのほうがやさしかった気がする。
結婚してしまったら、私のことなんてどうでもいいみたい。
いや、子供さえ産まれれば、どうでもいいのだろう。
そうこうしているうちに、虎の国に行く日が近づいてきた。ラクシュミとの関係は、相変わらず平行線をたどっていた。
ゆりももうあえて何も言わなかった。今は早く違う国に行ってしまいたかったのだ。
旅行の前日、ラクシュミは珍しく早めに寝室にきた。
「ゆり、お前は、この国の人間だ。もうそれはわかっているな?」
確認するように聞いた。
「はい」
「なるべくジュメと一緒にいるようにしろ。いいな?」
「はい・・・」
もしかしたら、これが最後の会話になるかもしれない。そうゆりは思った。
「王様も、元気でね」
「ああ・・・」
私がいなくなったら、この人は、どう思うだろう。きっとすごく怒るだろう。
・・・まあいいや。
もう私には関係ない。
大体自業自得ってもんだし・・・過去の自分のことは、とりあえず考えたくない。
それにしてもどうやって違う国に行くのだろう。そう思っていると、朝、城の中の一室に通された。
部屋の中には魔法陣のような大きな模様が床に描かれていた。
「これで移動するのですよ」
ジュメが言う。
「へえ、便利なんだね」
とゆり、3人がその円の真ん中に立ち、ラクシュミが傍らで何か呪文のようなものを唱えた。
ゆりは最後にラクシュミの顔を見た。ラクシュミも、ゆりを見ていた。
さよなら・・・王様・・・・
次の瞬間、風景が変わっていた。
「おーきたきた!ようこそ虎の国へ!」
体格のいい男がゆりに近づき、ゆりの腕をとり、ブンブン振るった。
鏡でアヤコの後ろにいた男だ、とゆりは気づいた。
まるでプロレスラーのように体格は良く、筋肉がついている。金色の短髪、精悍な顔立ちをしていた。
「早速で悪いんだが、おいしい料理を作ってくれるかい?アヤコ今寝てるんだ寝言でおいしい物が食べたいといってるんだ」
ガットは目に涙を浮かべて言った。
「待ってください。少し休ませていただかないと」
ジュメが抗議する。
「私大丈夫だから、調理場に案内してください」
「おお!ありがとう!」
ガットがゆりをぎゅっと抱きしめた。
「ガット様!」
「おお、悪い悪い!」
がははと笑ってゆりを離す。
「案内するよ」
台所に行くと、机の上には様々な食材が並べられていた。得たいの知れない肉なんかがおいてある。
「適当に用意しておいたから、よろしくな。ゆりちゃん」
「はあ・・・」
なんか頭痛くなってきた。一体何人分の料理をつくればいいのやら。
「とにかく、あっちで使ってた食材以外はよくわからないからなあ、他のどけてくれる?ミラ」
「はあい」
ゆりはゴムで髪をしばった。
調味料の棚を見てみると、そこにもなんだか得体の知れないものがおいてあった。
「もってきてよかった」
ゆりは荷物の袋から調味料セットを出した。
「まずはパンの生地をこねて、と」
ゆりはテーブルの場所を確保して、料理に取り掛かった。
「かわい・・」
「かわいいなあ・・・」
「わっ!」
見ると、扉の所に一杯男がいて、こっちを見ている。
「のぞかないでください!」
ジュメが怒って言った。
「ひゅう、あんたもかわいい」
「あのね!」
料理が次々とでき始めることろ、或部屋では、アヤコががばっとおきた所だった。
「おお、アヤコおきたかい?ご飯だよ。おいしいご飯が食べられるよ」
「ご飯?」
「ゆりちゃんが来てくれたんだよ」
「本当!?」
アヤコは急いで台所に言った。
「ゆりちゃん!」
「あ、アヤコさん、こんにちは!」
ゆりがアヤコに言う。
アヤコはテーブルの上に食べ物を見て、涙を流した。
「ありがとう。ありがとう」
「アヤコさん・・・」
「食べてもいい?」
「うん。いいよ。はい」
ゆりはアヤコにスプーンを渡した。
アヤコは肉の煮込みのようなのを食べた。そしてはっと目を見開いた。
「これ・・・カレー?カレーの味がする」
「カレーもどきかな。」
アヤコは次々と口に運んだ。
「おいしい。おいしいよう・・・」
涙が流れている。
次ににコロッケのようなものを食べて、パンを食べた。
「おいしい、うう、ありがとう・・・ゆりちゃんって料理の天才ね!」
「アヤコさん・・」
泣きながら食べてくれるなんて、作ったかいがあったわ。
「アヤコ、よかったな・・」
後ろではガットが涙を流していた。そして扉の方では、毛深い男達がみんな泣いていて、ゆりはぎょっとした。
ここの男達って、何か変・・・・
その夜、ガットはゆりのために宴会を開いてくれた。お城の外で、いわばキャンプファイヤーのような感じだ。
真ん中で火をたいて、その周りにみんな座り、踊ったりお酒を飲んだり。外は蒸し暑い。常夏の国って感じだ。
「ねえ、ジュメ、ここの男の人って、みんな体格いいんだね」
ゆりは横にいるジュメにこっそり耳打ちした。まるでプロレスラー軍団が回りにいるみたいだ。そして、当然虎がのしのし歩いてい
て、ゆりは身をすくませた。
「そうですね。虎族は、この世界で一番体格がいいかもしれませんね。」
「そうなんだ、あれ?アヤコさんは?」
「眠ってしまったんだよ。最近良く眠るんだ。妊娠のせいだと思うけど」
ガットがゆりの横に腰を下ろした。
「そうなんですか。」
「ガット様、ゆり様に触らないでくださいね」
ジュメがクギをさした。
「わかってるって、おれが親友の妻に手を出すような男に見えるか?」
「親友?」
「ラクシュミのことさ。俺たちは昔っから仲がいいんだ。」
王様は反論しそうだけど・・ゆりはそう思ったが黙っていた。火の回りでは、女性陣があられもない格好で踊っている。こっちは
結構開放的なんだろうか。
それにしても・・・・和むなあ・・・
ゆりは女の人の顔を眺めた。美人もいるけれど、普通の顔の人が結構多い。蛇の一族の女性のように美形ぞろいという事はない。
それに、女の人の体型は、アジア的だった。
つまり、そんなに足が長くない。胸は皆でかいが。体格がよすぎる女性もいるが皆そうではなく、細身で普通の女性達もいた。
頭の上に猫の耳がついた女性達もいる。彼女らは猫の一族なのだろう。皆楽しそうに笑っている。
なんだかアットホームな雰囲気なんだな。虎の一族って。
ことあるごとにこうやって皆で集まり、踊ったりして楽しんでいるのだろう。
蛇の一族にはこういう雰囲気はないのでゆりはうらやましく思った。
「ゆりちゃんも踊らないか?」
ガットが聞いた。
「え・・・」
「あの、今日は疲れているのでこれで休ませていだだきます」
ジュメが言った。
「そういわずにさ、な」
ガットが親しみやすい笑みを浮かべてきた。
「じゃあ、少しだけ」
「ゆり様」
「踊ってくる」
「そうこなくちゃ。俺が教えてあげっからね」
ガットはゆりと手をつないで輪の中に入っていった。
軽快な音楽にあわせてからだを動かす。
「うまいうまい」
ゆりは微笑んだ。
「ガット様、おれと変わってくださいよ!」
虎族の男が近づいてきた。
「おれも、おれも、一緒に踊りたい!」
「うるせー、」
「アヤコ様にいいつけますよー」
「ぐっ、ごめんな。ゆりちゃん、このがさつな野郎達と踊ってやってくれるかい?君のようなかわいい子に皆目がないんだ」
「え・・・」
「最初は俺、俺、シトラスです。よろしく〜」
「よろしく」
「きゃわゆい・・・このまま連れ帰りテー」
シトラスがゆりの手を握って言う。
ぼこっと音がした。ガットのけりがシトラスのおしりに入ったのだ。
「てめえら、変なことすんじゃねーぞ」
ガットが回りの男たちに言った。
「わかってますよ」
シトラスは、うれしそうな顔でゆりと一緒に踊った。
なんか変なの。でも、楽しい。こんなのしばらくぶり。
ゆりは久しぶりに笑ったような気がした。
「王妃・・・」
傍らで見ていたミラが複雑な顔をしてつぶやいた。
しばらく踊り、部屋に行くと、ベッドが3つ並んでいた。
「申し訳ありませんが、同じ部屋で休ませていただきます。何かあったときに対処ができませんので」
「私はいいよ。久しぶりに疲れたー、お風呂はいってくるね。」
「あ、はい。準備します」
その夜、ゆりは久しぶりにぐっすり眠った。
朝、ガオーガオーーと何か獣が吼える声でゆりは目を覚ました。
「何あれ」
「城の外に虎が一杯いますわ。食事の時間みたいですわ」
窓から外をのぞいていたミラが言った。ミラもジュメもすっかり着替えている。
「朝食でございます」
声がして、部屋にメイドたちがワゴンで食べ物を運んできた。
ゆりはそれを見るなり絶句した。そして、メイドが去った後2人を見た。
「何これ」
ワゴンの上にあったのは、鶏の丸焼きだった。3個置かれている。そういえば、昨日の歓迎会のときも、これが一杯おかれていたような気がする。
「こちらの朝食なのでしょうね」
「朝からこれはないでしょう」
とゆり。
「しかも10人前はあるよ。これ」
「虎族は大食漢ですから」
ミラが言った。
「なるほど・・・ここの料理人に料理教えるの、大丈夫かなあ」
ゆりはちょっと心配してしまった。
ゆりは、3人の料理人に料理を教えることになったのだ。話を聞くと、たいていの味付けは塩と胡椒くらいで、いろいろ手の込んだ料
理は、虎族の者は好まないのだという。性格的に大雑把なせいもあるかもしれないが。
それで大好物が肉の焼いたもの。だからたいてい肉を焼いただけの料理になるようだ。
ゆりは一日がかりで、アヤコが好むような料理の作り方を教えた。料理人たちは、熱心にメモを取りながら聞いていた。料理がいろ
いろできるころには、アヤコがやってきて、片っ端から食べて行った。
「ゆりちゃん、昨日はごめんなさいね。今日はいろいろお話しましょう。」
「ええ」
「そうだ、今日は一緒の部屋に寝ましょうよ。そのほうがいろいろ眠るまで話せるし」
アヤコが手をたたいていう。
「俺も一緒だよね。アヤコ」
とガット。
「そんなわけないでしょ。あんたは違う部屋で寝てよ」
アヤコが言うと、ガットがえーと抗議の声をあげた。
「寂しいじゃないかー」
「一日くらいいいでしょ」
「うう。うん」
ガットはしょんぼりした顔で言った。
なんか・・・すごい。この2人の関係。
完全に尻にひかれている。
その夜は、ゆりはアヤコのベッドに一緒に眠ることにした。ベッドはかなりでかい。二人は余裕だ。
「ガットさん本当にアヤコさんのことが好きなのね」
はたから見ていてそれが良く分かる。心底愛しているという感じだ。
「そうね。子供ができたから、喜びもひとしおみたい。ねえ、ゆりちゃん、蛇の国で辛いことない?本当に大丈夫なの?」
「・・・・実は・・・・もう、帰りたくないの・・・」
ゆりは瞳を曇らせて言った。
しばらく王様には会いたくない。
「やっぱり・・・あの、長いのがいやなんでしょ?わかるわー一匹見ただけでぞっとする。」
アヤコはベッドの上で身体をぶるっと奮わせた。
「いや、そうじゃなくて・・・王様との関係が・・・」
「ゆりちゃんは何で結婚したの?」
「・・・成り行きかも」
「成り行き?愛してるーとか言われて?」
「ううん。ただ、子供を産んでほしいって言われて、うんって言ったの」
「なんで?ゆりちゃんはあの人のこと好きだったの?」
「結婚したら好きになれるって思ってたんだけど、自信なくなっちゃった。王様は、私に全然興味ないんだもの」
「そうなんだ・・・こんな世界に突然きて、心細かったんじゃないのかな。今は結婚した事後悔してるの?」
「うん・・」
「・・・大丈夫だよ。ゆりちゃん。私が助けてあげる。戻るのがいやなら戻らなきゃいいよ。ずっとこの国にいればいい」
アヤコはゆりを元気づけるように手を握り締めた。
「アヤコさん・・・」
「一筋縄じゃいかないだろうけど、何か方法考えましょ。ね。」
「ありがとう」
帰らなくていい。そう考えるとほっとした。
「虎族の男はいいわよ。みんな人情に厚くてやさしいし、それにすごい甘えんぼなの。私たちのこの黒い髪と黒い瞳、虎族の男には
結構ツボみたいでね、ゆりちゃん、この国ではもてもてよ」
「そ、そうかな・・・」
「そうそう」
帰らなくていい・・・帰らなくてもいいんだ・・・
ゆりは、他の二人にはばれないように、そ知らぬ顔で、料理をこちらの料理人に教えていた。だが、どこか楽しそうなゆりの様子に
ミラも、ジュメも、不安になっていく。
そして、その不安も現実になった。帰る日の朝、ゆりは、二人の元に戻ってこなかった。
ジュメが迎えにいこうとすると、ガットがやってきた。
「ガット様、ゆり様はどこです?」
ジュメは目を吊り上げて聞いた。
「う・・・ん。それがさ、帰りたくねえってさ」
ガットが頭をかきながら言う。
「は?何をおっしゃられているんです」
ジュメが唖然として言う。
「どうも、彼女ラクシュミとうまくいってないみたいじゃないか。それで帰りたくないっていうんだ」
「帰りたくない、ではすみません。ゆり様が帰らないと困るんです。それはガット様もよくご存知のはずでしょう」
「わかってるさ。俺だってラクシュミともめたくない。だけどなあ・・・アヤコも聞かないし、」
「ゆり様に合わせてください。このまま二人だけで帰るなんてできないんです」
「参ったなあ」
ガットが頭をかく。
その時だった、
「どうかしたのか?ジュメ」
声をかけられてジュメは後ろを向いた。
「ミカエル様!」
廊下を歩いてくるのはミカエルだった。
「王妃に何かあったのか?」
ジュメは仕方なく話をした。
「そうか。私がゆり様と話をしてみよう。話せばきっとわかってくださるよ」
「参ったな・・・お見通しだったわけか」
ガットはまた頭をかいた。
ゆりはガットと一緒に部屋に入ってきた人物を見てぎょっとした。
「ミカエル・・・」
「ゆり様・・・」
「ガット、どうして連れてきたの!」
アヤコが怒って言う。
「このまま何も話をしないわけにはいかないだろう。ゆりちゃんは、無理やり王妃にされたわけじゃないんだから」
「ゆり様、話をしましょう」
「・・・わかったわ・・・」
「心配なら俺もいるよ?」
ガットが言う。
「ありがとう。大丈夫です」
ゆりはガットに言った。二人は、客間で話をすることにした。
ミカエルは穏やかな表情でゆりを見ていた。
「王様は、予想してたんだ。こうなること」
ゆりがうなだれたまま切り出した。
「・・・ゆり様、あなたは王と結婚する事で、一族の一員になったのですよ。一族にとっては、裏切りはもっとも重い罰なのです。
しかも、あなたは一族の将来のために必要な方だ」
ミカエルは優しく言った。
「そのうち帰る。もう少しだけここにいたいの」
「わがまま言わないでください」
「いいじゃない。少しくらい。交わりの月までに向こうに帰れば」
「だめです。そんなことはできません」
ミカエルは真剣な表情で言った。
「いやになったからと逃げ出す事はできないのですよ。あなたは、ラクシュミ様の妻になる道を選んだのだから。他の道を選ぶこ
とはできません。帰りましょうゆり様。夫婦の関係は、時と共に育まれていくものでしょう。何年かすれば、王ともうちとける事が
できるようになりますよ」
「・・・・」
「帰りましょうね。ゆり様」
ミカエルは優しく言った。
「あの人と仲良くなれるとは思えない」
ゆりは小さな声でぼそぼそと言ったのでミカエルには良く聞こえなかった。
「王妃?」
「・・・せめて・・・もう少しここにいたい・・必ず帰るから・・・」
「いけません。遅れれば、王の心証が悪くなります。あなたのためにもならない」
「・・・私・・・この国の人好きだな。ここにいるとほっとする。」
ゆりは横を向いて言った。その瞳には、涙がにじんでいた。
ゆりは、アヤコに帰ることを告げた。アヤコはとても心配していたが、大丈夫だからと言い張った。
ジュメとミラの元にいくと、二人ともとても不安げな顔をしていた。
「二人ともごめんね」
ゆりは二人に謝った。
自分が悪いんだ・・・
深く考えずに結婚してしまった自分が。
魔法陣を抜けて、ゆりはとうとう元の国に戻ってきてしまった。
ミカエルに促されて、王の間に入る。ゆりはラクシュミの顔を見ることができなかった。
「疲れただろう。部屋でゆっくり休め」
優しげな声が聞こえてきた。
「はい」
ゆりはそう返事をして、王の間を出た。
部屋に戻ると、蛇のルーが飛びついてきた。
「ルー、元気だった?」
ゆりはルーを抱きしめるようにした。
「あの、ゆり様、紅茶でもお持ちしましょうか」
ミラが言った。
「うん。ありがとう」
ミラは部屋を出た。複雑な表情をしていた。
その夜、ゆりはバルコニーにいた。ラクシュミからは寝室に来いとも何も言われなかったため、自分の部屋にいた。
虎の国は、とても暑くて、夜は風が気持ちよかったけれど、今は少し肌寒いくらいだ。
もう二度と、他の国に行くなんてできないだろう。
それよりも・・・私は逃げようとした。
それを、あの人はどう思うだろうか。
・・・でも、それもどうでもいい。いまさらどう思われたって、かまいはしない。
「こんなところにいたのか?風邪を引くぞ」
声が聞こえてきて、ゆりは顔を向けた。ラクシュミが窓のところに立っていた。
「王様・・・」
ラクシュミは怒っている様子もない。普通の表情をしていた。
「怒らないの?聞いたんでしょう?」
「怒られたいのか?」
「・・・」
「予想はしていた。だが、帰ってきたのだからもうよい」
「そう・・・」
「お前に一つ頼みがある」
「頼み?」
「お茶のことだ。あのお茶は、朝と晩、必ず飲んでくれ」
「ちゃんと飲んでます」
「嘘をつくな。侍女の目を盗んで捨てているだろう」
ゆりの頬がぴくりとひきつった。
「お前の部屋の窓から湯が落ちてきたといったものがいる」
「・・・」
ゆりは開き直った顔をしていた。
「私はお前を疎ましく思いたくはない。だが、逆らってばかりだとそうなるぞ?」
「興味がないのも疎ましいのも一緒じゃないの?」
「私がいつお前に興味がないといった?」
「言わなくたってわかるよ。王様は一度だって私と世間話だってしたことないじゃない。こんなので、交わりの月なんて、
いやよ。私」
「・・今年はもう、お前とはすごさない」
「そう、よかった」
「そういう言い方はやめろ。お前は私を何だと思っている!」
ラクシュミが冷たく言い放ち、ゆりはぎくりとした。
その時ゆりは初めて、ラクシュミが恐ろしいと感じた。
「・・・とにかく、お茶の事は、言うことを聞け。それだけだ」
ラクシュミは、そう言うと姿を消した。
ゆりは大きく息を吐いた。
とても怖かったのだ。
今年はもう、お前とは過ごさない・・・か。
これでとりあえずは、夢でうなされる事もなさそう。
交わりの月ラクシュミが一体誰と過ごすのか、ゆりにはもうどうでもよかった。
どうせ恋人とやらと過ごすのだろう。
自分とは比べ物にならないくらい美しい恋人と。
好きにすればいい。どうせ、私達は名目上の夫婦なのだから。
「寝よう」
ゆりは布団に入った。
それからしばらく、ゆりは自分の部屋で寝た。ラクシュミがたずねてくる事も、何か苦情を言われることもなかった。
ただ、仕方なくお茶だけは飲んでいた。ミラにまで泣きつかれたからだ。
だが、数日すると気分が悪くなってしまい、ゆりは寝込んでしまった。
「精神的に、疲れられているようですな。最近は食事もあまりとられていないようですし」
医者に言われた。
「ねえ、あのお茶は、一体なんなの?何故飲まなきゃいけないの?」
「王妃様がこの世界になじむためのものです。ですから、飲んでいただいているのですよ」
「今更・・・おかしいよ・・・」
「もう少しの辛抱ですから」
「・・・」
まさか毒ではないだろうけど・・・
寝込んでいても、ラクシュミは見舞いにくることもなかった。医者から報告は受けているだろうけど。
なんだかむなしい・・・・顔を見たいわけではないけれど・・・
これで夫婦なんていえるの?
身体は元に戻ったものの、心はいつまでも晴れなかった。
結局、虎の国に行く前と、対して関係は変わらない。
その夜、夢を見た。
夢の中のラクシュミは優しくゆりに微笑んで、抱きしめて口付けた。
「愛してる、ゆり・・・」
優しい愛の言葉も、愛の抱擁も、現実では望むことはできない。
そう思うと、夢から覚めたゆりは涙を流したのだった。
数日後赤い月が出た。交わりの月が始まったのだ。
「真っ赤だ・・・なんか気持ち悪いなあ」
今夜はあちこちで、愛の契りがかわされているのだろう。
王様も、誰かを愛してるんだろうなあ・・・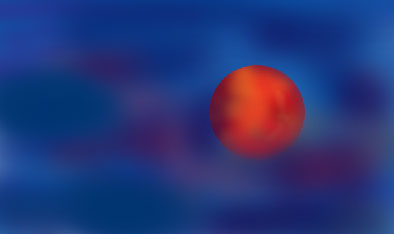
あの人も、愛する人には優しく微笑むのだろうか。
そりゃそうよね。
その期間は、城の中も、異様な雰囲気に包まれていた。
ゆりは思い切って、高い塔に一人で登ってみた。いざ階段を昇るとすごくきつい。途中でやめようかとも思ったが、
がんばって上まで上りきった。
「ぜいぜい・・・」
肩で息をしながら、窓辺にもたれた。
「あー疲れた。水もってくればよかった」
ゆりはしばらく景色を眺めていた。
でもすがすがしい気分だ。
「あーあ。白馬に乗った王子様が助けにきてくれないかな・・・」
ゆりは一人でぶつぶつつぶやいた。おとぎ話ならば、誰かが連れ出してくれる設定なのだが。現実はそうはならない。
「誰かさらってくれないかなあ・・・・」
翼があれば・・・飛んでいけるのに・・・
(逃がしてあげるよ・・・)
その時、頭の中に声が聞こえて、ゆりはぎょっとした。
(そこから逃げたいのだろう?)
「だれ?」
ゆりはあたりをきょろきょろ見た。
だけどだれもいない。
(私はそこにはいけない。王の結界には入れない。あなたが、ほんの少しでいい、王の結界を出てくれたら、そうしたら、
逃がしてあげる)
声は男の声だった。
「あなたは、だれ?」
(そこでの生活はつらいだろう?あの冷たい王の、子供を産むだけのために、閉じ込められて・・・・その証拠に、交わり
の月だというのに、あなたは一人こんなところで寂しくいる。あなたはそれでいいの?蛇の一族がどうなろうと、あなたに
関係はないだろうに・・・)
「・・・・あなた・・・敵なの?」
(あなたにとっては敵ではないだろう。自由になりたくはないのかね?今この時期しか機会はない。もし逃げたいのなら、
結界を越えるのだ)
結界を・・・越える
超えれば、自由になれる?
(なれるとも・・・)
自由・・・
「何をしている?」
声がして、ゆりはぎょっと振り向いた。後ろにラクシュミが立っていた。
「いつからいたの?」
ゆりの顔はこわばっている。
「今さっきだ。お前の姿が見えた」
「・・・」
ゆりは目をそらした。
「誰と話していた?」
ゆりの心臓の音が跳ね上がった。
「誰とも。ただ、独り言言ってただけです」
「お前は嘘が下手だな」
「・・・・」
「私は、お前の裏切りを一度は見逃した。二度目はないぞ」
ラクシュミは落ち着いた口調で言った。
「裏切ってないわ。未遂だもの」
「私にすれば同じだ」
「なぜ逃げたくなったか、考えようとはしないの?」
「私はお前に嫌われるような事を、した覚えはないのだがな・・・」
ラクシュミがぽつりといった。
よく言うよ・・・好かれるような事も、したことないくせに。
「お前は望んで私の妻になったはずだが?」
「あの時は、私は何も分かってなかった。あなたと愛し合えるって信じていたから」
「・・・」
「ばかげてる。あなたは子供を産んでほしいとしかいってない。あの言葉以上の感情なんて、今でももってないのに」
「お前も私の子供をほしがっていたではないか」
「・・・・」
ゆりはため息をついた。
子供子供・・・この人と私のつながりは、それしかない。
「私とお前では住んでいた世界すら違っていたのだ。考え方も違う。お前が思うとおりにはいかん」
そうじゃない。
アヤコさんとガットさんはちゃんと夫婦だったもの。愛し合っていた。
言ったって、どうせ無駄だろう。
話し合う機会さえ、この人は与えてくれなかった。
「さっきの話だがな、誰と何を話していた?」
ラクシュミは前に進み、ゆりのすぐ前まで来た。
「何のことかわからない」
ラクシュミは手を出して、ゆりの頭をなでた。ゆりの身体がひどくこわばった。
「私はお前をひどい目にあわせたくはない。だが、お前が何かすれば、制裁を加えねばならなくなる。それをよく考えることだ」
「・・・私を殺すなんて、できないくせに」
「殺さずとも、方法はいくらでもある。たとえば、お前の足を動けなくする事も簡単にできる。一生ベッドの上で過ごすのはいや
であろう?」
「・・・・そうやって、一生脅すつもり?」
「そうしたくはない」
「・・・・」
ゆりは横をむいた。
つくづく、簡単に結婚してしまった自分が悔やまれる。
「お前がどれほど嫌がろうと、もう逃げ出す事はできないのだ。私が王の座を降りる事が出来ないのと同じようにな」
「・・・」
これが、夫婦の会話だなんて・・・
「もう・・・行ってください。私は一人になりたい」
「お前ももう戻れ」
「城の中くらい自由にさせて」
ラクシュミはゆりの腕を引いた。
「!」
一瞬で、ゆりは自分の部屋に戻されてしまった。
ゆりは腕を引いて体を離した。非難に満ちた瞳で。
「お前はまだ病み上がりだろう。」
ゆりは顔を横に向けた。知らず知らずのうちに、涙が流れていた。
「・・お前はまったく難しい女だ。どうすればお前の気が晴れるのか、教えてほしいくらいだ」
「自由になりたい」
「ここでの生活がそんなに苦痛か?今日の糧に困っている者とて、この世界には、ごまんといるのだぞ?お前がどれほど恵まれ
ているか、」
「私はただ・・・」
ゆりのひざががくんと折れ、ラクシュミが、ゆりの体を抱きとめた。
ゆりはぽろぽろと涙を流している。
私はただ・・・・愛されたいだけなのに・・・
どうして私を見てくれないの?
どうして何もしてくれないの?
私がきれいじゃないから?
私は子供を産む道具じゃない。
どうして、こんな惨めな思いをしなきゃならないの・・・
「・・・」
ラクシュミは、ゆりの心を読んでいた。
「はなして・・・」
ゆりが泣きながら言う。
「・・お前、ずいぶんやせたな。やせすぎた女など、見られたものではないぞ」
ラクシュミがそっけなく言うと、ゆりの体がこわばった。
「離して!」
ゆりが暴れる。だが、ラクシュミは腕をつかみ離さなかった。
「どうせ私はきれいじゃないわよ!」
「もっと太ったほうがいい。そのほうが好きだ」
ラクシュミは、ゆりの手を捕らえたまま言う。
「私は、お前を嫌ったことなどないぞ。お前に好意すら抱いているのに、なぜわからん」
は?
ゆりは、思ってもいなかった言葉にぽかんとしてラクシュミの顔を見た。
「私はお前の容姿がいやだと思ったことはない。角のように他の種族の余計なものもついていないし、お前の肌の色も好ましい」
「・・・」
「今日は、一緒に夕食をとるか」
「え・・・」
「お前がちゃんと食べるかみていてやる」
ゆりは口をあけっぱなしである。
ラクシュミはゆりの頬をなでて、涙をふいた。
「後で人をよこすからな。それまでに、顔を洗って、支度していろ」
ラクシュミが優しく言う。
ゆりは沈黙していた。
なんだか、いつもと様子が違う。
「今は、お前にあまり触れることはないが、時が来れば、お前をもっと愛おしく思えるだろう」
ゆりは意味がわからず首をかしげた。
「一族の者同士なら何も言わずとも相手が理解するものでな。自分の感情を口で説明するのは難しい。時をくれ。私も、すぐには
お前のことを理解できない」
「・・・」
ゆりはじいっとラクシュミの目を見ていた。
自分に興味がなさそうな、冷たい視線は相変わらずである。だが、ラクシュミの手は、ゆりの頬をなでていた。
ゆりはしばらくしてうなずいた。
ラクシュミが出て行った後、ゆりは顔を洗い、ちょっとおしゃれっぽいドレスを着せてもらって、髪をきれいにしてもらった。そう
こうしていると、別の侍女が呼びにきて、ゆりはいつもとは違う部屋に入っていった。客間のような豪華な部屋に長いテーブルがお
いてある。部屋のすみには、ハープをひいている女性がいる。この前の女性ではなく、別の女性だった。ラクシュミはすでに席に座
っていて、ハープの音色を聞いているようだった。ゆりに気づくと、顔を向けて少し微笑んだ。
「そこに座れ」
自分の前の席をさす。
「はい」
ゆりは席についた。すぐに食べ物が運ばれてきた。色とりどりのサラダ、スープ。そして、メインの料理は、鳥のようなお肉を焼い
たものだった。ラクシュミは、それほど手をつけずに、お酒ばかり飲んでいる。
「王様ってあまり食べないんだね」
「いっぺんに食べると頭が回らなくなるんでな。お前はたくさん食べろ」
ラクシュミにみられて食べるのは初めてだったので、ゆりは緊張した。
「王様・・・それ、飲んでみたい・・・」
ゆりは、ラクシュミが飲んでいるお酒を見ていった。この世界に来て、お酒は飲んではいなかった。
「お前はあれだ」
横を見ると、侍女がお茶の入ったポットをもっていた。いつものあれである。
「うう・・・」
「ふふ・・・全部飲んだら褒美をやるぞ」
ラクシュミが微笑んでいった。
「褒美?」
ゆりの目が少なからず輝く。
「ああ。楽しみにしてろ」
ラクシュミの珍しい申し出にゆりは好奇心にかられて、お茶を全部飲んだ。
「ね、王様、褒美って何?」
テーブルの上の食器が全て下げられた。
「お前と遊んでやる」
「遊ぶ?」
テーブルの上に、四角い板が運ばれてきた。そして、大きな箱が二つ。
「バラクというゲームだ。したことあるか?」
「ないです」
「やり方を教えてやる」
ラクシュミはこまを盤に並べていった。
「同じように並べてみろ」
「はい」
ゆりは見よう見まねで並べていく。10センチくらいの人形で、青いきれいな石でできていた。兵隊や、冠をかぶった王様っぽい駒があり、
それぞれいろいろな格好をしている。
全部並べると、ラクシュミはこまの説明をしだした。ゆりは熱心に聴いていた。実際にゲームをしてみる。複雑で難しかったが
ゆりは必死に相手をしようとした。もちろんぜんぜんかなわなかったが。気づくと、3時間も経過していた。
「そろそろやめるか」
「う・・うん・・・」
ぜんぜん歯がたたなかったのが悔しかった。だが、ラクシュミとこんなにも長い時を何かをして過ごしたことはない。
「湯浴みの後、寝室に来い」
「え・・・でも・・・」
「こい」
ゆりはうなずいた。
「王様、遊んでくれてありがとう」
ゆりが微笑んで言うと、ラクシュミも微笑んだ。
とても優しい笑みで、ゆりはみとれてしまった。
どうしたんだろう・・・いつもの王様と、まるで別人みたい。
っていうか、全然違う人だよ。
逆に怖い気がするのはなぜ。
王の寝室の前で躊躇していると、扉が勝手に開いてゆりはびっくりした。
ゆりは寝室に入って行った。
「こっちにこい」
ベール越しに、ラクシュミの声が聞こえてきた。
むわっと花の匂いが漂ってきた。
「・・・すごい匂いがする・・・」
「私の匂いだろう。この時期は、特に夜は、匂いがきつくなる」
「・・・」
「ずっとそこに居る気か?」
「だって・・・姿が変わるって・・・」
「今は変わってはいない」
ゆりは、手を握り締めて、思い切ってベッドまで行った。すると、確かに甘い匂いがきつくなった。ゆりの顔を見ると、
ラクシュミは少し微笑んだ。
「ねえ、もしかして別の人じゃないよね?」
ゆりは恐る恐る聞いた。
「ん?」
「だって・・・今日の王様変だよ。私と遊んだりなんて・・・今まで絶対なかったのに・・・」
「交わりの月だからな。この時期は、敵も子作りに忙しいから、少し余裕がある。性格も変わってるかもしれんな」
「変わってるよ。すごく優しくなってる。てっきり、王様誰かと過ごすのかと思ったのに」
「なんでだ?」
「だって・・・好きな人がいるんでしょ?」
ラクシュミは頭を支えて寝そべり、ゆりを見ていた。
「好きな人?」
「恋人がいるんでしょ?」
「恋人?よくわからんが」
「夜遅い時、たまにその人と過ごしてるんじゃないの?」
ゆりはこの際だと思って聞いた。
「お前の言うことがわからない。それは私が他の女を抱いてるんじゃないか、ということか?」
「うん」
「前に言ったと思うが、我々は交わりの月以外でそう性欲を感じることはない」
「だけど、この前アヤコさんに聞いたら、そんなことないって」
「虎族は別だ。あいつらはいつでも性欲に満ちている。蛇の一族は男も女も性欲が薄い方なのだ。それが問題でもある」
「どうして?」
「交わりの月でも交わらない者もいるからだ。出生率がすごく低いのが私の悩みの種だ。虎族の性欲をわけてほしいくらいだ」
「そうなんだ・・・」
「私も疲れているのにわざわざそんなことはしない」
「じゃあ、王様に恋人がいるっていう噂は嘘なの?」
「大方お前がいるのを知って言われたのではないのか?お前をうらやましがってる女は多い」
「・・・」
「交わりの月の間で、なんとか機嫌を直してくれ。みんな心配していたぞ。私も、お前が笑ってる方がいい」
「うん・・・」
ゆりは少し微笑んだ。
次の日も、その次の日も、ラクシュミは、時間を作り、ゆりの相手をした。ゆりの心は穏やかになり、よく笑うようになった。
ようやく、ラクシュミが身近に感じられるようになってきたのだ。夜には、手をつないで眠ることもあった。
そして、5日目の夜中、ゆりが突然苦しみだした。
「う・・・ううう・・・」
「ゆり?どうした?」
「いた・・・い・・・胸が痛い・・・」
ゆりは体を折り曲げている。
「ゆり・・」
しばらくすると、痛みはなくなった。
「あれ?」
「大丈夫か?」
「うん・・・・なんだったんだろう」
「もう少しだな・・・・」
「え?」
「いや・・・」
交わりの月の間、ラクシュミが話し相手をしたおかげで、ゆりの心は平常心を取り戻した。
赤い月が終わり、ラクシュミはまた忙しい日々が始まり、夜も遅くなったが、ゆりは機嫌が悪くなることもなかった。
逆に王様って大変なのね、とねぎらいの気持ちを持つようになってきたのだ。
食事の時に、すっぱいお茶もちゃんと飲んでいる。
そういえば、王様にこのお茶のこと聞くの忘れてたな・・・
まあいいか。
ゆりの機嫌がよくなったので、ゆりの侍女たちもほっと胸をなでおろしている。
その日ルーと遊んでいたら、フリットがやってきた。
「王妃、今よろしいですか?」
「うん」
フリットは優しい笑みを浮かべて部屋に入ってきた。
「今日は珍しい蛇をお目にかけたいと思うのですが」
「珍しい蛇?みたい!」
ゆりの目が輝いた。
「ではお手をどうぞ」
「はい」
ゆりはフリットの手をとった。すると、一気に城の外に飛ばされた。城の南にある庭園のようだ。
フリットが「ヒュ、ヒュ、ヒュ」と口笛を吹くと、ぱたぱたと空を何かが飛んできた。
「えー!」
ゆりは目を見開いた。それは短い蛇のような姿をしているが、背中にはこうもりのような羽がついていた。だが、顔は蛇だ。
「かわいい!」
二匹の蛇は、ゆりの周りを回っている。そんなに大きくはない。長さも30センチほどだろうか。
「有翼蛇ですよ。そんなにはいないんですが」
「おもしろーい」
ゆりは手を出してみた。すると、蛇はぺろりとゆりの指をなでた。ゆりのニコニコ顔を見てフリットは微笑んだ。
ラクシュミとゆりの仲を、他の者たちも何気に気にしていたのだ。
「あれ?」
ゆりは体に違和感を感じた。
「どうしましたか?」
「ううん。なんでもない」
なんだか胸がちょっと痛かったけど・・・直った。変なの。
「お部屋に戻りますか?」
「うん。ありがとうね。また見せてね」
「はい」
ゆりはそのまま部屋に戻された。
それから何度か胸が痛むことがたびたびあった。といっても苦しいってほどではないので、ゆりはほっておいた。
そして、交わりの月から一ヶ月ほど過ぎたころ。
その日は天気がとてもよかったので、蛇に混じってゆりは芝生に座っていた。
するといつの間にやらうとうとしてしまい、ゆりはごろんと横になって眠ってしまった。
しばらくして、身体を揺り動かされて、ゆりは目を覚ました。
「王妃、こんな所で寝ちゃだめですよ」
「ううん・・」
上を見ると、ミカエルの顔があった。
「おめでとうございます。王妃」
「?何が?」
ゆりはぼんやりしていた。ミカエルは微笑んだ。体の上には、なぜかミカエルのマントがかけられている。
「・・・あれ?」
ゆりはマントをめくってぎょっとした。自分の胸に、何か見慣れないものがある。
「ようやく大人になられましたね」
「え?・・・」
「えー!」
ゆりは自分の胸を見て悲鳴をあげた。
なんと、胸が二倍以上に膨らんでいた。