第9話
ゆりはその日、調理場にいた。
何か新しい料理を作ってレシピをアヤコの元に送ろうと思ったからだった。同盟国には一応宅急便のようなものが
あり、アヤコとは手紙のやりとりはしていた。アヤコはとてもゆりのことを心配しているようだった。
最近はラクシュミとの関係も良好なので、安心しているようだ。
ゆりの横にはミラもいる。
「何かお魚が食べたいな」
ゆりがぽつりと言った。
「魚ですか?」
ミラが聞く。
「うん。あんまり魚ってご飯に出てきたことないね」
「そうですね。食べる習慣があまりないんですよ。こちらでは」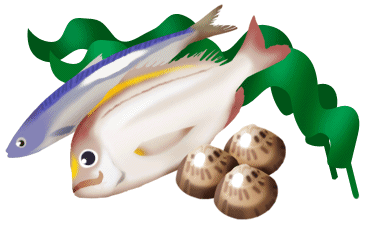
「ミラは食べないの?猫族って魚好きそうだけど」
猫は魚が好きという先入観でそう聞いた。
「私は鳥肉が好きですから」
この蛇の国は海に面していない。そのため、海にある食べ物はあまり食べる習慣はないようだった。
国境は山と川に囲まれている。
海草のようなものはあるけれど、貝などは食卓にあがったことはない。
ちなみに家畜は鶏っぽい鳥や、豚っぽい生き物がいる。牛はいないが牛よりも小さい牛とヤギのあいのこのような
奇妙な動物がいる。
「干物が食べたくなってきた。作れないかなあ・・・」
「ひもの?」
その時、フリットが顔を見せた。
「王妃、今日は何を作るんですか?」
「あ、フリット、ねえ、フリットって魚釣りとかしない?」
「魚釣り?ああ、ああいうのんきなシュミはないですが・・・なぜですか?」
フリットはきょとんとして聞いた。
「向こうでは結構お魚食べてたから、魚がすっごく食べたくて、川魚とかとってきてほしいな」
ゆりはかわいげに言ってみた。
「いいですよ」
「本当?」
「はい、じゃあ適当にとってきます」
「ありがとう。フリットって優しいのね」
ゆりはニコニコである。
午後には届けてくれる、というのでゆりは待っていた。すると、昼食後、布袋をかついだフリットが調理場にやってきた。
「はい、どうぞ」
ゆりが中を見ると、かなり大量な魚が入っていてびっくりした。50匹はいそうだ。
「え・・これ一人で釣ったの?」
「水蛇に取りにいかせました」
「へー」
魚はぴちぴちはねていた。大きいのやら、小さいの、なんだか変な形をした魚がいる。すると、大きな蛇がするする
近づいてきた。
「食べたい?」
ゆりが聞くと、蛇は袋の中に顔を突っ込んで魚を口に入れた。
蛇が食べるということは、食べれる魚なのだろう。
「わーい。とりあえず塩焼きにして食べよっと」
ゆりは大喜びで適当に魚を選んで焼いた。フリットは出て行き、ミラはゆりの横でじっと見ている。
「おさかな。おさかな〜」
しばらくすると、香ばしい匂いが漂ってきた。
「わーおいしそう」
ゆりは魚を一匹とって、ちょっと食べてみた。すると、白身魚風味で、結構おいしい。
「おいしいよ、ミラ食べてみて」
「はあ・・・」
ミラも少し身を食べてみた。
「・・・おいしいです」
妙な間があってミラは言った。
「本当に?」
「はい、魚初めて食べましたけど、こういう味だったんですね」
ミラはにこっと微笑んだ。
「じゃあ次は、魚のから揚げとムニエルとかつくろうかな。いっぱいつくって誰かに食べさせようっと」
料理人まで巻き込んで、ルンルン気分の魚料理作りが始まった。
「アーいっぱい料理作るのって楽しいね。私って料理人向きかも」
やがて、大量の魚料理ができあがってきた。
「ねえ、ミラ、だれか適当に呼んできて、試食会」
「は〜い」
ミラが出て行った。
ゆりが魚のからあげをつまんでいると、
不意に目の前にアヤコが現れた。
「アヤコさん!」
「ゆりちゃん!あ!お魚ー!!!!!」
アヤコの目はきらきら輝いていた。
「食べていいよ。アヤコさん!」
「ゆりちゃん・・・」
アヤコは涙ぐみながら魚料理を食べだした。
「おいしい・・・おいしいわ。向こうの味がする・・・ゆりちゃん、お願い、梅干と味噌つくって」
「それはさすがに難しいよ・・・」
アヤコの食べるスピードはすさまじく、ゆりも横にいた料理人も、あっけにとられてみていた。
やがて、全部なくなった。
は・・・はやっ
まるでテレビで大食い選手権でもみているようだ。しかし、アヤコのおなかは全然膨れてない。
一体どこに食べ物は消えているのか不思議だ。
「アヤコさん、これ、夕ご飯に焼いてもらって」
ゆりは残りの魚の袋をアヤコに渡した。
「ありがとう・・・あれ?私どうやってきたんだろう・・・帰り方わからない」
「アヤコさん、あれ」
ゆりは入り口あたりにいた蛇をさした。
「ぎゃあ!蛇!」
アヤコはそういって消えた。
その時、ぞろぞろと男の人が調理場にやってきた。ミラは、テーブルの上にあった皿を見てあれ?といった。
「さっきアヤコさんがきて全部食べちゃった」
「あらら」
その時、何気にほっとした顔をした男たちにゆりは頬を膨らませた。
ひどい・・・全然信用されてない・・・
その夜、ちょっと遅めにきたラクシュミは、ゆりがまだ起きていたので声をかけた。
「今日アヤコがきたそうだな」
「うん。料理また食べられちゃった。でもどうやって気づいてくるんだろうね。不思議」
まさか向こうまで匂いが漂ってるわけでもないだろうし・・・
恐るべし食に対する欲求!
「私も妊娠したらああなるのかな」
「違う国に行かれるのは困る。それに虎の一族は大食漢だからな」
「・・・」
ゆりは何気なくラクシュミに近づいた。
「フリットが、お前がきれいになったといってたぞ」
「え?」
ゆりの頬がちょっと染まった。
「よかったな。ほめられて」
「うん・・・」
フリットって優しくていい人よね。
でも、ヴィラのほうが気になるなあ・・・
いまだにヴィラの顔はうっすらとしか見えない。向こうはこっちの体は全部見えているのに、
ちょっとずるいような気もする。
その夜は、ラクシュミはゆりを抱き寄せて寝てくれた。
だが、それから10日ばかり、ラクシュミはゆりにそっけなかった。話しかけても「ああ」とか
くらいしか返さないし、なにやら近づいてほしそうにない感じである。
なんなの・・・変な人・・・
もしかしたら何かあったのかな?
ゆりはそう思い、ミラに聞いてみた。だが何も起こってないとミラはいった。
そうこうしていると、夜、ヴィラがやってきた。
「久しぶりね」
ゆりが言った。あれから、10日以上は経過している。
「そうですね。会いたかったですか?」
「そういうわけじゃないけど・・・」
ヴィラがゆりの横に座った。
「ねえ、王様って、感情にむらがある人?」
ゆりは聞いた。
「むら?」
「時々機嫌悪い時あるから・・・」
「だれだってそうでしょう。」
「そうだけど・・・ちょっと前は極端に機嫌悪かったよ。何か事件でもあったの?」
「いいえ。ああ・・・ちょうど月がなかったからでしょう」
ヴィラが思いついたように言った。
「月?」
「我々は月に結構左右されますよ。月がない夜は、かなり感情は沈みがちになりますし、薄い三日月の時もそうです。王の
力も、どうやら少し関係しているようですから、機嫌が悪い時は、体がお辛いのかもしれません」
「そうなんだ・・・」
「今夜は半月ですから、王の感情も少し回復してるようですよ」
「へーじゃあ、月を見て王様に接したらいいんだね」
「そういうことです」
「そういうのは早く知りたかったなあ・・・」
ゆりが口を尖らせる。
「こういうことは本能的なことですからね、みんなわかってると思ったんじゃないでしょうか」
「そうかな・・・」
ヴィラが何気に腕を回してきてゆりはどきりとした。
「・・・ねえ、ヴィラって恋人いないの?」
「恋人?聞いてどうするんです?」
「だって、いたら悪いから・・・」
「悪い?」
「あなたの恋人がこのこと知ったら、いやでしょ?」
「逆に喜びますよ?」
「え?なんで?」
「王妃にはだれでも触れられるわけじゃないですからね。名誉なことなんですよ。もうひとついえば、
我々は恋愛感情に薄いたちでしてね。愛し合っている恋人ってのは珍しいんですよ」
「・・・じゃあどういうのが恋人なの?」
「交わりの月を毎年過ごす相手は恋人といえます。我々にとっては交わりの月に女を抱くのは
義務のようなものですから、あなたが思っているようなのんきなものじゃないんですよ」
「・・・そうなの・・・じゃあ結婚とかしないの?」
「夫婦というのはあなたと王だけですよ。一族の者は他はだれもそういう関係にありません」
「え?そうなの?」
ゆりは驚いた。
「長年同じ相手と過ごしている者もいますがね、力が強い男はたいてい複数の女がいますよ。だれでも強い男の
子供がほしいですからね。」
「じゃあ、ミカエルとかは?」
「相手いっぱいいますよ」
ガーン・・・
「ミカエル殿は女性の人気も高いですからね。力のある女を五人ほど独占してますね」
・・・ミカエルのイメージが・・・・
「お話はそれくらいにしましょう」
「今日は何するの?」
「王が来るまでいちゃいちゃ」
ヴィラはゆりの体を抱き寄せた。
そして優しく口付けて、体に触れた。
三回目ともなると、ゆりもちょっと安心してきている。
裸にされて、胸に触れられた。胸の先端に触られて、ゆりはびくりと体をふるわせた。
「あなたの肌は、とても柔らかくていいですね。」
「・・・・」
「体の中も・・柔らかい・・・」
ヴィラの指が下半身をまさぐり、やがて、中に入ってきた。
「あ・・・」
「随分感じやすくなりましたね。王妃、」
「・・・・」
体の奥が潤ってくるのを感じる。
「や・・・だ・・・」
指の動きが激しくなった。
「あ・・・やあ・・・」
胸をなでられながらも体の中を指でかき混ぜられて、ゆりの体はやがてびくんとのけぞった。
「いってしまったんですか?」
「・・・・」
「もう一度ね」
再びゆりは愛撫された。
やがてヴィラが去り、入れ替わりにラクシュミが来てゆりは抱かれた。
体の中に、ひんやりとした感触がする。
「お前は体の感触はいいのだが、体温が高いのが難点だな」
ラクシュミが言った。
ゆりは抱かれて、いく瞬間、体を突き抜けるほどの快楽を感じて驚いた。
体の中からじわじわと何かがめぐるような感じがする。
終わったあと、ゆりはぼんやりしていた。
「どうした?」
「・・・なんだか・・・抱かれてる時、むわっとしたものがきたの」
「気づいたのか?気をちょっとやったのだ」
「気・・・なんだか気持ちよかった」
「そうか?」
「気をもらうのって、なんかいいね」
「お前のそのブレスレットには、相当の気が入ってるぞ。お前は私に引っ付いて寝てる時も、少し気を奪っているから
な。すでに、結構な一族の気質を帯びているぞ」
「そうなの?もっとほしいな。気」
「あまりやると私が困る。」
「気って引っ付いてるともらえるの?」
「ああ。お前は夜は無意識にやってるが。なんなら今度ヴィラにもらってみたらどうだ?」
「ヴィラに?」
「気はもらいすぎて悪いということはない。だが、あまりもらいすぎるんじゃないぞ?ヴィラが死んでしまうからな」
「うん。今度もらってみる」
体を通して送りこまれた気がとても気持ちよかったため、ゆりは他人の気というものにちょっと興味をもってしまった。
その三日後、ヴィラが来た。
「こんばんわ。王妃」
「こんばんわ」
「・・・4回目ともなると全然驚かないんでつまらないですね」
ヴィラが言った。
「そんなことないよ。ただ、今日は夕方王様から聞いたの。今夜ヴィラがくるって」
「なんだ・・・今日は何か聞きたいことありますか?」
「・・・ヴィラってどのくらい力あるの?」
「私?上、中、下、のランクでいえば、中ランクの、上の方ですね」
「ミカエルとかフリットは?」
「あの二人は上ランクの中くらいですね。」
「上ランクの上ってだれ?」
「4人の将軍たちですよ。四方の砦にいらっしゃいます」
ゆりは結婚前将軍たちと顔をあわせていた。結構年齢も上の方だった。
「私、もしかしてヴィラの顔みたことある?」
「ありますよ。結婚前に王の間で」
「そうなんだ・・・」
その時は大勢いたので、どの人がヴィラだったか、なんて検討はつかない。
「ヴィラの髪って・・・銀色?」
「純粋な銀色ではないですよ。」
「じゃあどんな色?」
「秘密」
「なんでよ」
ゆりが頬を膨らませる。
「いつ顔見せてくれるの?」
「まあそのうちにね」
「・・・ねえ、抱きしめて」
ゆりが言うと、ヴィラは沈黙した。
「今日は、あれはないんです。お話だけ」
「そうなの?でも抱きしめて」
「・・・なぜです?」
なにやら警戒しているようだった。
「私を愛してる、とか言い出さないでくださいね。王妃」
「言わないよ。そんなこと」
「ならいいですが・・・」
「ただ抱きしめてくれるだけでいいから」
「・・・」
ヴィラはゆりの体を抱き寄せた。
ゆりはヴィラの背中に腕を回して、ヴィラの気を奪うように念じてみた。
すると、むわっとしたものが体にきた。
あ・・・成功
「!?」
ヴィラは驚いてゆりの体を離した。
「今何しました?」
「気もらった」
「気?・・・・げ・・・」
ヴィラはゆりの体を見て眉をひそめた。ゆりの体をきれいな淡い金色の気が取り囲んでいたのに、それに緑色の
ヴィラの気がちょっと混じっている。
「・・・それならそうと、なぜ言わないんです」
「初めてだったから、できるかどうかわからなかったし・・・」
「・・・10分の1ほどもってかれましたよ?」
「え?そんなに?でも、この前王様からもらったのは、もっと多かったよ?」
「それは気の量が全然違うからですよ。全くもう驚いた」
「ふふ・・・」
ゆりは喜んでいる。
「ふふじゃないですよ」
「だって・・・楽しいもん。ヴィラを驚かせることができて」
ヴィラはため息をついた。
「それじゃ、今日はもういきます」
「うん。さよなら」
ヴィラは瞬間移動で出て行った。
・・・あの時王様にもらった方が気持ちよかったなあ・・・
ゆりはその後寝室にきたラクシュミにねだってみたが、疲れてるからだめだと言われてしまった。
次の日、ミカエルが部屋にやってきた。
「はい、お菓子ですよ。王妃」
「ありがとう」
ゆりはほほえんでミカエルを見た。
いつ見てもいい男・・・
「今日はどうしたの?」
「実は休みなので、ご機嫌伺いに・・・」
「そうなんだ。入って」
「はい・・・」
ミカエルはゆりの体の周りをじっとみている。そして奇妙な顔をした。
「ねえ、ミカエルってバラクできる?」
「できますよ」
「よかった。相手して。侍女はだれもできないの」
「いいですよ」
ゆりはゲーム盤とこまをもってきてテーブルにだした。
「バラクいつ習ったんですか?」
「この前の交わりの月の時、王様が教えてくれたの」
「そうですか」
ゆりはうれしそうな顔でゲーム盤を並べている。ミカエルは自分のこまを並べながら、ゆりを見ていた。
「え?何?」
「王妃はとても美しくなりましたね。幸せそうで、私もうれしいですよ」
「・・・前に迷惑かけたもんね」
ミカエルはほほえんだ。
「・・・ところで、体調は悪くないですか?」
「普通よ。」
「何か変わったことは」
「ないよ?」
「・・・・」
ミカエルが奇妙な顔をして、ゆりも首をかしげた。
二人は駒を並べて、ゲームを始めた。
・・・おかしいな。なんで王妃の気はこんなに奇妙なんだ?
ミカエルは考えたがわからなかった。
「ねえ、ミカエルって、いっぱい恋人いるんだってね」
ゆりがそういうと、ミカエルはぎょっとした。
「だれがそんなこと言いました?」
「え?そういう噂聞いたよ。」
「ただの噂ですよ」
とミカエルは強調して言った。
その時、ミラがお茶を運んできてくれて、ゆりはミカエルにもらったお菓子を開けた。
クッキーのようなものが入ってる。
ミカエルはじろりとミラを見た。
「な、なんですか?ミカエル様」
ミラの猫耳がぴくりと動いた。
「なんか私の変な噂が流れてるようだが・・・ミラじゃないよね?」
「私はナーンにも言ってませんよ?」
「ミラに聞いたんじゃないよ」
ゆりが言う。
「じゃあだれです?」
「だれって・・・力の強い人は、複数の恋人がいるもんだって聞いたよ。ミカエル力強いんでしょ?」
「別に恋人じゃないですよ。ただ、交わりの月を過ごす仲なだけです」
「・・・どう違うの?」
「全然違いますよ」
ミカエルはニコニコして言っている。ミラは後ずさって逃げていき、ゆりはそれ以上聞かなかった。
ゆりは話題を変えた。
「ねえ、ミカエルって、いろんな一族の男の人知ってるよね?」
「成人してる男なら全員知ってますよ」
「ヴィラってどんな顔?」
その時、ミカエルの駒を進める手が止まった。
「ヴィラ?なぜです?」
「なぜって・・・なんとなく・・・どんな顔かなって・・」
「・・・」
ミカエルはゆりの体をまとう気をみた。ところどころにある緑の気。
そういえばあいつも緑の気質だったな・・・
しかもなぜか王妃の頬が赤くなってるのも気になる
「ヴィラにあったことあるんですか?」
「ないよ」
ますますゆりの頬が赤くなった。
「ここに呼んであげましょうか?」
「え?」
ゆりはぎょっとした。
「私は一族の者全員と思念を交わすことができますから、ヴィラを呼ぶこともできますよ」
「だ。だめ。絶対だめ、呼んじゃだめ!」
ゆりはあきらかにおろおろして言った。
「顔が見たいんじゃないんですか?」
「ううん。みたくない」
首まで赤くなっている。
どうもあやしい・・・
ミカエルはそれ以上追及しなかったが、ゆりの部屋を出た後、王の休憩室に行った。
ラクシュミはでかい長椅子に寝そべって休んでいた。
「お前今日は休みじゃなかったか?」
ラクシュミがミカエルを見て聞いた。
「さっき王妃にあったんですが・・・すっかり幸せそうで安心しました」
ミカエルは違う椅子に座りながら言った。
「そうか」
「ところで王、私に何か隠してることがありますね?」
ミカエルは意味ありげにラクシュミを見た。
「・・・・あるかもな」
「・・・王妃の気に王族以外の気が混じってましたがどういうことでしょう」
「さあどういういうことだろうな」
「しらばっくれるんですか?」
「まあいいじゃないか、どうでも」
「何がいいんですか。私は王妃を誘惑したいのを我慢してるのに・・・」
ミカエルはゆりが聞けばぎょっとするようなことを言い出したが、ラクシュミは顔色も変えない。
「ゆりはお前の好みじゃないだろ」
「好みの問題ではなく、かわいらしいと思ってるんです。性格が」
「・・・ゆりに言うぞ」
「あの黒髪も好きです。肌も柔らかいし。それに大人になってぐんと色気がでてきましたし」
「お前は手を出すんじゃない。ゆりがお前に本気になったらどうする」
「・・・」
「せっかくゆりと私の仲がましになってきたんだ。今はあんまり近づくな」
「わかりました」
ミカエルは口を尖らせて言った。
「だがゆりに気をやるだけならいいぞ」
「気をやる?」
「体をひっつけたら気をやれる。ゆりは自分で一族の気はつくれない。他人からもらうしかないんだ」
「そうですか」
ゆりは全く知らなかったが、蛇の一族の王妃は、一族の男に限り、どの男でも恋人にすることができる、という特権
のようなものがあった。王妃の恋人、というのは、交わりの月以外で、肉体関係になる男のことである。といっても
愛しているから交わるという仲ではない。王妃が交わりの月を無事王と過ごすためでもあるのだった。いわば、
交わりの月の練習である。王妃は、他の男とそうなったからといってその男を愛することは絶対にない。王と王妃の
絆というのはそれほど強いものなのだ。王妃にとっては王の子供を産むということが使命のようなものだからだ。
だがゆりは一族の女ではないので、感情的に大きくずれがある。そのために、一族の男には絶対にゆりを誘惑しないように
と言ってあったのだった。
ラクシュミと離れて、城の中を歩いていたミカエルは、本当に偶然ヴィラとすれ違ってぎくりとした。ミカエルが
じっとにらんでくるのでヴィラもミカエルを見た。
「なんですか?」
ヴィラが聞いた。
「・・・今ちょっと時間あるか?」
「ないです」
即答だった。
「じゃあ夜は」
「なんなんです。一体」
ミカエルとヴィラは、親しく話を交わす仲でもないし、一緒に酒を飲んだこともない。ヴィラが不審な顔をするのも
当然である。
「ちょっとこい。少しでいいから」
ミカエルはヴィラに触れて強引に瞬間移動させた。そこは、だれも使っていない城の中の一室だった。
「一体なんなんですか」
ヴィラが不愉快そうに言った。
全く・・・相変わらず目つきの悪いやつだ・・・
青みがかった銀色の髪、瞳も青い。冷たい顔立ちの男だった。美形とは言えるだろうが、その目つきのせいで
ひどく冷たく見える。
こういう男にゆりが興味を持つということがミカエルは解せない。
「お前、王妃にあったことがあるのか?」
ミカエルが聞くと、ヴィラは目を見開いた。
「王妃?なんですか。突然」
「なぜか王妃がお前のことを気にしていた」
「はあ。私は知りませんよ。そんなの」
「顔は知らないのに気にするってのはどういうことだ?」
「私に聞かれてもしりません」
「・・・」
二人は沈黙した。
「そうか。悪かった」
ミカエルが言うと
「では」と言ってヴィラは消えた。
ミカエルとしても何の確証もなかったからヴィラを問い詰めても仕方ない。
その夜、ゆりが王の寝室に入ると、中は真っ暗だった。
「暗い。みえないよー」
いつもは灯りがついているのになんでだろうとゆりは両手で周りを探りながら前に歩いていった。
すると、不意にその手が握られて、ゆりは、きゃっと声をあげた。みると、前に誰かいる。
「あ・・・ヴィラ?」
暗闇で見える銀色の髪は、ヴィラのようだった。
「こんばんは」
「昨日の今日でまた?」
「いいえ。今日は話をしに来ただけです」
「そ、そうなの?」
「今日はにおいが違いますね」
「うん。お風呂に香油入れたから」
「そうですか。いいにおいですよ」
「ほんと?」
ゆりがうれしそうな顔をする。
「ちょっと座りましょう」
「うん」
ゆりはベッドにちょこんと座った。横に座ったヴィラの顔をジーと眺めている。
「あなたはよっぽど私の顔が気になってるようですね」
「だって・・・みたいんだもの・・・」
「ミカエル殿に私のこと言ったでしょう。渋い顔で問い詰められましたよ?」
ヴィラは冷静な口調で言った。
「ごめんなさい・・・つい・・・」
「だめですよ。この役を一番やりたいのはあの人だったんですからね」
「え・・・なんで?」
「あなたが一番位が高い女だから」
「それだけの理由?」
「無論、あなたに好意があるんでしょうがね、あなたは彼のこと好きなんですか?」
「え?好きだよ。ミカエルってかっこいいし・・・優しいし・・・」
ゆりの頬が赤くなった。
どうも危険だな。この人は・・・
情にほだされやすいようだ・・
これじゃああの人が手を出したらころっと行きそうだな。
ヴィラは、ゆりの性格を大方把握していた。
純真で素直すぎる。
王のために他の男に抱かれる、だなんてできないだろう。
優しくされるとその男にまで情をもってしまう。
過ぎた情は危険だ。
「王以外の男に変な感情もたないでくださいね」
「もたないよ。ねえ、どうしてあなたがこの役選ばれたの?」
「さあ、どうしてでしょうね。」
「女の扱いに、な、慣れてるから?」
ゆりはちょっと恥ずかしそうに聞いた。
「実は、私は、美男って方じゃないんですよ。だから選ばれたんです。私なら、あなたが好きにならないから」
「嘘。一族の人って、たいてい美形だよ。男も女も」
「何事にも例外はありますよ」
「そういわれると余計に気になる・・・」
「顔を見ると肌に触れられたくなくなるかもしれません。」
「そんなことないよ。私、あなたの声好きだし、それに、王様はそんな理由であなたを選んだわけじゃないよ」
ゆりは慰めるように言った。
「・・・・いけませんよ。王以外の男の顔を凝視したりしては」
「だって、どうせ顔見えないし・・・」
「それに、好きという言葉は王以外に使ってはいけません」
「はい・・・」
「・・私はそろそろいきます。ではまた」
ヴィラは、姿を消した。瞬間移動したのだ。
ゆりは一人残された。
なんか胸がどきどきする。
これって逢引みたいなものだもんなあ・・・
顔も見えない男との逢引かあ・・・・
美男ではないといっていたけど・・・
もしかして、私って気が多いのかも?うう、気をつけなきゃ。
その夜も、ラクシュミがベッドに来たのはかなり遅かった
ゆりは起きていたが、ラクシュミが疲れているだろうと思い、話しかけなかった。
「まだ寝ていないのか」
ラクシュミが聞いた。
「え?わかるの?」
「目を開けているだろう」
「・・・見えるの?真っ暗なのに」
「ああ。お前、機嫌はどうだ?」
「とてもいいよ。」
「そうか。」
ラクシュミはそれきりはなしかけなかった。
時折確かめるようにきく。機嫌は悪くないか、と。
一応は気にしてるみたい。
その次の日、女戦士のジュメが尋ねてきてくれて、ゆりは驚いた。あの虎の国の一件以来、あっていなかった。
「ジュメじゃない!もう、どうして今まできてくれなかったの?」
「すいません。私は純血ではないので、気がとがめて」
久しぶりにジュメの顔が見れて、ゆりはうれしかった。
ジュメも、うれしそうなゆりの顔を見て、顔がほころんでいる。
「ミラ、何かお菓子とお茶もってきてね」
「はい」
ミラは部屋を出て行った。
「あの時迷惑かけたままだったから気になってたの」
ゆりが言った。虎の国に行って帰らないと駄々をこねてしまったことを思い出す。
「よかったです。王妃が楽しそうにしてらして。ミカエル様に王妃の様子はよく聞いてたんですよ」
「そうなんだ・・・」
しばらくして、お茶とお菓子が運ばれてきた。
「ミラもここ座りなよ」
「はい」
「実はさ、よくわからないことがあるの」
ゆりはお茶を一口飲んでいった。
「なんですか?」
「蛇の一族の恋愛感みたいなもの?夫婦って私と王様だけなんだってね。」
「そうですよ。仲の良い男女でも、あまり一緒に住んだりはしないですね。普段、一緒のベッドで寝ることもない
ですし」
「え?そーなの?」
「一族の女性は、普段男に触れられるのをあまり歓迎しないんですよ。男もそうですよ」
「え・・・じゃあ王様って、かなり我慢してる?もしかして」
「王は夜しか王妃といられませんからね。一族の女性ならほっとくでしょうが、王妃はほっとかれるのは
いやでしょう?」
「うん。・・・それから、一族の女性たちに、いまだにあまりあってないんだけど・・・みんなまだ私に
わだかまりがあるのかな」
時々すれ違う程度で、ゆりはいまだ一族の女性たちと楽しく話をしたりはしていない。
侍女たちがいるのでさびしくはないのだが。
「そうですね。まあ、それはしょうがないですよ。そのうちに、みんなの心も変わってきますよ。」
「そうですよ。王妃」
ミラも励ますように言った。
「うん。そうね。」
きっとそのうちにみんなと仲良くなれるよね。
その夜遅く、ラクシュミは寝室にやってきたものの、倒れこむように眠ってしまった。
ひどく疲れているようだった。
王様・・・
王は一人で結界というものをつくっている。その結界は夜寝ている時も、作り続けねばならないらしい。
敵は国の中に潜んで結界が消えるのを、ずっと待っているのだとか。
王様って大変なんだなあ・・・
私も何か手伝えたらいいのにな。
ゆりは、左腕のブレスレットをはずした。これには蛇族の力が込められているという。
ゆりはそれをそっと布団の上からラクシュミの胸元に置いた。
王様の助けになりますように。そう願いながら。
―ここは・・・どこだ・・・
景色がゆがんで見えた。ラクシュミは、めまいを感じて頭を押さえた。
「・・・様!」
「父様、大丈夫ですか?」
自分の体に触れる手があった。
父様?
横にいる人物を見た。よくは見えない。だがまだ成熟はしていない少年のようだ。
そして、近づいてくる足音。
「どうしたの?父様ぼんやりして」
少女だった。銀色の、流れるような髪。金色の瞳が心配げに自分を見上げた。
「休んでください。たまには僕らに任せて」
少年が言った。ラクシュミがその顔を見る。銀色の長い髪を後ろにしばっている。
その顔立ちは・・・
少年のころの自分に瓜二つだった。
「そうよ。父様、結界の力不足は、攻撃力でカバーするから」
と、少女。
「父様〜」
目の前に黒髪の少女がぱっと現れて抱きついてきた。こちらは、銀の髪の少女よりはかなり幼い。
黒い髪を頭の上のほうで縛っていた。瞳も黒い。
「だめよ。父様は疲れてるんだから」
銀の髪の少女がいう。
「そうなの?大丈夫?」
黒髪の少女が自分の顔を見あげた。大きな瞳をしていた。
「・・・どうやら迷っておられるようだ」
少年が言った。
「え?」
「迷う?」
「父様、またお会いしましょう」
少年が、ラクシュミの手を握った。
「・・・・」
ーいずれ・・・また・・・
「うう・・・」
ラクシュミは頭を押さえた。
どうやら変な夢を見たようだ。
体を起こすと、何かがころがり、ラクシュミはそれを拾い上げた。それは、ゆりがいつもしているブレスレットである。
なぜ?
ラクシュミは、ゆりを見た。ゆりは眠っている。
変な夢を見たのはこれのせいか・・・
ラクシュミは、ブレスレットを見つめた。夢で見た3人の顔を思い出す。
顔はよく思い出せなかった。
ラクシュミは指おり何かを数えだした。
「・・・・」
銀の髪の少女、少年、黒髪の少女、
この前にみた黒髪の男。
あの時の女性は、さっきの少女と一緒だろう。多分。
ゆりが会った男は、さっきの少年と一緒なのかどうか。
確か短い髪だといっていたような・・・
さっきの少年の髪は長かったな・・・
ラクシュミはぞっとしてゆりを見た。
ゆり、一体お前、何人子供産むんだ?
進む